冒頭のアクションヒント - 隕石リスクと神話を科学的に理解し、現実的な備えや視点転換に役立つ提案集
- 月1回、NASAやJAXAなど公式サイトで最新の隕石接近情報を確認する。
衝突確率は0.01%未満が大半だが、正確な状況把握で不安や誤情報から距離を置ける。
- 家族・知人と緊急時の集合場所・連絡方法を2パターン以上決めておく。
巨大隕石だけでなく地震・津波にも応用でき、不測の災害時に生存率向上。
- "空から火"など神話伝承5件以上調べ、自分なりの科学的背景も考察する。
`昔話`が災害リスク啓発へ変わり、防災意識や歴史観にも深みが出る。
- (7日以内)地元自治体サイトか防災アプリで「天体衝突」含む危機管理マニュアルを探して保存する。
"もしも"への具体策入手で動揺せず対応準備できる。数分投資するだけでも安心感アップ。
古代人が空を恐れた理由と宇宙災害の由来を知ろう
空というのは……昔から、なんだか妙に人を惹きつけたり、時には怖がらせたりする不思議な存在だった気がする。いや、ぼんやり眺めてるとわかるが、天体とか宇宙の動きをベースにした世界観――これ、古代の話だけじゃなくて、とどのつまり、人間ってずっと空を見上げ続けてきたんじゃないかなあ、と。例えばストーンヘンジみたいな古石建築、それにピラミッドとかね(どれも有名すぎ?)、そういう巨大なものも大抵、天体の巡りにちゃんと合わせて配置されているケースが多いらしい。彗星だの隕石だの、空から降ってくる不可解な光景は災難の前兆だと思われてた節もあるし……。なんというか、その畏敬――むしろ恐怖かな。ファイアーサーペント(火蛇)について語り継ぐ伝承は驚くほど幅広い。ネイティブアメリカンだけでなくギリシャにも北欧にもヒンドゥーやオーストラリア原住民文化にも存在していて、多くの場合、彗星そのものが“死”とか“滅亡”を象徴する何かとして語られていたっぽい。一応補足、「ディザスター」という単語自体もラテン語やギリシャ語で「悪い星」みたいな意味になるとかで。この短命で、一見すれば華麗とも言える彗星なのに……どうしてこんなに強烈な畏れの感情を抱いてしまうんだろう?正直言えば、本能的になんとなく脅威を感じ取っていた気もしなくはないし、それとも…本当に過去に悲劇的な出来事――実際彗星絡み――が起きて、その記憶が消え切らず残っていた可能性さえ捨てきれない。
そして二十世紀も末期近くなると、「地球外から何か突っ込んで来る」概念自体がガラリと様変わりすることになった。六千六百万年前、大型小惑星衝突によって恐竜絶滅へ至ったこと――まさしくその事実こそ科学界のみならず一般市民へまで衝撃的に広まり、それ以後、人々の心にも深い影響を刻むことになるんだから。(ちょっと考え込んじゃうよね)
そして二十世紀も末期近くなると、「地球外から何か突っ込んで来る」概念自体がガラリと様変わりすることになった。六千六百万年前、大型小惑星衝突によって恐竜絶滅へ至ったこと――まさしくその事実こそ科学界のみならず一般市民へまで衝撃的に広まり、それ以後、人々の心にも深い影響を刻むことになるんだから。(ちょっと考え込んじゃうよね)
隕石衝突リスクや恐怖を示す最新の科学的事実を把握しよう
銀河同士の衝突――なんて、一昔前はSF小説とかの話題だと思ってた。実際に地球に明確な影響が現れることなんてないんじゃないかと、ずっと高を括ってた自分もいた。でもね、気付けばそんな空想どころか、最近じゃ無視できない実データが山積みになっている。ふぅ……まあ数字ばっかり眺めすぎると逆にピンと来なくなるものだけど、例えば最新の推計によれば、年およそ6,100個以上もの隕石が地球の大気圏へ落ち込んでいて、単純計算でも一日に十数回(正確には17回を超えるらしい)もドカンと落下している状況なんだとか。あれこれ連想してたら古代人はどう感じただろう…と思ったけど、とりあえず今、本筋へ。
実際、その多くは上空何十キロの成層圏辺りで儚く燃え尽きる運命みたい。でも、ごくわずか──ほんとうにごく一部だけど──奇跡的に地表まで届くらしい。チェリャビンスクでは2013年、広島型原爆30発ぶんという呆れるほど巨大なエネルギーを放つ隕石が爆ぜてしまい、1,200人以上が怪我する事態にまで至った。息詰まる衝撃だったな……技術発展云々より「無力さ」を噛み締めさせられた瞬間。しかし過去にも例があって、記録によれば1908年にもシベリア・ツングースカで桁違いな出来事(2,000kmにも及ぶ森林が薙ぎ倒される災禍)が生じている。
もし仮に、それら彗星や隕石群──うん、名前はいろいろあるけど、ともかくヤバイ物体たち──が近代都市部へ直撃していたら、人類史を書き換えていただろうし、その惨事は到底語りきれなかったんじゃないかなぁ。怖い話。でも一方で対策?万全とは到底言えそうもない現実だ。NASAでは「潜在的危険天体」とされるものだけでも50万個規模だと見積もっているみたいで。でも皮肉なことに、そのほとんど……約498,000個については現在位置すら追跡不可のままだとも公表されてる。それなのに2021年には、小惑星が地球軌道ギリギリまで接近したこと自体、「通過後」ようやく察知したという滑稽さすら覚える出来事まで起きた。それゆえというべきか、「想定外」への備えとして監視・緩和・リスクマネジメント、この三本柱そのものをもっと創造的かつ柔軟性を持って強化していかなきゃダメなのでは、と改めて痛感する次第。
### **見えざるインパクトと忘却された危機**
惑星表面には大きく口を開いたクレーター跡などが名残を留めてたりするものだけど、不思議なほど痕跡ひとつ観測できないケースも意外によく存在してしまう。あーまた逸れそうだった、いや本当にこれは油断できない余白だからこそ怖い、と感じるばかりだ。
実際、その多くは上空何十キロの成層圏辺りで儚く燃え尽きる運命みたい。でも、ごくわずか──ほんとうにごく一部だけど──奇跡的に地表まで届くらしい。チェリャビンスクでは2013年、広島型原爆30発ぶんという呆れるほど巨大なエネルギーを放つ隕石が爆ぜてしまい、1,200人以上が怪我する事態にまで至った。息詰まる衝撃だったな……技術発展云々より「無力さ」を噛み締めさせられた瞬間。しかし過去にも例があって、記録によれば1908年にもシベリア・ツングースカで桁違いな出来事(2,000kmにも及ぶ森林が薙ぎ倒される災禍)が生じている。
もし仮に、それら彗星や隕石群──うん、名前はいろいろあるけど、ともかくヤバイ物体たち──が近代都市部へ直撃していたら、人類史を書き換えていただろうし、その惨事は到底語りきれなかったんじゃないかなぁ。怖い話。でも一方で対策?万全とは到底言えそうもない現実だ。NASAでは「潜在的危険天体」とされるものだけでも50万個規模だと見積もっているみたいで。でも皮肉なことに、そのほとんど……約498,000個については現在位置すら追跡不可のままだとも公表されてる。それなのに2021年には、小惑星が地球軌道ギリギリまで接近したこと自体、「通過後」ようやく察知したという滑稽さすら覚える出来事まで起きた。それゆえというべきか、「想定外」への備えとして監視・緩和・リスクマネジメント、この三本柱そのものをもっと創造的かつ柔軟性を持って強化していかなきゃダメなのでは、と改めて痛感する次第。
### **見えざるインパクトと忘却された危機**
惑星表面には大きく口を開いたクレーター跡などが名残を留めてたりするものだけど、不思議なほど痕跡ひとつ観測できないケースも意外によく存在してしまう。あーまた逸れそうだった、いや本当にこれは油断できない余白だからこそ怖い、と感じるばかりだ。
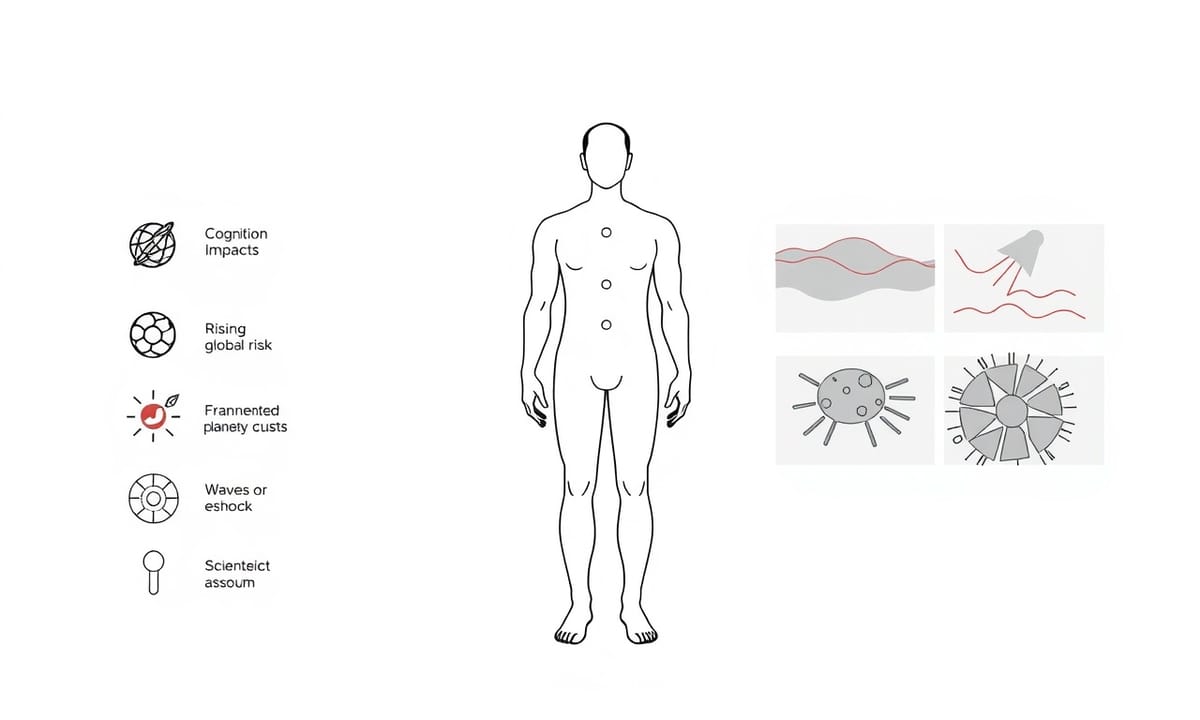
毎年地球に降る隕石と目に見えない危険性を比較してみよう
小惑星とか彗星とか、その物理的性質を改めて色々と考えてみると、何というか……想像以上に多くが大気圏に突っ込む時にバラバラになるみたい。あー、そういうのってちゃんと調べたらわかるんだけどさ。でさ、これだと記録に残ってる衝突回数なんて、実際より全然少なく見積もられていることになるんだろうね。ちょっと信じ難いけど。本当、NASAは「グローバルな大災害」という定義を持っていて、それは世界人口の25%が死ぬような天体衝突、と決めているんだとか。正直言うと怖すぎない?こうしたレベルの出来事は、およそ1/100,000年ごとの確率でしか発生しないという推定らしい。でも、人類ってもう30万年以上も地球上で暮らしてきた存在なんだから——こういう惨事を実際に何度か経験してきた可能性は捨て切れない、と考えざるを得なくなる。「ま、いいか。」例えば1908年のツングースカ事件だけど、小さいと思われがちな小惑星や彗星でも、本当に洒落にならない被害が起こり得る。それも繰り返されている。数千年単位くらいで複数回は発生していたみたい。ただ、その手の出来事、大部分は記録にもならず結局伝承とか神話として曖昧に残されただけなのかな、と想像できたり。
### **科学的記憶として語り継がれるもの**
こういうところから、「ジオミソロジー(geomythology)」って領域への興味につながるわけで。この学問分野では昔から続く神話や伝説が――不思議と――歴史的あるいは地質・天文現象などリアルな事件そのものを何層にも包み込みつつ保持しているかもしれない、と解釈する視点もあるんだよね。いや、不安になったり面倒だったりする瞬間もあるけど、その口承ストーリーにはサバイバルの知恵だったり重要な記憶だったり、有用なエッセンスが意外にも含まれてたりすることが実際ある。一例挙げれば2004年ボクシングデー津波なんだけど、アンダマン諸島周辺の先住民達って近代的な警報機器も持っていなかったけど助かった人たち、多かったらしい。その理由?それぞれの伝承に「海が急激に引いたら、すぐ後ろから巨大な波(つまり津波)が来る」って語り継がれていたから。それを守ったおかげで命拾いしたんじゃないかな。
### **科学的記憶として語り継がれるもの**
こういうところから、「ジオミソロジー(geomythology)」って領域への興味につながるわけで。この学問分野では昔から続く神話や伝説が――不思議と――歴史的あるいは地質・天文現象などリアルな事件そのものを何層にも包み込みつつ保持しているかもしれない、と解釈する視点もあるんだよね。いや、不安になったり面倒だったりする瞬間もあるけど、その口承ストーリーにはサバイバルの知恵だったり重要な記憶だったり、有用なエッセンスが意外にも含まれてたりすることが実際ある。一例挙げれば2004年ボクシングデー津波なんだけど、アンダマン諸島周辺の先住民達って近代的な警報機器も持っていなかったけど助かった人たち、多かったらしい。その理由?それぞれの伝承に「海が急激に引いたら、すぐ後ろから巨大な波(つまり津波)が来る」って語り継がれていたから。それを守ったおかげで命拾いしたんじゃないかな。
巨大隕石衝突が引き起こすグローバル危機の頻度を考えてみよう
民間伝承、あれ、つまりフォークロアってやつか――実際に、それがきっかけで誰かの命が救われた事例も存在するらしい。嘘みたいな話だけど、本当だったりする。この手の伝説が本当に津波から人を助けることになった経緯には、一体どれほど偶発的な要素が絡んでいるのだろう、とか思ってしまう。いや、自分でもちょっと疑わしい気もしてくる。他の神話とかは一体どうなんだろう?…それこそ遠い昔に起きた異常な災害――地球規模とまでは言えないかもしれないけど、何か忘れ去られてしまった天変地異みたいなもの――そういう記憶を反映したものなのだろうか。ただのおとぎ話じゃなくてね。もうこの問題は、テレビのトンデモ系ドキュメンタリー番組だけが追いかける題材に留まっていないらしい。というか、多くの科学者たちも最近になって、「古代伝承には過去に起きたインパクトイベント(衝突事象)について重大なヒントが潜んでいる可能性」があると指摘し始めているみたいだ。
### ヤンガードリアス・インパクト仮説
なんとも議論を呼びやすい説としてよく取り上げられるのが「ヤンガードリアス・インパクト仮説」なのだけれど、これは約12,800年前、ごく巨大な彗星が破片となって地球へ衝突したせいで全地球レベルの気候激変、大規模な森林火災、更には多種多様な生物たち(もちろん人間もいた)が一挙に絶滅へ追いやられた……そんな流れを主張するものだ。その結果として、「ヤンガードリアス」と呼ばれる氷期末期特有の急激冷却、および環境崩壊現象など数々の記録された大規模出来事とも合致する。
まあ、この時代を巡る外的要因について腑に落ちない点はいくつかあると言われていてさ。一つ目としては、それまで1,400年間ひそやかな温暖化基調だったにも関わらず、世界中で平均気温が唐突に10°C以上も下落した事実。それこそ、人類史のみならず直近200万年でも最凶レベルの寒冷化と言えると思う…。二点目は北米地域についてなんだけど、そこではマンモスやマストドン、それにサーベルタイガーなど――そう、多様だったメガファウナ、大型動物群のほぼ全部ごっそり姿を消すという前代未聞クラスの絶滅事件が引き起こされてしまったんだ【注意事項】。ま、いいか…。
### ヤンガードリアス・インパクト仮説
なんとも議論を呼びやすい説としてよく取り上げられるのが「ヤンガードリアス・インパクト仮説」なのだけれど、これは約12,800年前、ごく巨大な彗星が破片となって地球へ衝突したせいで全地球レベルの気候激変、大規模な森林火災、更には多種多様な生物たち(もちろん人間もいた)が一挙に絶滅へ追いやられた……そんな流れを主張するものだ。その結果として、「ヤンガードリアス」と呼ばれる氷期末期特有の急激冷却、および環境崩壊現象など数々の記録された大規模出来事とも合致する。
まあ、この時代を巡る外的要因について腑に落ちない点はいくつかあると言われていてさ。一つ目としては、それまで1,400年間ひそやかな温暖化基調だったにも関わらず、世界中で平均気温が唐突に10°C以上も下落した事実。それこそ、人類史のみならず直近200万年でも最凶レベルの寒冷化と言えると思う…。二点目は北米地域についてなんだけど、そこではマンモスやマストドン、それにサーベルタイガーなど――そう、多様だったメガファウナ、大型動物群のほぼ全部ごっそり姿を消すという前代未聞クラスの絶滅事件が引き起こされてしまったんだ【注意事項】。ま、いいか…。
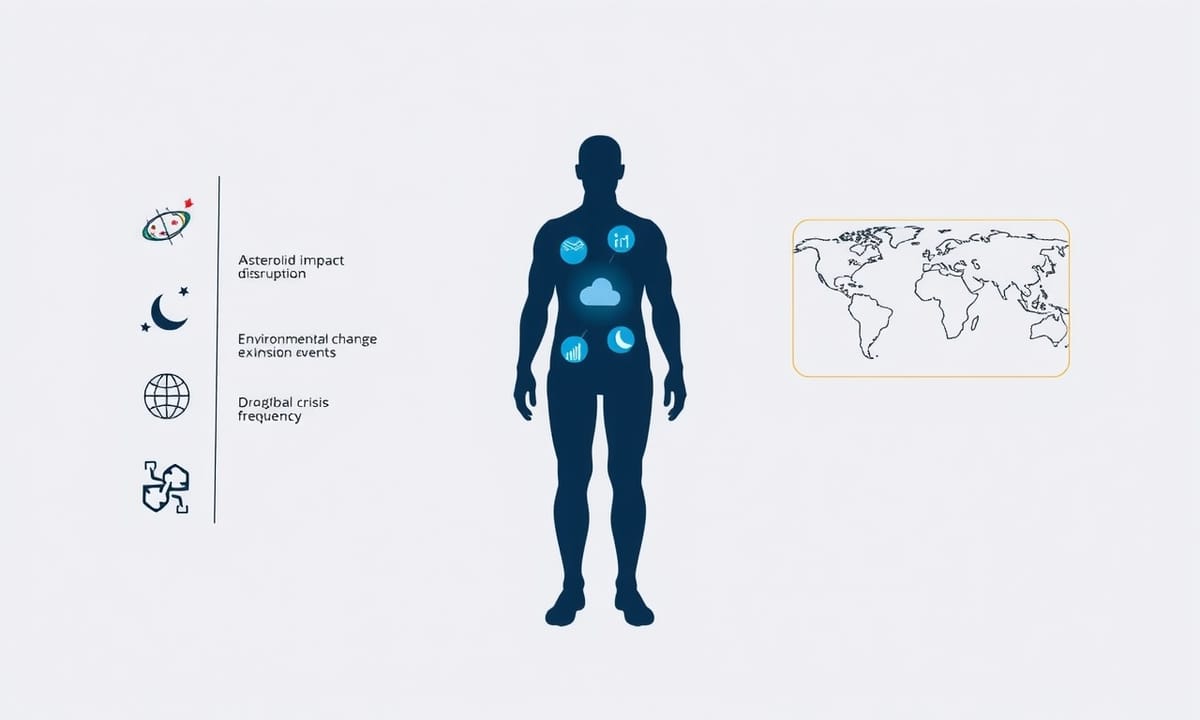
民族伝承や神話がどんな科学的記憶につながっているか探ってみよう
第三に、最大で人口の六割が失われるという、まるで地獄みたいな急激な減少が起きて、農耕もどこか途絶えたりしたし──いや、本当に?──村なんかも見捨てられた、と言われている。こういう悲惨な出来事すべて、本当に宇宙との衝突によるものだったのかって疑いたくなる気持ち、まあ分かる。でもこの説を打ち出している研究グループは「そうです」と答えていてさ、例えば堆積層や微細球体、それから土壌中の豊富な白金といった隕石由来とされる証拠も挙げているって話。
### 火が天から降るという神話
ああ、それから妙に惹きつけられるのは、この壊滅的時代と古くさい世界神話の記述が、不可解なくらい重なる部分なんだよね。プラトンって人が紀元前360年頃に語ったアトランティス伝承――いわばかつて華やかだった文明社会が洪水とか地震で崩壊する昔話だけど、その消滅した時期にも数字が示されていて、ソロンを基準に約9,000年前……つまり今からおよそ12,000年前くらいなんだ、と(そんな昔!)。偶然なのかなあ。ギリシア神話だって太陽神ヘリオスの息子パエトーンが父親の戦車を奪って暴走し、大地を丸ごと焼き尽くすエピソードあるじゃない。「空より火落つ」「大地炎熱す」みたいな表現、それ自体ひょっとすると巨大衝突を目撃した古代人の感想めいて感じ取れてしまうんだよ。【注意事項】
### 火が天から降るという神話
ああ、それから妙に惹きつけられるのは、この壊滅的時代と古くさい世界神話の記述が、不可解なくらい重なる部分なんだよね。プラトンって人が紀元前360年頃に語ったアトランティス伝承――いわばかつて華やかだった文明社会が洪水とか地震で崩壊する昔話だけど、その消滅した時期にも数字が示されていて、ソロンを基準に約9,000年前……つまり今からおよそ12,000年前くらいなんだ、と(そんな昔!)。偶然なのかなあ。ギリシア神話だって太陽神ヘリオスの息子パエトーンが父親の戦車を奪って暴走し、大地を丸ごと焼き尽くすエピソードあるじゃない。「空より火落つ」「大地炎熱す」みたいな表現、それ自体ひょっとすると巨大衝突を目撃した古代人の感想めいて感じ取れてしまうんだよ。【注意事項】
津波から生還した伝説で現代の防災知識と過去の教訓を照らそう
ある学者たちは、この神話が彗星や隕石の衝撃的な出来事についての記憶を、暗号化された物語として語り継いでいるのではないかと考えたりする。エジプト人の神官――あのソロンにアトランティス伝説を話した人物さえ――も、似たような大規模災害は歴史上何度も繰り返されてきたと示唆し、「多様な理由により、人類は幾度となく滅亡を経験してきた。そして未来にも、その運命から逃れられぬことになるかもしれない」と断片的に述べている。ふうん……このパエトン墜落神話自体が、大変長い周期で地球を襲う業火現象の寓意だなんて、どこまで本気なんだろう。
さて、ゴベクリ・テペについてぼんやり思い返すと、この遺跡は現代トルコ領内に位置し、あのストーンヘンジよりも古いって聞いたことがある。ただ、建設者たちは元来狩猟採集民で、本格的な建築技術など持ち合わせていなかったとも言われる。うーん、それなのになぜこんなもの作った?2017年にはエディンバラ大学による論文が出ており、その中ではゴベクリ・テペ内部の特定彫刻が星座配置と整合していて、時期は最低でも12800年前にも遡れる可能性を示唆しているらしい。一部研究者は、これら創造主たちがヤンガー・ドリアス期寒冷化に関連すると想定される壊滅的隕石衝突という、一種の苦難や恐怖そのものを心に刻み残したと解釈する向きもある。この仮説が正しいならば……いや正直半信半疑だけど、ゴベクリ・テペは単なる宗教施設なんかじゃなくて、とても痛切で壮大な「後世への警鐘」として石面に記録されたモニュメントだったんだと思えてしまう。ま、いいか。
さて、ゴベクリ・テペについてぼんやり思い返すと、この遺跡は現代トルコ領内に位置し、あのストーンヘンジよりも古いって聞いたことがある。ただ、建設者たちは元来狩猟採集民で、本格的な建築技術など持ち合わせていなかったとも言われる。うーん、それなのになぜこんなもの作った?2017年にはエディンバラ大学による論文が出ており、その中ではゴベクリ・テペ内部の特定彫刻が星座配置と整合していて、時期は最低でも12800年前にも遡れる可能性を示唆しているらしい。一部研究者は、これら創造主たちがヤンガー・ドリアス期寒冷化に関連すると想定される壊滅的隕石衝突という、一種の苦難や恐怖そのものを心に刻み残したと解釈する向きもある。この仮説が正しいならば……いや正直半信半疑だけど、ゴベクリ・テペは単なる宗教施設なんかじゃなくて、とても痛切で壮大な「後世への警鐘」として石面に記録されたモニュメントだったんだと思えてしまう。ま、いいか。
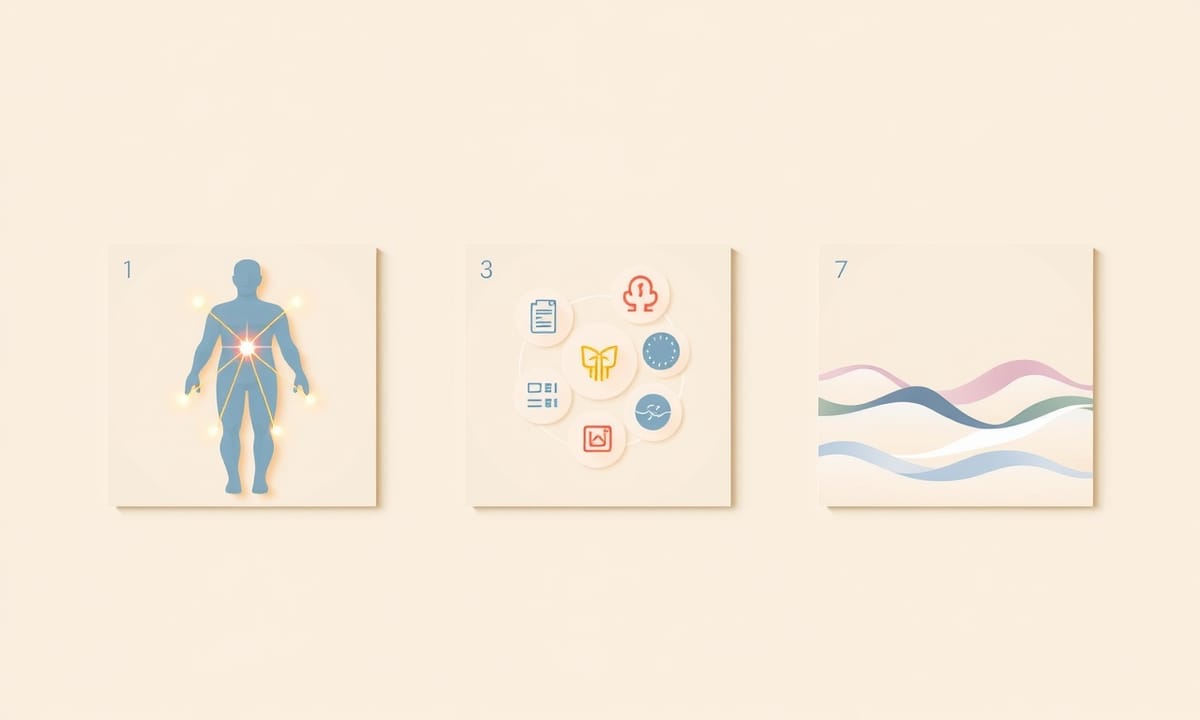
ヤンガードリアス期仮説が地球史へ残した謎とインパクトを追おう
ヤンガードリアス期に関するインパクト仮説、正直いって未だに賛否両論が渦巻いているようで──ああ、そういえば「古代の神話」って言葉を耳にするといつも脳内でカタストロフSFが浮かぶ。ま、それはさておき、神話や考古資料、そして科学が妙な形で交差してくるところにはやっぱり心惹かれる何かがある気もするんだよね。
実際、諸文化に伝わってきた伝承、その中身を紐解いてみると……宇宙由来の衝突災害とでも言うべき記憶をどこか抱えてるんじゃないか?という推察を手放せなくなる瞬間が増えてきてる印象がある。まあ、本当にそんなことあったの?って自問自答するしかない時もあるけど──ふいに思考が逸れてメガリス遺跡について連想してしまった、やばい戻ろう──こういう観点は、人類史の失われた危機体験を解析するうえで案外頼りになる場合もありそう。
それから最低限言えることとして、多分これらの「物語」って私たちにさ、とても根源的なメッセージ──そう、自分たちは万能ですべてを制御できる存在じゃない──この事実を忘れちゃダメよ、と何度も呼び掛け続けていると思う。いやいや地球なんて今まで何回も“落下物”受け止めてきただろうし、おそらく今後も同じ運命を免れはしないでしょうし。「シューティング・ギャラリー」、まさしく今現在でも未来永劫休む暇なんてない構図だったり?
ひょっとしたらだけど、このタイミングだからこそ各地の神話群――遠昔起きた現実として認識したほうが…あるいは直近将来的なリスクへの合図として捉えなおす必要性、薄々感じ始めても無理はないと思った。それら全部、「天」の断片が降り注ぎ世界へ爪痕残した事件であり、そのような事例はこれから先再び繰り返され得る。……ちょっと考え込む時間になっちゃったけど、本質的には人間ってその可能性と日々付き合わざるを得ない生き物なのかなぁ。
実際、諸文化に伝わってきた伝承、その中身を紐解いてみると……宇宙由来の衝突災害とでも言うべき記憶をどこか抱えてるんじゃないか?という推察を手放せなくなる瞬間が増えてきてる印象がある。まあ、本当にそんなことあったの?って自問自答するしかない時もあるけど──ふいに思考が逸れてメガリス遺跡について連想してしまった、やばい戻ろう──こういう観点は、人類史の失われた危機体験を解析するうえで案外頼りになる場合もありそう。
それから最低限言えることとして、多分これらの「物語」って私たちにさ、とても根源的なメッセージ──そう、自分たちは万能ですべてを制御できる存在じゃない──この事実を忘れちゃダメよ、と何度も呼び掛け続けていると思う。いやいや地球なんて今まで何回も“落下物”受け止めてきただろうし、おそらく今後も同じ運命を免れはしないでしょうし。「シューティング・ギャラリー」、まさしく今現在でも未来永劫休む暇なんてない構図だったり?
ひょっとしたらだけど、このタイミングだからこそ各地の神話群――遠昔起きた現実として認識したほうが…あるいは直近将来的なリスクへの合図として捉えなおす必要性、薄々感じ始めても無理はないと思った。それら全部、「天」の断片が降り注ぎ世界へ爪痕残した事件であり、そのような事例はこれから先再び繰り返され得る。……ちょっと考え込む時間になっちゃったけど、本質的には人間ってその可能性と日々付き合わざるを得ない生き物なのかなぁ。
古代神話や洪水伝承に見られる『空から火』現象の共通点を整理しよう
20世紀、地球外生命についての論争はどうも終わる気配がない、みたいだ。そういえば、ResearchGateに掲載された「The Twentieth Century History of the Extraterrestrial Life Debate: Major Themes and Lessons Learned」には、この時代の主な論点や、どこでつまずいたか――そんなことがわかりやすく整理されている(ここ大事だからメモ)。ちょっと脱線するけど、1908年のTunguskaとか最近話題になったChelyabinsk隕石事件(The Planetary Societyのリポートをぼんやり読んだ記憶あり)、こういった天体衝突って案外ずっと現実味ある脅威として扱われ続けてるらしい。へえー、としか言いようがない。[ResearchGate]
ところで、「disaster(災害)」って結局どういうもの? と思うんだけど……Merriam-Webster Dictionaryによれば、それは唐突で規模の大きい損壊・喪失をもたらす現象らしい。「想定できない、けれど一発で多くを失う」――ま、そんな雰囲気。しかもCosmos Magazineによると、一日に17個も隕石が地球へ降り注いでいるとか? いや本当に? 数字だけ見ると結構インパクト強い。[Merriam-Webster Dictionary]
ふと思いついたんだけど……NASA Jet Propulsion LaboratoryではAsteroid Watchなる監視システムが稼働中。そのPlanetary Radar網を駆使して1968年以降1,000個以上もの地球近傍小惑星を捕捉したという。まあ、そう単純に安心はできない感じ。でも思考が逸れてきたかな? ……話戻すと、小さな天体でも、そのインパクトリスクを適切に評価・対処しなくちゃね、とOpen PhilanthropyやNASAの資料「Dealing with the Impact Hazard」がまとめていて。「観測」「評価」「緩和」って、多層的なプロセスなんだよね。[Open Philanthropy]
まあいいか――日々たゆまず監視しつつも、本筋として地球外生命論争が絶え間なく更新され続けている、その皮肉めいた流れ自体もちょっと面白く思えてきた。(Fire serpents [University of North Texas], ResearchGate, NASA JPL, The Planetary Society, Cosmos Magazine, Merriam-Webster Dictionary, Open Philanthropyより)
ところで、「disaster(災害)」って結局どういうもの? と思うんだけど……Merriam-Webster Dictionaryによれば、それは唐突で規模の大きい損壊・喪失をもたらす現象らしい。「想定できない、けれど一発で多くを失う」――ま、そんな雰囲気。しかもCosmos Magazineによると、一日に17個も隕石が地球へ降り注いでいるとか? いや本当に? 数字だけ見ると結構インパクト強い。[Merriam-Webster Dictionary]
ふと思いついたんだけど……NASA Jet Propulsion LaboratoryではAsteroid Watchなる監視システムが稼働中。そのPlanetary Radar網を駆使して1968年以降1,000個以上もの地球近傍小惑星を捕捉したという。まあ、そう単純に安心はできない感じ。でも思考が逸れてきたかな? ……話戻すと、小さな天体でも、そのインパクトリスクを適切に評価・対処しなくちゃね、とOpen PhilanthropyやNASAの資料「Dealing with the Impact Hazard」がまとめていて。「観測」「評価」「緩和」って、多層的なプロセスなんだよね。[Open Philanthropy]
まあいいか――日々たゆまず監視しつつも、本筋として地球外生命論争が絶え間なく更新され続けている、その皮肉めいた流れ自体もちょっと面白く思えてきた。(Fire serpents [University of North Texas], ResearchGate, NASA JPL, The Planetary Society, Cosmos Magazine, Merriam-Webster Dictionary, Open Philanthropyより)
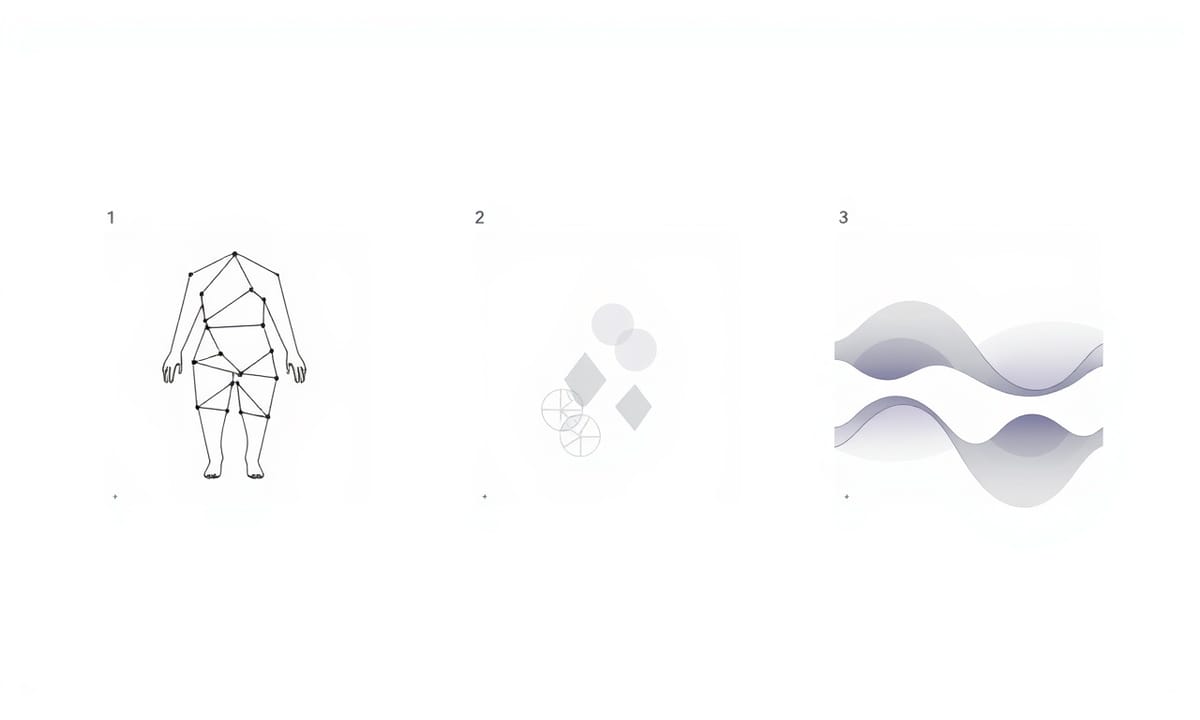
ギョベクリ・テペ遺跡に刻まれた星座と気候変動との関連性を調べてみよう
NASA(2015年)によると、地球近傍の天体が衝突する危険性については段階的に体系化された評価が実施されているようだ(出典:NASA, 2015)。正直なところ、そのリスク…自分にはあまり実感が湧かないけど、専門家たちはきちんと調べているらしい。あと、ジオミソロジー関連の研究では神話や伝承というものが、案外よく自然災害に関連付けられて考察される現象も見受けられるという指摘があった(出典:Brittan, 2024)。まあ…そう言われてもピンとこない人もいるかもしれないね。
さらに2004年インド洋大津波の件について、World Visionによって被災地域の影響や詳細な被害状況が報告されている。その出来事は国境を超え、とりわけ多様な国々で甚大な人命損失と経済的ダメージを引き起こしたことを思い知らされた(World Vision, 2004)。アンダマン諸島辺りに伝わる古代口碑に関しても、NBC Newsで触れられていて、大昔から津波や変な天候について伝え続けられていた様子が紹介されていたっけ。ま、いいか。
「神話」と「科学」というテーマになると不思議な緊張感すら漂うけど、この両者の繋がりや役割みたいなものを科学史の視点から掘り下げた考察文献も存在するようだ(ResearchGate, 2007)。それぞれ独立して成り立ちながら、時に互いへ何かしら作用し合う、不思議な関係なのだろうか?いや…誰にも断定できないことかな。
ヤンガードリアス期衝突仮説の場合は主となる三つの重要研究群が挙げられる。Firstmannたち(2021)は新しい地質証拠を吟味・検討し、その視点で斬新さを加えつつ展開。一方でDaultonたち(2023)は当該年代層から得た物質痕跡分析に特化して議論を進めていた印象。それとは別にFirestoneたち(2007)の先駆的調査結果発表も外せず…彼らのお陰で学界全体がざわついた覚えすら残っている。
アトランティス市なる都市についてNational Geographic誌の記事では、その歴史的背景だったりプラトン以来連綿と語り継がれてきた伝説、それだけじゃなく現代まで提唱されてきた多種多様な見解とか仮説なんかについても、多面的観点から客観的アプローチでもって取り上げていた。気持ちとしては正直夢物語っぽい部分も拭えない。しかしながら…人類はいまだ諦めず憧れたり議論したり、本当に面白い生き物だと思わざるを得ない。
さらに2004年インド洋大津波の件について、World Visionによって被災地域の影響や詳細な被害状況が報告されている。その出来事は国境を超え、とりわけ多様な国々で甚大な人命損失と経済的ダメージを引き起こしたことを思い知らされた(World Vision, 2004)。アンダマン諸島辺りに伝わる古代口碑に関しても、NBC Newsで触れられていて、大昔から津波や変な天候について伝え続けられていた様子が紹介されていたっけ。ま、いいか。
「神話」と「科学」というテーマになると不思議な緊張感すら漂うけど、この両者の繋がりや役割みたいなものを科学史の視点から掘り下げた考察文献も存在するようだ(ResearchGate, 2007)。それぞれ独立して成り立ちながら、時に互いへ何かしら作用し合う、不思議な関係なのだろうか?いや…誰にも断定できないことかな。
ヤンガードリアス期衝突仮説の場合は主となる三つの重要研究群が挙げられる。Firstmannたち(2021)は新しい地質証拠を吟味・検討し、その視点で斬新さを加えつつ展開。一方でDaultonたち(2023)は当該年代層から得た物質痕跡分析に特化して議論を進めていた印象。それとは別にFirestoneたち(2007)の先駆的調査結果発表も外せず…彼らのお陰で学界全体がざわついた覚えすら残っている。
アトランティス市なる都市についてNational Geographic誌の記事では、その歴史的背景だったりプラトン以来連綿と語り継がれてきた伝説、それだけじゃなく現代まで提唱されてきた多種多様な見解とか仮説なんかについても、多面的観点から客観的アプローチでもって取り上げていた。気持ちとしては正直夢物語っぽい部分も拭えない。しかしながら…人類はいまだ諦めず憧れたり議論したり、本当に面白い生き物だと思わざるを得ない。
失われた過去の天変地異から未来への警告として神話を見る視点で考えよう
AtlantisとSolon――うーん、pliphilharland.comの話だけどね、『ティマイオス』でエジプトの司祭がSolonにAtlantisの話を聞かせるんだって、中期前4世紀BCEあたりらしい(https://www.philipharland.com/Blog/2022/07/egyptian-wisdom-plato-on-solon-the-egyptian-priest-and-atlantis-mid-fourth-century-bce/)。それに『ティマイオス』第1部には、司祭自身による語りもあるっぽい(https://www.yorku.ca/pclassic/Plato/Timaeus/timaeus1.htm)。まあこういう技術的な言い伝えが今まで残ったって、不思議としか…。ごめん、ちょっと脱線したね。で、本題へ戻して、ギリシャ神話からPhaethonって人物にも触れたくなる。Heliosの息子でさ、自分で太陽の馬車動かそうとして盛大にしくじる―そんな逸話が結構有名だよ(https://www.greeka.com/greece-myths/phaethon/)。Heliosについても実はかなり詳細な説明がされていてさ、とにかく太陽神としてギリシャ系神話では重要な位置づけなんだよね(https://www.greeklegendsandmyths.com/helios.html#google_vignette)。えっと、それから最近注目集めている考古学ネタといえばGöbekli Tepeかな。この遺跡、UNESCO公式サイトでも紹介されているし(https://whc.unesco.org/en/list/1572/)、なんでもThe University of Edinburghの2024年の研究によれば、この場所から出土した古代彫刻群は世界最古レベルのカレンダーかもしれないんだって言われてる(2024年報告・https://www.ed.ac.uk/news/2024/ancient-carvings-may-be-world-s-oldest-calendar)。あ~情報多すぎて頭パンクしそう、ま、いいか。


















































