宗教の違いを理解しつつ、共通点に気づく視野が広がる
- 週1回、自分と異なる宗教や価値観について3分調べてみる
他者理解のきっかけになり、自分の固定観念も柔軟になる
- 身近な人3人に「生きる意味」や「死後」について聞いてみる
答え方の多様さから共通点や違いが実感でき、視野が広がる
- "唯一神" "聖典" "儀式"などキーワードを5つ挙げて各宗教で比べてみる
"同じものを別名で呼ぶ"発見につながり、偏見が減って面白くなる
- (7日間)意識して毎日1回「祈り・黙想・自然への感謝」を短時間でも体験する
行為自体は多くの宗教に共通し、自分なりの心地よさも見えてくる
宗教って何?時代と文化を越えて残る謎
宗教というものは、なんだろうな、人類文明の中でずっと続いてきた、深い――いや、時に重苦しいくらいの存在感を持っている気がする。ああ、でも「最も」かどうかはちょっと分からないけどさ。人間って、自分の存在とか、その先に何があるのか理解しようとしてきたわけで、それは時代や文化や地理なんて無関係だったりするんだよね。ふと今朝パンを焼きすぎて焦がしたこと思い出したけど…まあ、それはさておき。
世界にはキリスト教もイスラム教も、一神教だけじゃなくてアフリカの伝統的な祖先崇拝みたいなのまで、本当に色々な宗教がある。でもさ、「私たちは違う方法で同じ神を拝んでる可能性もあるんじゃない?」っていう問いが頭をよぎったりしない? ま、この問い自体、全く全部同じだと言いたいわけじゃなくて。違いを消してしまえってことでもなくて。それぞれ別だけど、不思議と通じ合うところ――共通点みたいなものについて考えてみる行為なんだと思う。えっと、自分でも言葉がまとまらないけど…また話それそうになった。
宗教という現象について考えるとき、人間独特の一定パターンとかテーマ、重なる道徳観念とか、「聖なるもの」に向かおうとする一体的な探求心? そんな感じのものが見えてくる気がするんだよね。実際問題、それぞれ信じ方違ってても根っこでは似た部分、多分ある。ま、いいか。
【すべての宗教が試みている核心的な問い】
例えばキリスト教(ナイジェリア)、イスラム教(サウジアラビア)、ユダヤ教(イスラエル)、西アフリカに昔から伝わるヨルバ信仰…などなど場所や宗派関係なしに、多くの精神的伝統には妙に似通った根本課題への思索癖が見受けられる。「私たちはなぜここにいる?」とか「人生には意味や目的、本当にある?」とか、「どう生きればいい?」ともなるし…。ふーむ、一瞬コーヒー淹れ忘れて冷めそうになった。
善悪とは何なのか。「死後には何がおこるんだろう」とか「もっと高次元な存在はいて、その存在と自分との距離感・関係性はいったい何なの」みたいな疑問もついて回る。不思議だけど結局こういう根源的疑問ばっかり追い求めちゃうところ、人間らしいよね、と今更ながら思う。それぞれ答え方は違えど、大事にしてるテーマ自体は案外重複してたりして…。
世界にはキリスト教もイスラム教も、一神教だけじゃなくてアフリカの伝統的な祖先崇拝みたいなのまで、本当に色々な宗教がある。でもさ、「私たちは違う方法で同じ神を拝んでる可能性もあるんじゃない?」っていう問いが頭をよぎったりしない? ま、この問い自体、全く全部同じだと言いたいわけじゃなくて。違いを消してしまえってことでもなくて。それぞれ別だけど、不思議と通じ合うところ――共通点みたいなものについて考えてみる行為なんだと思う。えっと、自分でも言葉がまとまらないけど…また話それそうになった。
宗教という現象について考えるとき、人間独特の一定パターンとかテーマ、重なる道徳観念とか、「聖なるもの」に向かおうとする一体的な探求心? そんな感じのものが見えてくる気がするんだよね。実際問題、それぞれ信じ方違ってても根っこでは似た部分、多分ある。ま、いいか。
【すべての宗教が試みている核心的な問い】
例えばキリスト教(ナイジェリア)、イスラム教(サウジアラビア)、ユダヤ教(イスラエル)、西アフリカに昔から伝わるヨルバ信仰…などなど場所や宗派関係なしに、多くの精神的伝統には妙に似通った根本課題への思索癖が見受けられる。「私たちはなぜここにいる?」とか「人生には意味や目的、本当にある?」とか、「どう生きればいい?」ともなるし…。ふーむ、一瞬コーヒー淹れ忘れて冷めそうになった。
善悪とは何なのか。「死後には何がおこるんだろう」とか「もっと高次元な存在はいて、その存在と自分との距離感・関係性はいったい何なの」みたいな疑問もついて回る。不思議だけど結局こういう根源的疑問ばっかり追い求めちゃうところ、人間らしいよね、と今更ながら思う。それぞれ答え方は違えど、大事にしてるテーマ自体は案外重複してたりして…。
生きる意味や死後の世界…どの宗教も問う核心
これらは、些細な疑問なんかじゃない。むしろ人間という存在の根っこに触れている命題でさ、ぼんやりしてると頭が痛くなるくらいだ。ああ、そういえば…宗教って本当にたくさんあるけど、それぞれ独自の答え方とか実践方法、それから物語まで提供していて、不思議なことに信じる人たちがその中から意味や安らぎ――ときには人生の指針すら見つけようとしているんだよね。
**一神教の信仰:唯一無二の神、その周囲に預言者たち**
キリスト教とかイスラム教、それからユダヤ教、この三つはいわゆるアブラハム系宗教として有名なんだけど、全部を辿っていくと精神的な家系図みたいなのがアブラハムという人物に繋がっていて、その彼こそ唯一絶対なる神への揺るぎない信頼を体現していた、とされている(創世記12章、クルアーン2:124)。まあ…ちょっと脇道。それでも結局またこの話に戻っちゃうんだけどさ。キリスト教の場合はイエス・キリストが「神の子」であり、「人類を救うため愛と犠牲によって遣わされた」と考えられている(ヨハネ3:16)。一方イスラム教ではムハンマドが預言者で、「アッラー」の唯一性を強調しながら服従や公正・慈悲も大切にされている(クルアーン112:1–4)。ユダヤ教はさらに古参で、イスラエル民族との契約関係――トーラーや聖なる律法を守りながら生きる姿勢――そんなところに重きを置いている(申命記6:4)。
とはいえね、それぞれ儀式とか規範には違いだって当然ある。でも肝心なのは深層部分――つまり「信じること」「責任感」「霊的な関係性」みたいなものだと思う。うーん……今さら何を書いてるんだろ、とも感じつつ。
**伝統的および先住民族宗教:日々へ編み込まれる聖なる気配**
いや待った、もちろんアブラハム系以外にも世界には多様な伝統宗教や先住民スピリチュアル思想、更にはヒンドゥーとか仏教・道教など東洋哲理も混ざり合いつつそれぞれ異なる角度から「聖」を捉えてきた歴史があるわけで…。
例えば伝統的アフリカ宗教なら至高存在への畏敬だけじゃなく、多種多様な精霊・祖先霊や自然力なんかも仲介役として極めて重要視されていたりする。礼拝行為自体もしばしば共同体全体で執り行われ、その象徴性だったり土地・祖先との絆だったりバランス感覚みたいなのも特徴かな。あれ?話逸れてない?…まあいいか。また戻す。
ヒンドゥー 教になると、「ブラフマン」と呼ばれる宇宙原理=万物 の根底となる神秘的本質について説かれていて、それは色々な神格(バガヴァッドギーター やウパニシャッド)によって表現され続けてきた。この辺、本当に奥深くて容易くまとめ切れるものじゃないと思う——でも結局、人間はどこまでも意味や繋がりを求めずにはいられない生き物なんだろうね…。
**一神教の信仰:唯一無二の神、その周囲に預言者たち**
キリスト教とかイスラム教、それからユダヤ教、この三つはいわゆるアブラハム系宗教として有名なんだけど、全部を辿っていくと精神的な家系図みたいなのがアブラハムという人物に繋がっていて、その彼こそ唯一絶対なる神への揺るぎない信頼を体現していた、とされている(創世記12章、クルアーン2:124)。まあ…ちょっと脇道。それでも結局またこの話に戻っちゃうんだけどさ。キリスト教の場合はイエス・キリストが「神の子」であり、「人類を救うため愛と犠牲によって遣わされた」と考えられている(ヨハネ3:16)。一方イスラム教ではムハンマドが預言者で、「アッラー」の唯一性を強調しながら服従や公正・慈悲も大切にされている(クルアーン112:1–4)。ユダヤ教はさらに古参で、イスラエル民族との契約関係――トーラーや聖なる律法を守りながら生きる姿勢――そんなところに重きを置いている(申命記6:4)。
この三宗教には共通点も多い。
- 一柱の神のみへの崇敬
- 道徳的生活への価値付与
- 神から授かった聖典や予言を導きと認めていること
- 来世観について一定の展望・ヴィジョンが示されていることとはいえね、それぞれ儀式とか規範には違いだって当然ある。でも肝心なのは深層部分――つまり「信じること」「責任感」「霊的な関係性」みたいなものだと思う。うーん……今さら何を書いてるんだろ、とも感じつつ。
**伝統的および先住民族宗教:日々へ編み込まれる聖なる気配**
いや待った、もちろんアブラハム系以外にも世界には多様な伝統宗教や先住民スピリチュアル思想、更にはヒンドゥーとか仏教・道教など東洋哲理も混ざり合いつつそれぞれ異なる角度から「聖」を捉えてきた歴史があるわけで…。
例えば伝統的アフリカ宗教なら至高存在への畏敬だけじゃなく、多種多様な精霊・祖先霊や自然力なんかも仲介役として極めて重要視されていたりする。礼拝行為自体もしばしば共同体全体で執り行われ、その象徴性だったり土地・祖先との絆だったりバランス感覚みたいなのも特徴かな。あれ?話逸れてない?…まあいいか。また戻す。
ヒンドゥー 教になると、「ブラフマン」と呼ばれる宇宙原理=万物 の根底となる神秘的本質について説かれていて、それは色々な神格(バガヴァッドギーター やウパニシャッド)によって表現され続けてきた。この辺、本当に奥深くて容易くまとめ切れるものじゃないと思う——でも結局、人間はどこまでも意味や繋がりを求めずにはいられない生き物なんだろうね…。

預言者たち、ただ一つの神への道案内?
仏教って、いや、なんか崇拝とかそういうのだけじゃなくてさ、ああ…倫理的な生き方とかマインドフルネス(ダンマパダね)、結局は個人の変容と悟り(涅槃)に行きつくための道が中心にあるわけだよね。うーん、話が逸れるけど昔読んだ本では「自己鍛錬」って言葉ばっか強調してたな…まあそれは置いといて、とにかくそこが大事。で、道教? 道教はまた全然違うようで、「道」との調和を求めてるんだよね。この「道」っていう概念自体がもう宇宙的というか、『道徳経』にも出てくるし、「ザ・ウェイ」なんて呼び方もされてたりするらしい。でも、この辺りでちょっと混乱しちゃう——どこまでが何なのかわからなくなる瞬間あるんだけど、ともかく言語や神話、それぞれ儀式もバラバラっぽい。でも不思議とみんな、自分より大きな何か――神々とか精霊とか普遍的エネルギーとか、それとも自然そのものだったり――そういうものへの畏敬を持っている。なんとなく共通してる感じ。
**私たちは皆、異なる方法で同じ神を崇拝しているのでしょうか?**
えっと、この問い、一見シンプルだけど実はめちゃくちゃ深いんじゃないかな。一度考え始めると止まらないやつ。ぱっと見だとキリスト教の人格神っていう考え方は、たしかに道教の「道」とかイボ族宗教で言われる祖先の精霊とは全然違う気がする。でも……もっと深掘りしてみたらどうかな? 興味深いところ出てくると思う。実際さ、それぞれ独特の歴史や言語、文化を通して同じ精神的現実を解釈しようとしている可能性――ありそうだよね。ま、そのへん曖昧だけど。
例えばさ、人々が太陽について色んな言語で表すとしても、結局指し示す天体自体は同じじゃない? ああごめん、ちょっと例え下手だったかな……でも要するに精神的真理も、多様な形ながら互いにつながった表現になったりすることあると思う。多くの伝統宗教では、人間には理解できない至高者について語られていたりする。その点でアブラハム系宗教における不可知・無限なる神とも重なる部分も見える。
キリスト教やイスラム教、それから伝統宗教にも広がっている道徳規範には共通点が結構ある気がする。それぞれ親切とか公正、おもてなし、それから謙虚さみたいな価値観、大事にされていること多いよね。不意に自分でも「あれ?」と思ったけど……祈りや断食、お供え物や踊りなど色々な儀式、それら全部ひっくるめても、多分、人間と神聖なものとの距離感を少しでも縮めたいという思いから来ているのかな、と今さらながら感じたりした。ま、いいか。
**私たちは皆、異なる方法で同じ神を崇拝しているのでしょうか?**
えっと、この問い、一見シンプルだけど実はめちゃくちゃ深いんじゃないかな。一度考え始めると止まらないやつ。ぱっと見だとキリスト教の人格神っていう考え方は、たしかに道教の「道」とかイボ族宗教で言われる祖先の精霊とは全然違う気がする。でも……もっと深掘りしてみたらどうかな? 興味深いところ出てくると思う。実際さ、それぞれ独特の歴史や言語、文化を通して同じ精神的現実を解釈しようとしている可能性――ありそうだよね。ま、そのへん曖昧だけど。
例えばさ、人々が太陽について色んな言語で表すとしても、結局指し示す天体自体は同じじゃない? ああごめん、ちょっと例え下手だったかな……でも要するに精神的真理も、多様な形ながら互いにつながった表現になったりすることあると思う。多くの伝統宗教では、人間には理解できない至高者について語られていたりする。その点でアブラハム系宗教における不可知・無限なる神とも重なる部分も見える。
キリスト教やイスラム教、それから伝統宗教にも広がっている道徳規範には共通点が結構ある気がする。それぞれ親切とか公正、おもてなし、それから謙虚さみたいな価値観、大事にされていること多いよね。不意に自分でも「あれ?」と思ったけど……祈りや断食、お供え物や踊りなど色々な儀式、それら全部ひっくるめても、多分、人間と神聖なものとの距離感を少しでも縮めたいという思いから来ているのかな、と今さらながら感じたりした。ま、いいか。
アフリカ伝統信仰と自然の神秘が織りなす日常
【永遠の哲学:一つの真理、多様な道】
「永遠の哲学(ペレニアル・フィロソフィー)」という言葉、なんだか、ちょっと古めかしい感じがするけど…いや、でも実は今でも意外と使われてるらしい。すべての宗教が普遍的な真理――その核みたいなもの――を持っているという考え方、わりと知ってる人は多いんじゃないかな。オルダス・ハクスリーとかフリチョフ・シュオン、名前だけ聞くとピンとこない人もいるかもしれない。ま、私も最初は誰それ状態だった。でも彼ら曰く、「世界には神聖な実在があって、あらゆる宗教はそれぞれ異なる表現で同じ究極的真理を語っている」ということなんだって。うーん、不思議だよね。でも確かに、「人生には意味がある」と本気で思いたい瞬間ってあるし、人類は物質だけじゃない何かにつながりたい衝動から逃れられない…ような気もする。ところで昨日コンビニで変なグミ見つけたんだけど、それはさておき、本筋に戻ろう。
【違いを尊重しながらも、つながりを求める】
だからと言って、「すべての信仰が同じ」みたいに雑にまとめちゃダメなんだよね。不思議なくらい、それぞれの宗教には独特の香りとか佇まい――個性とも言える何か――がちゃんと息づいてるし。それを大切にしたいと思う反面、その一方で共通している目的や問いにも目を向けたくなる時がある。「どちらの宗教が正しいか」よりも、「お互いにどんな道筋や視点から神聖さを汲み取れるのか」、そこから何か学べることはきっとある…いや、多分ね。でも、話逸れてカフェラテ飲みたくなったけど、とりあえずこの話題に戻ります。そういう姿勢こそ、対話や平和への小さな一歩になるんじゃないかなぁ、とぼんやり思ったりする今日このごろ。
【結論:人間による聖なるものへの探求】
結局のところ、人間って意味とか目的とか、それから不思議と「つながり」を追い求めずにはいられない生き物なんだろうね。宗教って、その心情――渇望? 焦燥? まあ両方かもしれない――が映し出されている鏡なのかな、と感じることがある。司祭による説教だったり、スーフィーによる踊りだったり(あんなふうに回れる体力ほんとうらやましい)、ヨルバ族占い師による唱歌でも仏教徒による瞑想でも、人々はいろんな形で自分たちより大きな“何か”へ手を伸ばしてきた。それこそ窓辺でぼーっと空を見るみたいにさ。それぞれ別々の窓なのに、本当は同じ「神聖なる光」を見上げているだけなのかなぁ……うーん、どうなんだろうね。でも、それでいい気もする。
「永遠の哲学(ペレニアル・フィロソフィー)」という言葉、なんだか、ちょっと古めかしい感じがするけど…いや、でも実は今でも意外と使われてるらしい。すべての宗教が普遍的な真理――その核みたいなもの――を持っているという考え方、わりと知ってる人は多いんじゃないかな。オルダス・ハクスリーとかフリチョフ・シュオン、名前だけ聞くとピンとこない人もいるかもしれない。ま、私も最初は誰それ状態だった。でも彼ら曰く、「世界には神聖な実在があって、あらゆる宗教はそれぞれ異なる表現で同じ究極的真理を語っている」ということなんだって。うーん、不思議だよね。でも確かに、「人生には意味がある」と本気で思いたい瞬間ってあるし、人類は物質だけじゃない何かにつながりたい衝動から逃れられない…ような気もする。ところで昨日コンビニで変なグミ見つけたんだけど、それはさておき、本筋に戻ろう。
【違いを尊重しながらも、つながりを求める】
だからと言って、「すべての信仰が同じ」みたいに雑にまとめちゃダメなんだよね。不思議なくらい、それぞれの宗教には独特の香りとか佇まい――個性とも言える何か――がちゃんと息づいてるし。それを大切にしたいと思う反面、その一方で共通している目的や問いにも目を向けたくなる時がある。「どちらの宗教が正しいか」よりも、「お互いにどんな道筋や視点から神聖さを汲み取れるのか」、そこから何か学べることはきっとある…いや、多分ね。でも、話逸れてカフェラテ飲みたくなったけど、とりあえずこの話題に戻ります。そういう姿勢こそ、対話や平和への小さな一歩になるんじゃないかなぁ、とぼんやり思ったりする今日このごろ。
【結論:人間による聖なるものへの探求】
結局のところ、人間って意味とか目的とか、それから不思議と「つながり」を追い求めずにはいられない生き物なんだろうね。宗教って、その心情――渇望? 焦燥? まあ両方かもしれない――が映し出されている鏡なのかな、と感じることがある。司祭による説教だったり、スーフィーによる踊りだったり(あんなふうに回れる体力ほんとうらやましい)、ヨルバ族占い師による唱歌でも仏教徒による瞑想でも、人々はいろんな形で自分たちより大きな“何か”へ手を伸ばしてきた。それこそ窓辺でぼーっと空を見るみたいにさ。それぞれ別々の窓なのに、本当は同じ「神聖なる光」を見上げているだけなのかなぁ……うーん、どうなんだろうね。でも、それでいい気もする。
ヒンドゥーや仏教、タオ―多彩な神観と宇宙観
このトピック、正直言って、あんまり簡単には語れないな…うーん、自分の考えか。まあ、ひとまずコメントしてみる?いや、その前にちょっと脇道だけど、実は「信仰」って言葉を聞くだけで少し身構えてしまうことがあるんだよね。昔の記憶がふっと蘇ったりするから。不思議だ。でも、本筋に戻すと、自分の信仰が人生の混沌の中で意味を見出す手助けになっているか——これはたぶん、人によって全然違う答えになる気がする。
僕自身は…ま、いいか。この部分は置いておこう。ただ、誰かが自分なりの信仰や世界観を共有してくれたら、それだけできっと救われる瞬間もあると思う。そもそも「美しさ」なんて曖昧模糊としてるし。ちなみに参考文献に _Armstrong, K. (1993). A history of God: The 4,000-year quest of Judaism, Christianity and Islam. Ballantine Books._ が挙げられているけど、この本も全部読破したわけじゃない。でも時々ページをめくると、不意に心が落ち着いたりする瞬間があったりして。不思議だよね。
で、話を戻すと…あなた自身の信仰や、その過程で感じたことをぜひコメントとして残してほしいな、と僕は思うわけです。ここまで書いてて何かまとまらなくなってきちゃったけど、一緒にこの「信仰」というものの美しさ——ちょっと気恥ずかしい表現だけど——について探求できれば、それはそれで意味があるかなぁ、と夜更けにぼんやり考えてたりします。
僕自身は…ま、いいか。この部分は置いておこう。ただ、誰かが自分なりの信仰や世界観を共有してくれたら、それだけできっと救われる瞬間もあると思う。そもそも「美しさ」なんて曖昧模糊としてるし。ちなみに参考文献に _Armstrong, K. (1993). A history of God: The 4,000-year quest of Judaism, Christianity and Islam. Ballantine Books._ が挙げられているけど、この本も全部読破したわけじゃない。でも時々ページをめくると、不意に心が落ち着いたりする瞬間があったりして。不思議だよね。
で、話を戻すと…あなた自身の信仰や、その過程で感じたことをぜひコメントとして残してほしいな、と僕は思うわけです。ここまで書いてて何かまとまらなくなってきちゃったけど、一緒にこの「信仰」というものの美しさ——ちょっと気恥ずかしい表現だけど——について探求できれば、それはそれで意味があるかなぁ、と夜更けにぼんやり考えてたりします。
同じ太陽を違う言葉で呼ぶみたいに…神は一つ?
(2009). The case for God. Alfred A. Knopf.
_ _Bible. (n. d. ). The Holy Bible. Various versions.
_ _Bowker, J. (Ed.). (1997).ああ、今ちょっと本棚を見てたら昔読んだ本が目に入ってきたけど… でも、戻ろう。で、この文献リストね、なんかただの羅列だけど、実はそれぞれ思い出深いものだったりもする。The case for God(2009年)はAlfred A. Knopfから出版されているし、えっと、それに…Holy Bibleはいろんなバージョンがあるって書いてるけど、ほんとに多すぎて選べないくらいだよね。ま、いいか。Bowker編集(1997年)のやつも何度か手に取った気がするけど、最近は全然触れてないなぁ。ちなみに、自分の部屋にも一冊くらいHoly Bible転がってる気がする。でも今は内容の話じゃなくて文献の話だったっけ…まあそんな感じで、一応全部ここに載せておくよ。
_ _Bible. (n. d. ). The Holy Bible. Various versions.
_ _Bowker, J. (Ed.). (1997).ああ、今ちょっと本棚を見てたら昔読んだ本が目に入ってきたけど… でも、戻ろう。で、この文献リストね、なんかただの羅列だけど、実はそれぞれ思い出深いものだったりもする。The case for God(2009年)はAlfred A. Knopfから出版されているし、えっと、それに…Holy Bibleはいろんなバージョンがあるって書いてるけど、ほんとに多すぎて選べないくらいだよね。ま、いいか。Bowker編集(1997年)のやつも何度か手に取った気がするけど、最近は全然触れてないなぁ。ちなみに、自分の部屋にも一冊くらいHoly Bible転がってる気がする。でも今は内容の話じゃなくて文献の話だったっけ…まあそんな感じで、一応全部ここに載せておくよ。
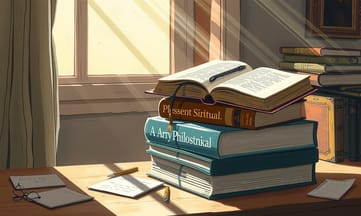
『万教帰一』という不思議な考え方、根っこは同じ?
Oxford世界宗教辞典。Oxford University Press。
えっと、ちょっとだけ話が逸れるけど、最近この本棚に手を伸ばすこと自体が億劫でさ。でもまあ、いいや。本題に戻ろう。Huxley, A. (1945). The perennial philosophy. Harper & Brothers。なんというか、このタイトルを見るたび、永遠ってそもそも何?と考えてしまうのよね、眠い時とか特に。ああ、それはともかくとして次。Mbiti, J. S. (1969). African religions and philosophy. Heinemann。この辺りはアフリカの思想について書いてあるらしいけど、自分にはまだ完全には消化しきれてない部分も多い気がするんだよなぁ…。ま、いいか。そして最後にMitchell, S. (Trans.)。
いや、本当はここで一度コーヒーでも入れたいところだけど、それじゃ全然進まないから続けるしかないよね、と自分に言い聞かせてまたキーボードを叩いてるわけで…。
えっと、ちょっとだけ話が逸れるけど、最近この本棚に手を伸ばすこと自体が億劫でさ。でもまあ、いいや。本題に戻ろう。Huxley, A. (1945). The perennial philosophy. Harper & Brothers。なんというか、このタイトルを見るたび、永遠ってそもそも何?と考えてしまうのよね、眠い時とか特に。ああ、それはともかくとして次。Mbiti, J. S. (1969). African religions and philosophy. Heinemann。この辺りはアフリカの思想について書いてあるらしいけど、自分にはまだ完全には消化しきれてない部分も多い気がするんだよなぁ…。ま、いいか。そして最後にMitchell, S. (Trans.)。
いや、本当はここで一度コーヒーでも入れたいところだけど、それじゃ全然進まないから続けるしかないよね、と自分に言い聞かせてまたキーボードを叩いてるわけで…。
違いを愛しながら似てる部分を探せるかもね
(1988)。Tao Te Ching。HarperPerennial。うーん、なんか「老子」とかって言われると急に難しそうだけど、実際パラパラ読んでみると意外と腑に落ちる部分があったりする。不思議だね。_ _Nasr, S. H.(2002)。The heart of Islam: Enduring values for humanity。HarperOne。えっと、この本はイスラム教の核心的な価値観について語られているらしいけど、読むタイミングを何度も逃してしまった気がするな…まあ、そのうち読めばいいか。_ _Olupona, J. K.(2014)。African religions: A very short introduction。Oxford University Press。それからアフリカの宗教について簡潔にまとめてある本も入ってて、多分これを手に取る人ってそんな多くないよね?でも、自分の視野がちょっと広がる気がして案外侮れないやつだったりする。本当にそうかなぁ?いや、たぶん合ってると思うけど…。_ _Quran。ただ「クルアーン」についてはタイトルだけ書いてある感じで、あっさりしている。でも、その重みというか歴史とか文化とかを思い出すと、一冊以上の存在感だよな、と勝手に思ってしまうわけで。また話逸れたけど、ともあれ全部資料としてちゃんと大事にしたい本ばかりだと思う…。
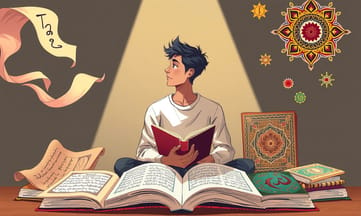
あなたは誰か―祈り・踊り・瞑想が導く先とは
(n. d. )『コーラン』。いろんな翻訳があって、まあ、どれも一長一短というか……うーん、迷うところだな。__ Schuon, F. (2005). 『宗教の超越的一体性』(改訂版)。Quest Books. __ それからSmith, H. (2009). 『世界の宗教』(改訂版)。正直、この本は分厚くて読み切るのに時間がかかったけど、不思議と途中でやめられなくてね。あ、そういえば最初に戻るけど、『コーラン』自体も内容が深くて、読むたびに新しい発見がある気がする。ま、いいか。
最後に…混沌に光を見出す旅、それぞれの窓から
[ed. ). HarperOne. _ _Smart, N. (1998). The world's religions: Old traditions and modern transformations. Cambridge University Press. _ _Zaehner, R. C. (1962). Hinduism. Oxford University Press. _]、って……あれ、ちょっと待って。いやいや、まだリストは終わってなかったんだよね。うーん、この文献リストを見ると頭が少しぼーっとするというか、それでもやっぱり重要なんだよな、参考文献ってさ。で、とにかくこの3つ――HarperOneとかCambridge University PressとかOxford University Pressのやつ――これら全部を参照してるみたい、たぶん。まあいいか。だけどさ、この辺り読むだけでも結構時間食うし、まったく、本当に疲れる。でも、不思議とこういう細かいところに目を向けないと全体像が見えてこない気もするし…。さて、話戻すけど、とにかく引用したい場合はこの3冊(えっと、そのまま書いてある通り)覚えとけば大丈夫っぽいよ、多分ね。


