ネットで面白い記事を読んでると、急に出てくる「メンバー限定ストーリー」の壁。Medium(ミディアム)でよく見かけるアレね。月にもらえる無料記事の本数を使い切っちゃって、「うわ、ここで終わりかよ!」ってなるやつ。正直、ちょっとイラッとするよね。😅
でもね、最近考えてたんだけど、あのペイウォール(課金制の壁)って、一体何なんだろう?単に読者をじらしてるだけ?それとも、もっと深い理由があるのかなって。僕も書き手の一人として、この仕組みはすごく気になってて。今日はその辺の「ぶっちゃけどうなの?」って話を、ちょっと整理してみようかなと思う。
先說結論:Mediumのペイウォールは「諸刃の剣」
いきなり結論から言うと、Mediumの仕組みは、質の高い記事を守り育てるための「必要悪」みたいな側面と、書き手にも読者にもフラストレーションを与える「厄介な壁」っていう、二つの顔を持ってる。これ、マジで諸刃の剣。広告だらけのウェブから僕らを開放してくれるかもしれないけど、その代わりに新しい種類の不自由さも生んでるんだよね。
そもそも、なんでこんな仕組みが生まれたの?
これを知るには、ちょっとだけ昔話をしなきゃいけない。Mediumが2012年に始まったとき、実は全部無料だったんだ。Twitterの共同創業者が始めたサービスで、「質の高い文章が、広告のノイズなしに読める場所」を目指してた。すごく理想的だよね。
でも、サイトを運営するのにも、良い書き手にお金を払うのにも、当然コストがかかる。最初は無料で頑張ってたけど、プラットフォームが大きくなるにつれて、それじゃ立ち行かなくなった。そこで出てきたのが、広告に頼らないでお金を生み出す方法…つまり、読者から直接お金をもらう「サブスクリプションモデル」だったわけ。
インターネットって、もう何年も「広告モデル」が当たり前だったじゃない?PV(ページビュー)を稼ぐために、扇情的なタイトルつけたり、中身のないクリックベイト記事が溢れたり。Mediumは、その流れを断ち切りたかった。「クリック数」じゃなくて「良い文章」が正当に評価される世界を作りたかったんだ。…うん、理念はすごく美しいと思う。

で、具体的にどういう仕組みなの?
すごくシンプルに言うと、こんな感じ。
- 読者側: 月額5ドル(日本ではだいたい500円くらいかな?)か、年額50ドルを払うと「メンバー」になれる。そうすると、メンバー限定記事が全部読み放題になる。あと、うっとうしい広告も表示されない。自分の払ったお金の一部が、読んだ記事の書き手に直接分配されるから、「応援してる」感も得られる。
- 書き手側: 「Mediumパートナープログラム」っていうのに参加すると、自分の記事をペイウォールの内側(つまり有料)に置ける。メンバーがその記事を読んでくれた時間とか、「Clap」(Medium版の「いいね」)の数に応じて、収益が分配される。つまり、メンバーに深く、長く読まれる記事ほど、儲かる可能性があるってこと。
理論上は、すごく良くできてるよね。書き手は小手先のテクニックじゃなくて、本当に中身のある記事を書くことに集中できる。読者はノイズのない環境で、質の高い情報にアクセスできる。Win-Winに見える。…でもね、現実はそんなに甘くないんだな、これが。
理想と現実のギャップ:メリットとデメリットを正直に話すよ
「じゃあ、みんなMedium使えばいいじゃん!」ってならないのが、この話の面白いところ。実際に使ってみると、読者にとっても書き手にとっても、結構な悩みのタネがある。ちょっと表にまとめてみたけど、僕の個人的な感想もかなり入ってるから、そのつもりで見てね。
| 対象 | メリット(良いところ) | デメリット(うーん…なところ) |
|---|---|---|
| 読者として |
|
|
| 書き手として |
|
|
特に書き手にとって、この収入の不安定さは死活問題だよね。僕の周りでも、「先月は結構良かったんだけどな…」って頭を抱えてる人がいる。一本の記事がバズって大金が入ってくる夢もあるけど、それだけで生活していくのは、正直かなり厳しい。
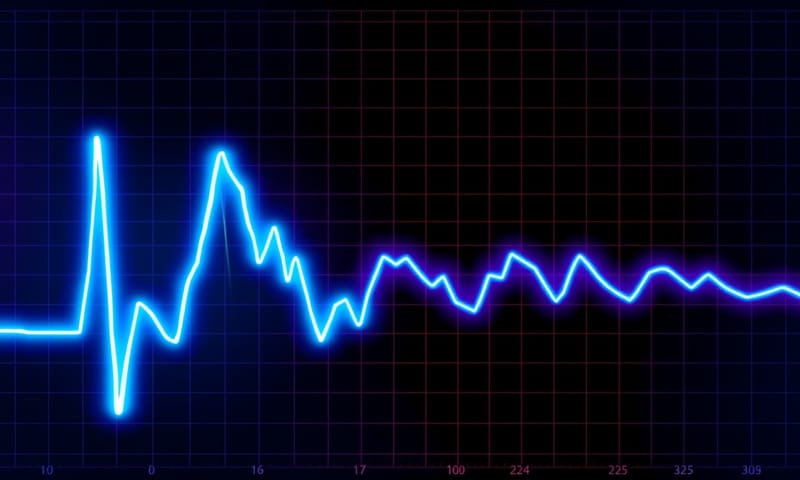
トップライターはどこへ?SubstackとNote.muとの比較
最近の大きな動きとして、海外では有名な書き手がMediumを離れて、Substack(サブスタック)みたいなニュースレタープラットフォームに移るケースが増えてる。なんでかって言うと、Substackはもっと直接的に、自分の読者と繋がれるから。
Mediumだと、プラットフォームのアルゴリズムに「この記事、面白いからオススメしとくね!」って選んでもらわないと、なかなか読んでもらえない。でもSubstackなら、自分のファン(購読者)に直接メールで記事を届けられる。収益も、自分の購読者数×月額料金だから、Mediumよりずっと予測しやすい。
あ、ちなみにこれ、日本の状況で考えると、note(ノート)がすごく近い存在だよね。noteもクリエイターが記事やコンテンツに値段をつけて直接販売できるし、サークル機能でコミュニティも作れる。ただ、Mediumが「世界中の質の高い読み物」っていう、ちょっとジャーナリズム寄りな雰囲気なのに対して、noteはもっと日記とか、個人のクリエイティブな表現の場所って感じが強いかな。文化的な背景が違うのが面白いところ。
結局、書き手は「プラットフォームに依存する不安定さ」を嫌って、「自分のファンと直接つながれる安定した場所」を求め始めてるってことなんだと思う。
じゃあ、Mediumはもうオワコンなの?
「じゃあもうMediumはダメなの?」って思うかもしれないけど、そうとも言い切れない。Medium自身もこの問題には気づいていて、色々テコ入れをしてる。
例えば、「Boost」っていう機能。これはAIじゃなくて、人間のキュレーターが「この記事は素晴らしい!」って思ったものをピックアップして、たくさんの人に届ける仕組み。アルゴリズムの気まぐれに左右されがちな状況を、人の手で修正しようとしてるんだ。こういう試みは、すごく応援したくなる。
結局、Mediumがやろうとしてるのは、これからのオンラインコンテンツのあり方そのものを問う、壮大な社会実験なんだよね。
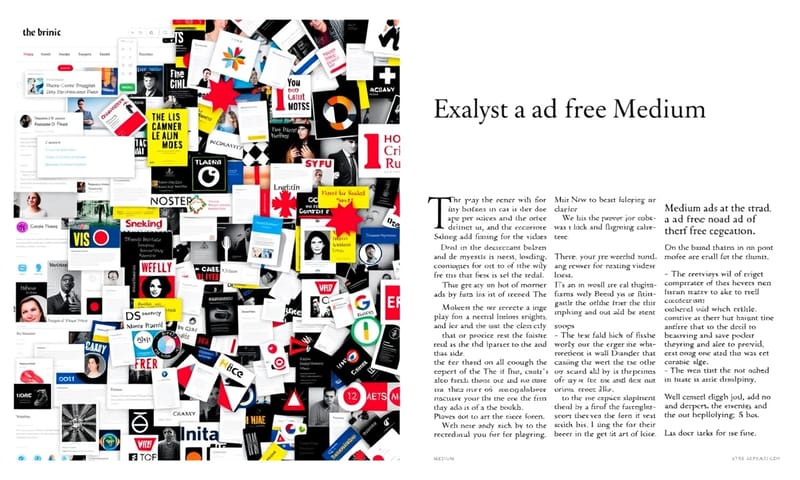
僕らが当たり前だと思ってた「ネットの記事は無料で読める」っていう時代は、実は広告主のお金で成り立ってた、不安定なものだったのかもしれない。これからは、読者が「この情報にはお金を払う価値がある」と判断して、直接クリエイターを支えるモデルが、もっと主流になっていくのかも。
そうなると、僕ら書き手は、ただ良い文章を書くだけじゃなくて、どうやって読者と関係を築くか、どうやって自分の価値を伝えていくかっていう、もっと戦略的な視点が必要になる。読者側も、「どの情報にお金を払うか」っていう、賢い選択が求められるようになるんだろうね。
結局のところ、僕らはどう向き合えばいい?
Mediumのペイウォールは、完璧な解決策じゃない。でも、ただの邪魔者でもない。広告漬けのネット環境から僕らを救ってくれる可能性を秘めつつ、同時に、情報のアクセシビリティとか、書き手の生活の安定性っていう新しい課題も突きつけてくる。
もしあなたが「質の高い、じっくり読める記事が好きだ」っていう読者なら、月500円の投資は、好きな作家やメディアを直接応援する、すごく意味のある行為になると思う。
もしあなたが書き手なら、このプラットフォームのクセをちゃんと理解した上で、「自分の書きたいこと」と「読者が求めていること」、そして「プラットフォームが評価してくれること」のバランスをどう取るか、考え続ける必要がある。…まあ、言うのは簡単だけど、これが一番難しいんだけどね。
インターネットの世界で、「質」と「公平さ」と「ビジネス」をどうやって両立させるか。Mediumの挑戦は、まだその答えを探している途中なんだと思うよ。
…と、ここまで色々話してきたけど、あなたはどう思う?
ぶっちゃけ、質の高い記事のためなら月500円くらいって、高いと思う?安いと思う?もしよかったら、コメントであなたの感覚を教えてほしいな!



