冒頭のアクションヒント - 差別構造の可視化と沈黙打破で社会変革を後押し
- 身近な会話やSNS投稿で週1回、偏見や差別に関する自分の体験や考えをシェアする
可視化が進み沈黙が減ることで社会的分断解消への一歩に
- 職場・学校・家庭など3つ以上の場面で差別的発言を耳にしたら、すぐ「それはどうして?」と問い返してみる
無意識な偏見構造を揺さぶり対話のきっかけが生まれる
- 年2回以上、公的なアンケートや行政サイトから人権課題について意見投稿または署名参加
"声"の蓄積が制度改革や啓発活動につながりやすい
- "中立"という言葉で議論回避しそうになった時、自分自身へ「このテーマだけは明確に立場表明」と決めて実行
人権尊重姿勢が周囲にも伝わり当事者意識アップにつながる
「被害者ぶっている」と言われるけど、本当にそうなのか?
最近、どこかでMediumの記事を見かけた気がする。そこではトランスジェンダーのコミュニティについて、「被害者意識にとらわれてる」といった声があったような……たしか、その中で「やけに声高で感情的」だとか、そういう表現も使われていた気がする。でも、こうした言葉遣いって、実際のところ当事者が日々直面している社会的な壁や構造の話をちゃんと語れなくさせてしまうんじゃないかな、と考えてしまう瞬間もある。もちろん、人によっては伝え方が少し強めだったり、雰囲気に個性を出す方もいるけれど、それだけで全体を判断するのはちょっと違うと思う。
それから、「被害者ぶっている」とか「誰かのせいにしてる」「自分で自分をかわいそうに思ってるだけ」という風な言葉――こういうフレーズは昔から何度となく使われてきたように思う。ただ、それが使われることで、本当に必要な指摘や批判まで押し込められてしまうこともあるみたいだ。実際には、不公平や差別を訴えること自体が「ただの被害者アピール」になるわけじゃないし、多くの場合それは、自分たちが感じている現実への正直な抵抗だったり、事実を伝える行為だったりするという印象もある。
まあ、人によって受け取り方はいろいろだろうし、「声を上げる=被害者意識」という単純な図式にならないことも多いんじゃないかな。世間では時々、この二つをごっちゃにして語られる場面を見るけど……ちゃんと切り分けて考えたほうがいい気もする。
それから、「被害者ぶっている」とか「誰かのせいにしてる」「自分で自分をかわいそうに思ってるだけ」という風な言葉――こういうフレーズは昔から何度となく使われてきたように思う。ただ、それが使われることで、本当に必要な指摘や批判まで押し込められてしまうこともあるみたいだ。実際には、不公平や差別を訴えること自体が「ただの被害者アピール」になるわけじゃないし、多くの場合それは、自分たちが感じている現実への正直な抵抗だったり、事実を伝える行為だったりするという印象もある。
まあ、人によって受け取り方はいろいろだろうし、「声を上げる=被害者意識」という単純な図式にならないことも多いんじゃないかな。世間では時々、この二つをごっちゃにして語られる場面を見るけど……ちゃんと切り分けて考えたほうがいい気もする。
「被害者意識」という言葉が持つ危険な力
こういう言葉、何て言うか、議論するためじゃなくて相手を黙らせる道具みたいな感じがしてしまう。たぶん「被害者意識」って、よく聞くけど、それを自分から選ぶ人はあまりいないんじゃないかと思う。実際には、大きな社会の仕組みの中で、不利益や傷つきを受けること、その状況に置かれること自体が「被害」だという話もあるらしい。誰かが声を上げようとした時、「また被害者ぶってる」とか言われたりすること、何度も見た気がする。でも、それって結局、責任を本人に押し付けるような流れになりやすいよね。
例えば、女性が職場で嫌な思いをした時に、「もっと地味な服装なら良かったのに」なんて指摘される場面とかもそう。問題は見えなくなるほど大きくなるわけでもないし、静かだからといって無かったことにもならない。それなのに、大きな声で不満や痛みを訴えた瞬間だけ批判される……ちょっと矛盾している気もしなくはない。
逆に考えると、自分や他の誰かのために不正義について話すとか、「傷ついたままで消えたくない」と思う行動そのものは、「被害者アピール」とは違う気がする。「生き延び方」の一つとも言えるかな。その後どう立ち直るか、その辺りこそ重要なのかもしれない。
差別についても少し触れておきたいんだけど、人によっては「自分がマイノリティだから差別されている」って認めること自体に抵抗感を持つケースもあるみたい。でも、多くの場合、それは個人の努力不足とは全然関係なくて。世間では約三割くらいの人しか気づいていないとも聞いたけど、本当のところはどうなのかな……まあ、ともあれ恥じる理由にはならないと思う。
例えば、女性が職場で嫌な思いをした時に、「もっと地味な服装なら良かったのに」なんて指摘される場面とかもそう。問題は見えなくなるほど大きくなるわけでもないし、静かだからといって無かったことにもならない。それなのに、大きな声で不満や痛みを訴えた瞬間だけ批判される……ちょっと矛盾している気もしなくはない。
逆に考えると、自分や他の誰かのために不正義について話すとか、「傷ついたままで消えたくない」と思う行動そのものは、「被害者アピール」とは違う気がする。「生き延び方」の一つとも言えるかな。その後どう立ち直るか、その辺りこそ重要なのかもしれない。
差別についても少し触れておきたいんだけど、人によっては「自分がマイノリティだから差別されている」って認めること自体に抵抗感を持つケースもあるみたい。でも、多くの場合、それは個人の努力不足とは全然関係なくて。世間では約三割くらいの人しか気づいていないとも聞いたけど、本当のところはどうなのかな……まあ、ともあれ恥じる理由にはならないと思う。
Comparison Table:
| テーマ | ポイント | 考察 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 社会的な不平等 | 多数派の安心感が少数派を圧迫することがある | 権利は心地よさに左右されるべきではない | 多様性を尊重し、全ての人間の尊厳を守る必要がある |
| 議論と無知 | 議論には本来恥ずかしさはないはずだが、LGBTに関する意見では偏見が強い | 科学的根拠に基づく議論が重要である | 無知や偏見に対抗するためには情報共有が不可欠である |
| 声を上げる意義 | 体験を語ることは存在証明につながる | 沈黙は不正義を許す可能性が高い | 発言することで現実を直視させ、不公平に立ち向かう勇気を持つべきである |
| 歴史から学ぶ教訓 | 過去の静けさは悲劇につながった事例が多い | 声なき時代への警鐘として機能すべき | 過去の教訓から、積極的な発信と行動が求められる |
| 真実と勇気 | 真実は声によって明らかになる場合も多い | 勇気ある行動によって小さな変化でも生まれる | 個々の声も集まれば大きな力になる可能性がある |
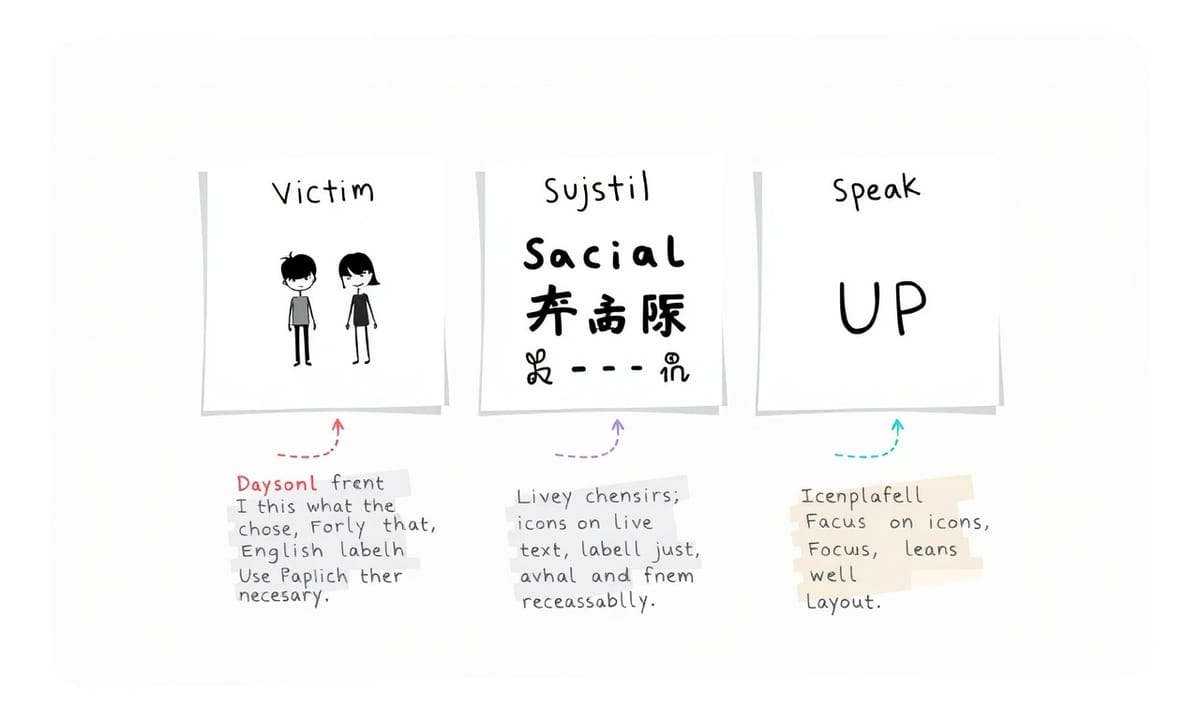
差別は個人の欠陥じゃないって知ってた?
差別って、たぶん狙われた人や集団の問題じゃなくて、それを広めたり、あまり気にしなかったり、なんとなく正当化したりする側の姿勢が現れてしまうものかもしれません。歴史をざっと見れば、同じようなことが繰り返されてきた印象がありますね。例えばアメリカ南部で行われていたジム・クロウ法――「分離すれど平等」みたいな建前だったんですけど、実際にはその「平等」ってどう考えても形だけで、本音は排除する仕組みに近かったと言われています。なんだか、その時代ではそれが「公平」と説明されたこともあったそうです。
ユダヤ人への偏見や中傷も昔から似たようなパターンが続いています。社会への脅威とか、秘密主義とか、忠誠心に欠けるとか…色々言い立てられていたようですし、最近でもホロコーストの記憶を語ると「被害者ぶっている」「過去の体験を利用している」などと一部で皮肉っぽく言われることがあるみたいです。生き延びただけでも何か迷惑扱いされる雰囲気になる場面もなくはないですね。
それから、むかし植民地支配を受けていた地域出身の方々についてですが、自分たちが経験したひどい出来事について話すと、「でも鉄道とか行政制度とか言葉とか得たものもあったでしょう?」と返されるケースも多いようです。本当にそうなのかは状況によって異なるのでしょうけど。
こういう話題って、一度に全体像を掴もうとしてもどこか断片的になりがちで、人によって印象もまちまちな気がします。数字にして語られることはほとんどなく、「数十年続いた」とぼんやり言われたり、「かなり昔から」だったり…。今思えば細部まで覚えている人は少ないでしょうし、多くの場合記憶にもズレがありますよね。それでも時々こうした出来事はふと思い出されますし、人々の間で語られる内容もゆっくり変わってきているようです。
ユダヤ人への偏見や中傷も昔から似たようなパターンが続いています。社会への脅威とか、秘密主義とか、忠誠心に欠けるとか…色々言い立てられていたようですし、最近でもホロコーストの記憶を語ると「被害者ぶっている」「過去の体験を利用している」などと一部で皮肉っぽく言われることがあるみたいです。生き延びただけでも何か迷惑扱いされる雰囲気になる場面もなくはないですね。
それから、むかし植民地支配を受けていた地域出身の方々についてですが、自分たちが経験したひどい出来事について話すと、「でも鉄道とか行政制度とか言葉とか得たものもあったでしょう?」と返されるケースも多いようです。本当にそうなのかは状況によって異なるのでしょうけど。
こういう話題って、一度に全体像を掴もうとしてもどこか断片的になりがちで、人によって印象もまちまちな気がします。数字にして語られることはほとんどなく、「数十年続いた」とぼんやり言われたり、「かなり昔から」だったり…。今思えば細部まで覚えている人は少ないでしょうし、多くの場合記憶にもズレがありますよね。それでも時々こうした出来事はふと思い出されますし、人々の間で語られる内容もゆっくり変わってきているようです。
歴史が証明する「沈黙の代償」
征服とか、奴隷みたいな話や文化を消してしまうこと――どれも何かしらで正当化できるものじゃないって考える人が多いと思うけど、それでも昔から似たような言い訳がちらほら見かけられる。最近だとLGBTの人たちに対しても、差別なんて「存在しない」とか、「ちょっと神経質すぎ」「騒ぎすぎ」みたいに言われることがある。もう少し前の時代でもそうだったような気がする。実際、ヘイトクライムっぽい事件や法律で制限されそうになった時、多数派側は困惑というより、「そんなことで空気を悪くするなよ」くらいの反応を見せる場合もあったりした。ただ、不快感を理由に問題の焦点をずらそうとしても、そもそもの加害そのものは消えないんだよね。
責任という話になると、自分で暴力や迫害を選んだわけでもない人にまで押し付けるべきじゃないと思う。大半の場合、被害者側じゃなくて、その仕組みや偏見を維持したり擁護したりする立場の人こそ、本来問われてもおかしくないはず。誰かが声を上げたからって、それ自体が問題になるわけじゃなくて、本当に危険なのは安全や権利を脅かす社会構造……まあ、この辺り、意見はいろいろあるんだろうけど。
責任という話になると、自分で暴力や迫害を選んだわけでもない人にまで押し付けるべきじゃないと思う。大半の場合、被害者側じゃなくて、その仕組みや偏見を維持したり擁護したりする立場の人こそ、本来問われてもおかしくないはず。誰かが声を上げたからって、それ自体が問題になるわけじゃなくて、本当に危険なのは安全や権利を脅かす社会構造……まあ、この辺り、意見はいろいろあるんだろうけど。
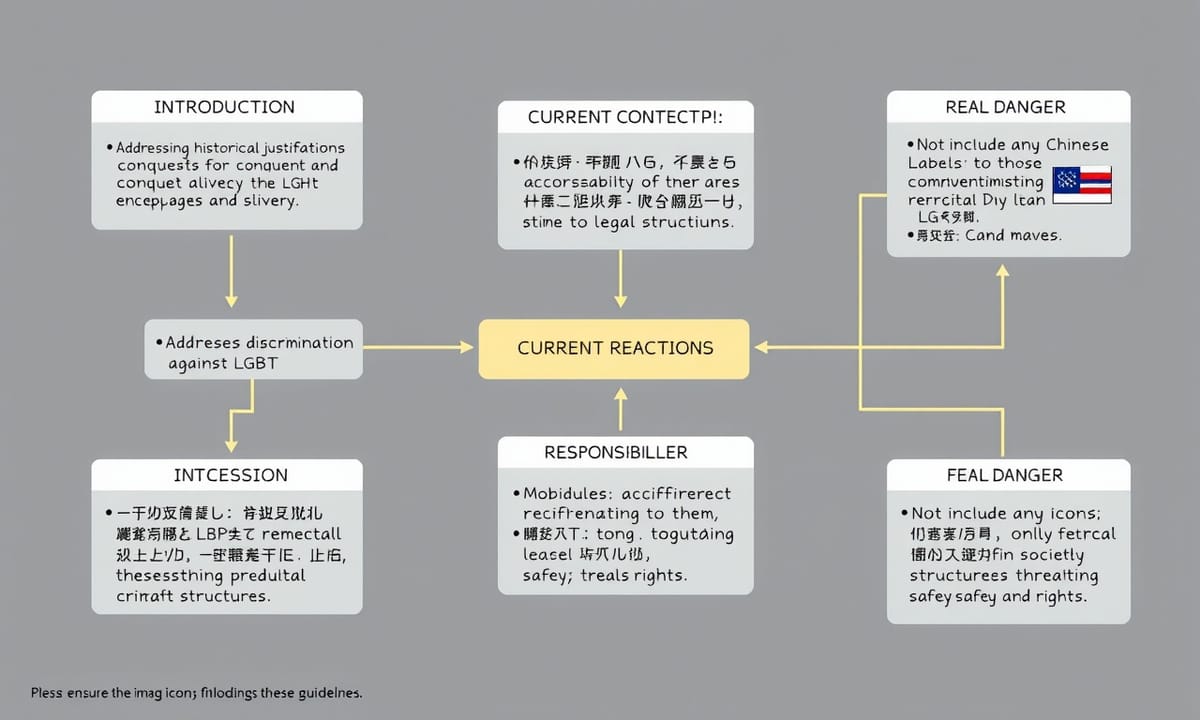
LGBTQ+への偏見も同じ構図で語られる
「両方の意見を聞くべきだ」なんて、たまにどこかで耳にすることがあるけれど、本当にそれがいつでも役立つのかどうか、ちょっと考えた方がいいかもしれない。例えば、何十年も前から続いている人種差別について、その被害に遭った人たちに対して、「じゃあ差別する側の話もちゃんと聞こう」って言えるだろうか?いや、そう簡単な話じゃない気がする。
ユダヤ系の家族を持つ人—まあ、例えば祖父母が戦争中に命を落としたようなケース—その人たちに、「ホロコースト否定論者とも冷静に意見交換してみては?」なんて声を掛ける状況って、まず現実ではあまり見かけない。そもそも、そこには大きな隔たりや傷が残っているわけで。
となると、同じような構図で考えてみてもいいのかな、と。同性のパートナーと暮らす人や、自分自身の性自認について周囲から否定されてきたトランスジェンダー当事者などにも、「あなたを否定する意見にも耳を傾けよう」と勧めることが妥当なのか。その辺り、とても難しいところだと思うし、「妥協点」を探すこと自体、不自然に感じられる場合も多い。
要は、人間としての尊厳とか存在そのものまで議論対象になる時、本当に「中立」や「歩み寄り」が成立する場面は限られているんじゃないかな、と最近ふと思う時がある。もちろん対話自体には意味があることもあるけど、それだけで全て解決できるわけでもなく…。
ユダヤ系の家族を持つ人—まあ、例えば祖父母が戦争中に命を落としたようなケース—その人たちに、「ホロコースト否定論者とも冷静に意見交換してみては?」なんて声を掛ける状況って、まず現実ではあまり見かけない。そもそも、そこには大きな隔たりや傷が残っているわけで。
となると、同じような構図で考えてみてもいいのかな、と。同性のパートナーと暮らす人や、自分自身の性自認について周囲から否定されてきたトランスジェンダー当事者などにも、「あなたを否定する意見にも耳を傾けよう」と勧めることが妥当なのか。その辺り、とても難しいところだと思うし、「妥協点」を探すこと自体、不自然に感じられる場合も多い。
要は、人間としての尊厳とか存在そのものまで議論対象になる時、本当に「中立」や「歩み寄り」が成立する場面は限られているんじゃないかな、と最近ふと思う時がある。もちろん対話自体には意味があることもあるけど、それだけで全て解決できるわけでもなく…。
人間の尊厳に「中立」は存在しない
なんだか、こういう集団って、昔から何度も「礼儀」とか「穏便さ」みたいな名目で、人間として扱われないことを求められてきた気がする。実際、それを指摘するのは特に恥ずかしいことじゃないし、むしろ時には必要だったりするのかもしれない。でも、あるグループが他の存在や生き方を公然と否定したり、消そうとしたり、法律で姿すら見えなくしようと動くときって、「ちょうどいい落とし所」みたいなものは、多分どこにも無かったりして。ただ、そのまま何もしなければ、一種の傍観というか、「中立っぽい顔をしているだけ」という雰囲気になる場面が多いと思う。
それに、不思議なほど大勢側の安心感って、大事にされやすいんだよね。ほぼ毎回と言ってもいいくらい守られてる感じがある。でも、その裏では結局、人命とか尊厳とか失われてる例もあった気がする。とは言え、「権利」というもの自体、本来なら誰かの心地よさによって左右される話じゃないはずだとも思う。多数派がちょっと不安だから、とか居心地が悪いからという理由で、ごく少数でも存在や安全や尊重まで制限される…そんな理屈って、本当に妥当なのかな?まあ、このへん曖昧なところもあるけど…。
それに、不思議なほど大勢側の安心感って、大事にされやすいんだよね。ほぼ毎回と言ってもいいくらい守られてる感じがある。でも、その裏では結局、人命とか尊厳とか失われてる例もあった気がする。とは言え、「権利」というもの自体、本来なら誰かの心地よさによって左右される話じゃないはずだとも思う。多数派がちょっと不安だから、とか居心地が悪いからという理由で、ごく少数でも存在や安全や尊重まで制限される…そんな理屈って、本当に妥当なのかな?まあ、このへん曖昧なところもあるけど…。
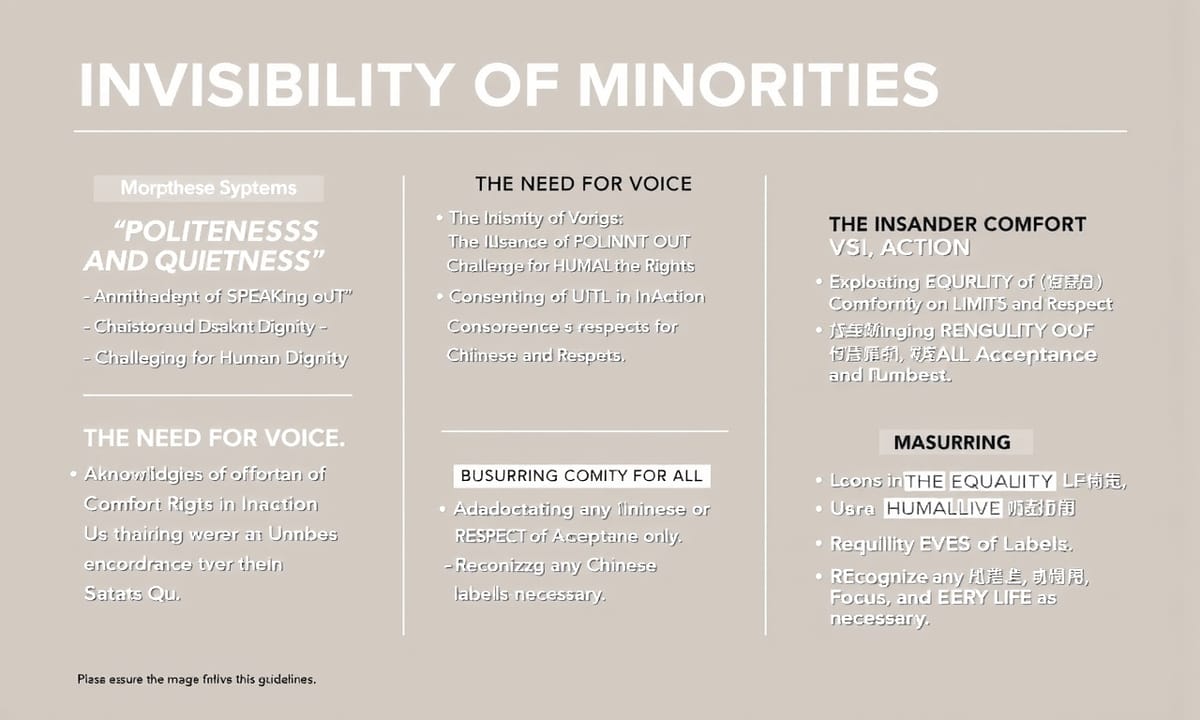
多数派の「居心地悪さ」が人権を上回るのか?
公共のトイレで「快適に過ごす権利」があるという主張、これが他人の安全を守ることより大事だと言い切れる人はあまり多くない気がする。誰かを正しい代名詞で呼ぶことがちょっと面倒だったとしても、それでその人の尊厳や認められる権利が損なわれるべきではない、と考える声も増えてきたようだし。個人的な好みとか、漠然とした不安…そういうものが、他の誰かが堂々と安心して存在できる自由まで否定する理由になるとは限らないんじゃないかな。
科学について話すと、たとえば不公平を指摘したり無知に注意を向けたりすること、それ自体に特別な恥ずかしさなんて本来ないはず。でもLGBTについて語ろうとすると、「宣伝だ」とか「何とかイデオロギー」みたいなフレーズばかり耳に入ってくる場面も少なくない。調べてみると、こうした言説は既に多くの専門家や機関によって批判されていて、確かな根拠には乏しい印象を持つ人もいる。
よく聞く話として、何となく見聞きした情報や、一部だけ抜き出された研究結果…そういったものだけを頼りに意見を組み立ててしまうケースも結構ありそうだ。全体像から切り離されているので、本来伝えたい内容とは少しズレてしまっている可能性も否定できない。科学的エビデンスへの懐疑や軽視、そのこと自体が必ずしも強い反論材料になるわけではなくて、本当はもう少し丁寧な議論が求められているようにも思う。
もちろん、この分野の話題は数十年単位で変化していて、新しい知見や社会的理解も徐々に広まってきた。ただ、「絶対こうだ」と断言できるほど十分な合意には至っていない部分も残るので、多様な視点から考えていく必要がありそうだ。
科学について話すと、たとえば不公平を指摘したり無知に注意を向けたりすること、それ自体に特別な恥ずかしさなんて本来ないはず。でもLGBTについて語ろうとすると、「宣伝だ」とか「何とかイデオロギー」みたいなフレーズばかり耳に入ってくる場面も少なくない。調べてみると、こうした言説は既に多くの専門家や機関によって批判されていて、確かな根拠には乏しい印象を持つ人もいる。
よく聞く話として、何となく見聞きした情報や、一部だけ抜き出された研究結果…そういったものだけを頼りに意見を組み立ててしまうケースも結構ありそうだ。全体像から切り離されているので、本来伝えたい内容とは少しズレてしまっている可能性も否定できない。科学的エビデンスへの懐疑や軽視、そのこと自体が必ずしも強い反論材料になるわけではなくて、本当はもう少し丁寧な議論が求められているようにも思う。
もちろん、この分野の話題は数十年単位で変化していて、新しい知見や社会的理解も徐々に広まってきた。ただ、「絶対こうだ」と断言できるほど十分な合意には至っていない部分も残るので、多様な視点から考えていく必要がありそうだ。
科学的事実を無視する人たちへの反論
なんというか、「議論」って感じでもないし、「ただの意見」みたいな言い方もちょっと違う気がする。無知というより、あえて知らないふりをしているような態度が時々ある。こういうのは、誰かのためにも、事実をきちんと守る意味でも、放っておくのはどうかなと考えさせられることがあるんだよね。間違った話が正しい情報として広まると、その影響を受ける人も出てくるし。
何も言わずに黙ってしまうこと、それ自体がむしろ問題だと思われる場面もたまに見かける。話すこと、体験を語ること、不公平や理不尽さを指摘する行為…これらは「被害者ぶっている」というより、多分どこかで消えたくない気持ちとか、自分の存在を示したい感覚に近いものじゃないかな、と感じたりする。声を上げたり、状況について伝えることで世界に鏡を差し出して、「ちゃんと現実を見てほしい」と呼びかけているつもりなのかもしれない。ただ、それだけで全部解決するとまでは言えないし、人によっては共感しづらいところもあると思う。でも、こういう取り組み自体には意味がありそうだな、と最近考えるようになった。
何も言わずに黙ってしまうこと、それ自体がむしろ問題だと思われる場面もたまに見かける。話すこと、体験を語ること、不公平や理不尽さを指摘する行為…これらは「被害者ぶっている」というより、多分どこかで消えたくない気持ちとか、自分の存在を示したい感覚に近いものじゃないかな、と感じたりする。声を上げたり、状況について伝えることで世界に鏡を差し出して、「ちゃんと現実を見てほしい」と呼びかけているつもりなのかもしれない。ただ、それだけで全部解決するとまでは言えないし、人によっては共感しづらいところもあると思う。でも、こういう取り組み自体には意味がありそうだな、と最近考えるようになった。
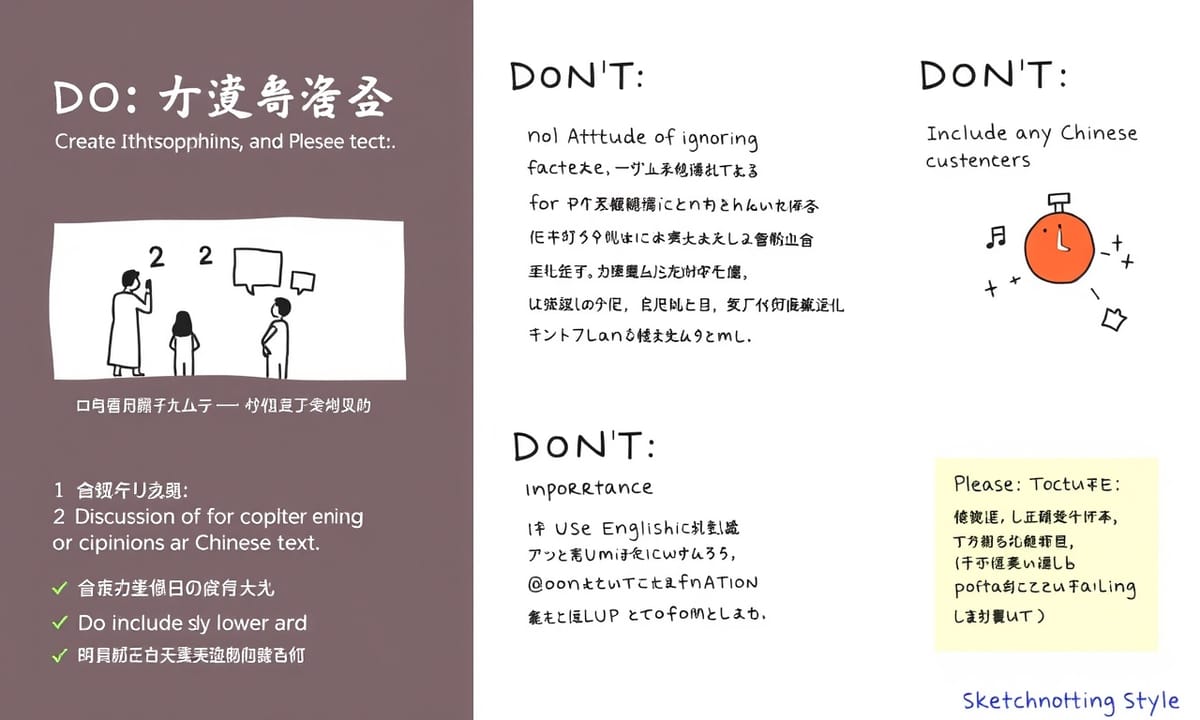
声を上げることが社会を変える唯一の方法
過去、何かを防ごうとする時、結局は傷つくことに向き合わなければならない場合が多いようだ。沈黙って、不思議なくらい色んなことを許してしまうんだよね。昔の話だけど、人々が収容所に連れて行かれるよりも前に、なんとも言えない静けさがあったと聞いたことがある。エイズで多くの人たちが亡くなった時代も、世間はほとんど声を上げなかった気がするし、今でも大勢には見えていない差別や不公平さみたいなものが、昼間堂々と続いているのもそのせいかもしれない。
正直、それを打ち破るためには、ちょっと騒々しくなるくらいじゃないと難しい場面もあると思うんだ。ただ感情的になったり、少し強めに主張したり…それ自体は好まれない場合もありそうだけど。実際、一部の人たちは見て見ぬふりをしたがる傾向もあるから、その目の前に現実を突きつけるしか方法が無い時だってある。でも、それで全て変わるとは限らないし、多分状況によるんだろうね。
正直、それを打ち破るためには、ちょっと騒々しくなるくらいじゃないと難しい場面もあると思うんだ。ただ感情的になったり、少し強めに主張したり…それ自体は好まれない場合もありそうだけど。実際、一部の人たちは見て見ぬふりをしたがる傾向もあるから、その目の前に現実を突きつけるしか方法が無い時だってある。でも、それで全て変わるとは限らないし、多分状況によるんだろうね。
沈黙こそが最大の脅威だという真実
どこかで、誰かが標的にされること自体を恥ずかしいと思いがちだけど、実際はそれを仕掛ける側のほうに責任があるような気もする。うーん、そういう話って七十回くらい聞いたことあるし、正直なところ、みんな考え方は似ているのかな。人権に関して中間みたいなものが存在するかどうか…たぶん「あいまい」なのを許す人もいるだろうけど、結局「事実」しか残らない場合が多い、と何人かから聞いた記憶がある。
真実って…誰か一握りの勇気ある人たちが口に出さない限り、そのまま埋もれてしまうことも珍しくない。まあ、「勇敢」と言えるほどじゃなくても、小さな声でも響く瞬間があれば、それだけでも十分意味はありそうだよね。
ああ、それと名前を書き忘れそうになったけど……ダイナより。
真実って…誰か一握りの勇気ある人たちが口に出さない限り、そのまま埋もれてしまうことも珍しくない。まあ、「勇敢」と言えるほどじゃなくても、小さな声でも響く瞬間があれば、それだけでも十分意味はありそうだよね。
ああ、それと名前を書き忘れそうになったけど……ダイナより。



















































