家庭環境の見直しで子供の幸福度を日常から高めるヒント
- 毎週3回以上、子供と10分以上ゆっくり話す時間をつくる
親が寄り添い会話することで、自己肯定感や幸せ実感が安定しやすい
- 家族全員で月に1回は外出やイベント体験を共有する
共同体験が思い出となり、家族関係の満足度も幸福度も向上しやすい
- 一日の終わりに子供へ「今日楽しかったこと」を尋ねてみる
`楽しい`という感覚に意識が向き、精神的な充実感につながる可能性が高まる
- "ありがとう"などポジティブな声かけを1日5回意識して伝える
親から受け取る温かさは長期的な心の安定・人間関係構築力にも影響する
家庭環境で子供の幸福度を見極める方法
学校に通っていたあの頃、クラスにはどうも疲れ果てた雰囲気が染みついている女の子が一人いたんだよね。まあ、正直なところ、その子の制服はしょっちゅう汚れていてさ、それに宿題もあまり出していなかった気がする。なんだろう……教室に座ると微かにアルコールの匂いが彼女から漂ってきたりして、内心ギョッとした覚えがある。そう言えば、まだ12歳だったと思う、多分間違ってないはず。
そんなある日の午後――忘れもしない理科のグループ課題でね、僕らは彼女の家を訪問することになった。玄関を開けると、一瞬ふわっとよぎる緊張感。その時、お父さんらしき人がコットで横になりながらシャツも着ずに台所で誰かへ向かって大声で叫びまくってた。本当に今思い返しても胸が苦しくなる場面だった。お母さんは、と言えば下を向いたままただせわしなく部屋から部屋へ移動してて…妙な沈黙というか隙間風みたいなのが家全体に流れていた気さえする。
結局その日、彼女自身はほぼ口を開かなかった。ただ静かに僕らの会話を聞いているだけで――どこか遠い世界にいるようにも見えた。あの日、自分は何かわからないけど、大切なことを学ばされた気がしたんだ…。ま、いいか。でもやっぱり忘れられない瞬間なんだよね。
そんなある日の午後――忘れもしない理科のグループ課題でね、僕らは彼女の家を訪問することになった。玄関を開けると、一瞬ふわっとよぎる緊張感。その時、お父さんらしき人がコットで横になりながらシャツも着ずに台所で誰かへ向かって大声で叫びまくってた。本当に今思い返しても胸が苦しくなる場面だった。お母さんは、と言えば下を向いたままただせわしなく部屋から部屋へ移動してて…妙な沈黙というか隙間風みたいなのが家全体に流れていた気さえする。
結局その日、彼女自身はほぼ口を開かなかった。ただ静かに僕らの会話を聞いているだけで――どこか遠い世界にいるようにも見えた。あの日、自分は何かわからないけど、大切なことを学ばされた気がしたんだ…。ま、いいか。でもやっぱり忘れられない瞬間なんだよね。
親ライセンス構想が抱える根本課題を考える
見た目だけで家庭環境が良いか悪いかなんて判断できるものじゃない、まあ当然だよね。だけど、もし明らかな場合は、その光景、一度目に焼き付くとなかなか頭から離れなくなる。忘れようとしたってダメなんだ。何年か後だったかな、ヒュー・ラフォレット(Hugh LaFollette)による「親の免許制」という話を耳にした瞬間、不思議とあの少女のことがふっと蘇った。いや、この理屈だけ聞けば至極まっとうに響くんだよね。自動車を運転するなら免許が必要なのだから、人ひとり――もっとも重大な責任と言える養育行為についても何らかの資格や認可が必要では?と思う気持ちも分からなくない。
けれど…次々とモヤモヤ疑問が噴き出すんだ。ルールを誰が設定するんだろう?そのテスト、誰がデザインするつもり?そして、それは果たして私が子供時代を過ごしたインドという土地で体得してきた価値観とか慣習――全部無視してしまう「西洋式育児」の点検表みたいなものになるんじゃない?下手するとバカにさえされちゃうぞ、などともちらついた。それになにより、「試験」に落ちた人や受験自体を拒否する人――その人達の子供はいったいどうなっちゃうわけ?
こういう考え方って、一応「将来ある子供たちの幸福」を願って生まれる善意からきてるとは思う。たださ、「いいアイディア」が実際社会制度として動き始めると、びっくりするくらい唐突に抑圧的だったり暴力的になってしまう可能性――そればっかりは拭えない。不穏、と言ったほうが近いかも知れない。ま、いいか。
けれど…次々とモヤモヤ疑問が噴き出すんだ。ルールを誰が設定するんだろう?そのテスト、誰がデザインするつもり?そして、それは果たして私が子供時代を過ごしたインドという土地で体得してきた価値観とか慣習――全部無視してしまう「西洋式育児」の点検表みたいなものになるんじゃない?下手するとバカにさえされちゃうぞ、などともちらついた。それになにより、「試験」に落ちた人や受験自体を拒否する人――その人達の子供はいったいどうなっちゃうわけ?
こういう考え方って、一応「将来ある子供たちの幸福」を願って生まれる善意からきてるとは思う。たださ、「いいアイディア」が実際社会制度として動き始めると、びっくりするくらい唐突に抑圧的だったり暴力的になってしまう可能性――そればっかりは拭えない。不穏、と言ったほうが近いかも知れない。ま、いいか。

家庭の経済状況より大切な親の愛情とは何か知る
どうにも、貧しい家に生まれたってさ、親ができるだけの愛情とか時間を、ほとんど全部そそいで子どもを育てているのを何度も見てきたんですよ。子どもたちは、ちゃんと幸せそうだったし、それなりに世間とも折り合いつけてる様子が妙に印象に残った。逆に、裕福な家庭で何不自由なく育ったはずなのに、不安ばかりを心の底で抱えながら、「自分はまだ足りない」とずっと思い込んじゃって…静かなる問題児になってしまうケースも目についた。いや、本当に不思議ですよね、この現象。こういうあれこれ見てきた身としては、“ライセンス制度”とか導入したら、まあ極端すぎる事例なんかは多少抑え込むこと自体は可能だとは感じます。でも、「毎日の苦労の中でも、自分が親として本気で子どもの力になりたいと思う、その願い」みたいな芯の部分って、一体誰がどう測れるんでしょう。そこだけ欠けちゃえばさ、ほかの条件全部満たしていても全然意味ないんじゃないかな…ま、いいか。
### ケア(思いやり)はテストで測れない
ちょっと昔の話になるけれど、自分がアメリカで修士課程やってた頃ね、不意に養子縁組したばっかりのご夫婦と知り合う機会があった。その二人から聞いたエピソードでは、「書類作成・インタビュー・身元調査……とにかくめちゃくちゃ手順多い“登山”みたいだ」と言われてしまったよ。それだけじゃなくて、経済的安定とか精神面だけ確認されるわけでもなく、一応なんとなく信じるべき子育て観みたいなの提示求められたり、その養子縁組機関創設者独自による初期段階から規定された宗教上必要な要件も示さなきゃならなかった、と。「結局このプロセス自体は、本当の能力を見る試験というより、“こういう型”というメンバー枠へ合致しているかふるい分けする色合いが強すぎない?」――そんな風にも思わざるを得なかったですね。しかも、その「型」自体だって誰が決めるかによってガラリと変わっちゃうし。この仕組みもし仮に全員へ適用しようとした場合、その副作用や広がるリスクも大きく膨れてしまうだろうなぁ…なんというか釈然としない部分、多すぎです。
### ケア(思いやり)はテストで測れない
ちょっと昔の話になるけれど、自分がアメリカで修士課程やってた頃ね、不意に養子縁組したばっかりのご夫婦と知り合う機会があった。その二人から聞いたエピソードでは、「書類作成・インタビュー・身元調査……とにかくめちゃくちゃ手順多い“登山”みたいだ」と言われてしまったよ。それだけじゃなくて、経済的安定とか精神面だけ確認されるわけでもなく、一応なんとなく信じるべき子育て観みたいなの提示求められたり、その養子縁組機関創設者独自による初期段階から規定された宗教上必要な要件も示さなきゃならなかった、と。「結局このプロセス自体は、本当の能力を見る試験というより、“こういう型”というメンバー枠へ合致しているかふるい分けする色合いが強すぎない?」――そんな風にも思わざるを得なかったですね。しかも、その「型」自体だって誰が決めるかによってガラリと変わっちゃうし。この仕組みもし仮に全員へ適用しようとした場合、その副作用や広がるリスクも大きく膨れてしまうだろうなぁ…なんというか釈然としない部分、多すぎです。
テストでは測れない親子ケアの違いを認識する
親というものを「資格」なんてコーディングしてしまうと、正直言ってヤバいことになる予感がする。ふと自分の身の回りでね、長年ひとりで働いているシングルマザーが、子どもたちを祖父母に預けてるってだけで「ダメな親」ラベル貼られたことあったんだ。でもさ、その子どもらはすごく元気に育ってる。不思議だよな...ま、いいか。このロジックをそのまま進めていけば、自分が昔お世話になった大学教授とか確実にクリアできるんじゃないかな。彼は授業の腕こそ一流だったが、とにかく仕事優先、人との心情にはそんなに細やかじゃなかった記憶がある。それなのに一方で、ごく狭い六畳ほどの部屋で三人の穏やかで知恵ある息子たちを立派に育て上げた女性—この人、おそらく規準から外されそう。何故なんだろう、この妙なしっくりこない感じ。曖昧だけど、「誰でも納得しそうな尺度」を欲張れば欲張るほど、危険性は雪だるま式...いや、指数関数的とも言える?…うん。考え込んじゃう。同じ地区内でも、生活費工面するため日夜働きづめ、その間だけ子を祖父母宅へ預けただけの母親が批判された事例も目撃した。しかし現実には、その家庭も子ども達自身もしっかり暮らしていたと思うんだよね。その原理からすると、「専門性高いがお堅い旧友教授」は問題なく評価されるわけ。でも、小さいながら明晰な心持ちを持つ三兄弟全員まとめて立派に育て抜いた人は、不適格扱いになる理不尽さ…。だからさ、「こうあるべき親像」を定義ごと塗り替えちゃおうみたいな動き自体が、本当に怖い道なんじゃないかなと思ってしまう。いやあ、不条理にも程がある気がしてならない。

コミュニティ基準と個人基準が育児評価にどう影響するか探る
大学で一年間教えたっていう経験が一応あるんだけど、まあ…教育に「人を変える力」があるのは本当だと思う。でも、それって正直、本人が心から何かしら変わりたいと望まない限り、どうにもならないところがあるんだよね。例えばさ、子どもの発達段階や社会的コミュニケーション、幼児期の癇癪への対応策とか――そういった話は授業でしっかり扱うことができる。でもさ、「共感力そのもの」って教えることなんて無理ゲーじゃない?いや、ほんと。「ああ、これ自分で身につけなきゃダメなんだろうな」ってつくづく思う時が多い。
深夜3時、赤ちゃんがぎゃんぎゃん泣いていて、自分自身もう何日もまともに眠れてないとする。こんな極限状態で「忍耐力とは体系的にこうです」なんて言葉並べても正直ピンとこない気がしてさ。そりゃ授業によって新しい知識や方法論は得られるし、その点は確実だと思うんだけど、「この領域には目を背けたままでいたい」みたいな部分まで他人の中身をガラッとは動かせない。...ま、いいか。(笑)
ちょっと思い出すのは昔会った父親の言葉だった。「本気で大切に思う気持ちは教えることなんてできませんよ(You can’t teach giving a damn)」…いやぁ、この台詞、本当にただそれだけなんだけど不思議なくらい響いた。シンプルすぎて拍子抜けするのに、それでも事実として重みがあるよなぁ。
害悪って、一見ド派手な形では現れないケースも普通に多い。その影響とか余波みたいなのは妙に長引くし。不適切な育児とか語る時、多くの人はいきなり虐待—殴る蹴るネグレクト、大声上げて路上で怒鳴り散らす、とか—一番ひどいやつばっか想像したりしちゃうものなんじゃないかな。
深夜3時、赤ちゃんがぎゃんぎゃん泣いていて、自分自身もう何日もまともに眠れてないとする。こんな極限状態で「忍耐力とは体系的にこうです」なんて言葉並べても正直ピンとこない気がしてさ。そりゃ授業によって新しい知識や方法論は得られるし、その点は確実だと思うんだけど、「この領域には目を背けたままでいたい」みたいな部分まで他人の中身をガラッとは動かせない。...ま、いいか。(笑)
ちょっと思い出すのは昔会った父親の言葉だった。「本気で大切に思う気持ちは教えることなんてできませんよ(You can’t teach giving a damn)」…いやぁ、この台詞、本当にただそれだけなんだけど不思議なくらい響いた。シンプルすぎて拍子抜けするのに、それでも事実として重みがあるよなぁ。
害悪って、一見ド派手な形では現れないケースも普通に多い。その影響とか余波みたいなのは妙に長引くし。不適切な育児とか語る時、多くの人はいきなり虐待—殴る蹴るネグレクト、大声上げて路上で怒鳴り散らす、とか—一番ひどいやつばっか想像したりしちゃうものなんじゃないかな。
教育や制度改革でどこまで親の力は伸ばせるか見直す
けれどね、いわゆる“悪い育児”というのは大抵の場合、とても静かに進んでいくものなんだよね…。気づかないうちに少しずつ蝕まれるっていうか。実は今も定期的にセラピーを受けている知人がいるんだけど、その理由は親から殴られたとか、何か大きな被害があったせいじゃない。ただ家の中で「心の拠り所」みたいなものを感じたことが一度もなかった――それだけ。例えばさ、「男だから我慢しろ」と何度も言われ続けてきたり、「泣いてはいけない」と抑えこまれて、最終的には喜びも哀しみも分からなくなっちゃう、そんな話も珍しくない。それと、もう一人の友達。彼のお父さんは社会でも有名な学者だったんだけど、不思議と、息子の間違いや失敗を指摘する時しか向き合ってくれなかった。「褒める」ということがごく稀。ある女友達のお母さんに至っては、自身へ「謙遜こそ自己価値より上等だ」なんて繰り返し語り聞かせてきた結果として、娘(つまり僕の友人)のささいな成功すら祝ったためしがない。うーん、結局どちらの場合でも、「自分が大切で価値ある存在なんだ」という感覚――これを培える雰囲気じゃ全然無かった気がする。
子供を守るための制度ですら、ときに本来の意味から外れてしまう。それくらい現実は皮肉だよね…。アメリカ合衆国ではChild Protective Services(児童保護サービス)という公的機関があって、不適切と思われる家庭から子供たちを引き離して里親制度に移す事例も知っている。でもそこでまた違う種類のトラウマ体験をしてしまうケースもしばしば耳にする。本来的には緊急時の安全確保策なんだけど――長期的・構造的解決には程遠いことだって多くて、新しい里親環境=絶対的改善とは限らない。不完全さから不完全さへの移動…そんな転落にも見えて仕方ない。
そういえば…自分自身でかなり印象深かった出来事がある。初めて姉妹夫婦がお子さんを授かった時、お祝いに顔を出したんだ。その二人、高学歴で情愛深さでも周囲から信頼されていた。でも、生まれたばかりの小さな命を前に腕でぎこちなく包むその様子には、本当にどう扱えばいいかわからず戸惑い揺れていた。ま、それだけ悩みながら必死になってくれるほうが、本当はずっと救われるんじゃないかなぁ、と妙に考え込んじゃったよ。
子供を守るための制度ですら、ときに本来の意味から外れてしまう。それくらい現実は皮肉だよね…。アメリカ合衆国ではChild Protective Services(児童保護サービス)という公的機関があって、不適切と思われる家庭から子供たちを引き離して里親制度に移す事例も知っている。でもそこでまた違う種類のトラウマ体験をしてしまうケースもしばしば耳にする。本来的には緊急時の安全確保策なんだけど――長期的・構造的解決には程遠いことだって多くて、新しい里親環境=絶対的改善とは限らない。不完全さから不完全さへの移動…そんな転落にも見えて仕方ない。
そういえば…自分自身でかなり印象深かった出来事がある。初めて姉妹夫婦がお子さんを授かった時、お祝いに顔を出したんだ。その二人、高学歴で情愛深さでも周囲から信頼されていた。でも、生まれたばかりの小さな命を前に腕でぎこちなく包むその様子には、本当にどう扱えばいいかわからず戸惑い揺れていた。ま、それだけ悩みながら必死になってくれるほうが、本当はずっと救われるんじゃないかなぁ、と妙に考え込んじゃったよ。
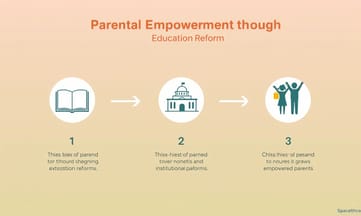
静かな虐待がもたらす長期的な心への影響に気付く
彼らは赤ちゃんの包み方すら、まだよく分かっていなかった。……あのとき、「それで、このまま家に連れて帰るつもりなの?」なんて、ふと思った覚えが今も残っている。いや、本当に。他愛ないことに聞こえるかもしれないけど、ほんの数週間でもいいから、訓練を受けた産後ドゥーラがそばについて感情的なサポートとかガイド役をしてくれていたなら――出産直後のどうしようもないストレスや途方に暮れる気持ちも随分と和らいだはずだ。
育児という営み自体、そもそも昔は共同体の力や友人・知人との繋がりで成り立っていたものだったんじゃないか、と時々思う。とは言え、その村やご近所さん同士で子育てする日常なんて、とっくに過去になってしまったわけで……現代ではもう孤独になるほうが圧倒的に普通、口にもできない不器用さや失敗だって、何層にも重なってしまいがちな世の中なのかもしれない。
でも、本当によく考えると、一部の苦しい状況とか重たいストレスって実用面・経済面・メンタルケアや学び直しなど幅広い支援によって結構避けることができる場合だってあるんじゃない?現実には社会全体として「個人」に責任を押しつける空気が強い気がするし、それより人を成功させられる仕組み作りを優先するべきじゃないかな、と感じてしまう。
それから、「親として資格制度」みたいなアイディアは一見するとシンプルだけど、有給休暇付きで誰でも平等に使える育児休業とか手頃なチャイルドケア、多様なメンタルヘルス支援──こういう誰ひとり取りこぼさず提供される仕組みを実現するほうが断然複雑なんだけど、より真っ当というかリアリティある答えなんじゃないだろうか。一瞬インパクトある対策より、本質的な「助け合い」の形こそ大切なのでは…なんて考えてしまう。
僕自身、「統制」よりたぶん「コミュニティ」に希望を見出したくなるタイプだと思う。正直ね、国が「何人まで子どもOK」と決めるような世界なんて想像したくない。それこそ身震いしてしまうような未来しか待っていない、と感じざるを得なくなる。ま、いいか。
育児という営み自体、そもそも昔は共同体の力や友人・知人との繋がりで成り立っていたものだったんじゃないか、と時々思う。とは言え、その村やご近所さん同士で子育てする日常なんて、とっくに過去になってしまったわけで……現代ではもう孤独になるほうが圧倒的に普通、口にもできない不器用さや失敗だって、何層にも重なってしまいがちな世の中なのかもしれない。
でも、本当によく考えると、一部の苦しい状況とか重たいストレスって実用面・経済面・メンタルケアや学び直しなど幅広い支援によって結構避けることができる場合だってあるんじゃない?現実には社会全体として「個人」に責任を押しつける空気が強い気がするし、それより人を成功させられる仕組み作りを優先するべきじゃないかな、と感じてしまう。
それから、「親として資格制度」みたいなアイディアは一見するとシンプルだけど、有給休暇付きで誰でも平等に使える育児休業とか手頃なチャイルドケア、多様なメンタルヘルス支援──こういう誰ひとり取りこぼさず提供される仕組みを実現するほうが断然複雑なんだけど、より真っ当というかリアリティある答えなんじゃないだろうか。一瞬インパクトある対策より、本質的な「助け合い」の形こそ大切なのでは…なんて考えてしまう。
僕自身、「統制」よりたぶん「コミュニティ」に希望を見出したくなるタイプだと思う。正直ね、国が「何人まで子どもOK」と決めるような世界なんて想像したくない。それこそ身震いしてしまうような未来しか待っていない、と感じざるを得なくなる。ま、いいか。
ワンオペ育児時代に必要な社会支援策を押さえる
歴史ってさ、「保護」っていうきれいな言葉の裏で、権力側が気づけば主導権をぎゅっと握る流れになりやすい - しかも、そこから優生思想へと転落するまでが妙に速かったりする。ま、そう思う。悪質な親が現実にいることは否定しないけど、問題自体は「ダメ親の有無」じゃなくて、本当に必要なのは生殖そのものを制限するべきか、それとも周囲を守る工夫を施すのか、その違いだと思うんだよね。自分が知る限り、家庭環境に色々難題があった子どもでも、不思議と真っ当に育っているケースには必ず家族以外のおとな - 例えば隣人とか先生とか親戚とか - その誰かしら大人の存在介入がセットだった印象ある。
ある日近所のおじさんがクリケット教えてくれたり、たまたま担任が耳傾けてくれたり、安全地帯として親類宅を開放してくれたり……それぞれ小さいことだけど、それら外部からの支えによって直接的な害悪みたいなのもうまく薄められてた感じ。複数のおとな達と日常的に関わっていた子ならなおさら、大人目線も増えるし虐待みたいな出来事をごまかし続けることだって難しくなる。当然ながら社会的な実践例にも触れる機会は自然と広がるわけで。この理由で正直、自分としては地域コミュニティへの予算投入案には全面的に賛成したくなるんだよね……いやまあ完璧解じゃないけどさ。
たとえば妊娠期から受講できる無料育児セミナー+参加意欲につながる金銭インセンティブ導入とか(これちょっと画期的で面白そう)。親同士で経験や悩み情報交換できる非公式ネットワーク構築、新生児誕生後には訓練済みヘルパーによる家庭訪問型フォローで早期対応サポート体制づくり、といったものまで含めて考えたい気持ちになる。そして学校現場にも当然求められるよね - 家庭内ストレスや異変サインを察知できて尚且つ親を傷つけず恥じさせないプロフェッショナル研修、これは絶対欠かせない要素かな。ま、いいか。
ある日近所のおじさんがクリケット教えてくれたり、たまたま担任が耳傾けてくれたり、安全地帯として親類宅を開放してくれたり……それぞれ小さいことだけど、それら外部からの支えによって直接的な害悪みたいなのもうまく薄められてた感じ。複数のおとな達と日常的に関わっていた子ならなおさら、大人目線も増えるし虐待みたいな出来事をごまかし続けることだって難しくなる。当然ながら社会的な実践例にも触れる機会は自然と広がるわけで。この理由で正直、自分としては地域コミュニティへの予算投入案には全面的に賛成したくなるんだよね……いやまあ完璧解じゃないけどさ。
たとえば妊娠期から受講できる無料育児セミナー+参加意欲につながる金銭インセンティブ導入とか(これちょっと画期的で面白そう)。親同士で経験や悩み情報交換できる非公式ネットワーク構築、新生児誕生後には訓練済みヘルパーによる家庭訪問型フォローで早期対応サポート体制づくり、といったものまで含めて考えたい気持ちになる。そして学校現場にも当然求められるよね - 家庭内ストレスや異変サインを察知できて尚且つ親を傷つけず恥じさせないプロフェッショナル研修、これは絶対欠かせない要素かな。ま、いいか。

社会的コントロールと共同体サポート、どちらが効果的か比べる
子どもを守るって、何を最優先にするか――本当に考え出すと迷いも出るし、単純じゃないんだよね。ま、それが現実か。誰しもが同じ意見ってことはまずないけど、それでも「テストに合格」というシンプルでわかりやすい基準には妙な安心感もある…正直。でもさ、人生自体がそんな型にはまらないからうまくいかなくて当然という気もしてしまう。立派な親だからといって常に成功するとは限らないのは、多分みんな薄々わかってるんじゃないかな。逆に、ありふれた普通の親であったとしても、適切な支援ひとつで見違えるくらい素敵になれたり。その一方、ごく当たり前そうに順風満帆に見える人でも、自分では全然気づかない間に子どもの心を測れぬ形ですり減らせてしまうこと、本当に起き得るから厄介なんだよ。
いやぁ…愛情とか細やかな配慮って、規則や数値みたいに標準化できっこないと思うんだよね。不思議なもので、深く悩めば悩むほど、「育児=完璧なスキル」みたいな発想そのものがむしろ虚しいというか。結局は日々積み重ねる継続と、小さな覚悟の繰り返しかもしれないと思い知らされる。でも制度によって多少楽になる時期もあったし、研修受ければ構え方にも幅が生まれる場合だってある。それこそ法律なら極端なケースだけは罰してくれる……とはいえ、本当に大事なのは目の前の我が子を意識的に「ちゃんと見る」と決め、その瞬間ごとの小さな感情にも手間暇惜しまない態度、その上で親としての重責とも向き合いつつ信頼関係を折れず保とうとジタバタするしか…。若かった自分は、「有能=知識量勝負」ぐらいで高を括ってたところあるし、その陰で本質的な微妙さとか見落としていた自信だけはいっちょ前だったような気までして――なんとなく情けなくなる…そんな今なんだ。
いやぁ…愛情とか細やかな配慮って、規則や数値みたいに標準化できっこないと思うんだよね。不思議なもので、深く悩めば悩むほど、「育児=完璧なスキル」みたいな発想そのものがむしろ虚しいというか。結局は日々積み重ねる継続と、小さな覚悟の繰り返しかもしれないと思い知らされる。でも制度によって多少楽になる時期もあったし、研修受ければ構え方にも幅が生まれる場合だってある。それこそ法律なら極端なケースだけは罰してくれる……とはいえ、本当に大事なのは目の前の我が子を意識的に「ちゃんと見る」と決め、その瞬間ごとの小さな感情にも手間暇惜しまない態度、その上で親としての重責とも向き合いつつ信頼関係を折れず保とうとジタバタするしか…。若かった自分は、「有能=知識量勝負」ぐらいで高を括ってたところあるし、その陰で本質的な微妙さとか見落としていた自信だけはいっちょ前だったような気までして――なんとなく情けなくなる…そんな今なんだ。
日々子供へ愛を注ぐ実践が全てを左右する理由を理解する
子育てに必要な力ってさ、混乱した時にとりあえず自分をなだめることだったり、思い切り間違えちゃった時に素直に謝れる柔らかさ、それから…んー、ぱっと見どうでもよさそうな場面であえて子どものプライドというか、その小さな尊厳をちゃんと意識し続ける態度とか、そんなもんなんじゃないかな。ま、正直言ってこういう感覚は紙の試験で測れる類いの話じゃない気がする。社会全体でこれに本当に決定打を出すのは…やっぱ無理筋なのかもしれないね。そもそも私自身ずっと疑問だった。一つだけはっきりしていることがある。「毎日、本気で目の前の子と向き合う」――この地味だけど重たい営みって、どんなライセンスだろうと資格やチェックリストごっこだろうと、たぶん絶対替えがきかないと思う。結局、それしかない。なぜって、小さい人たちはひたむきな愛情と細やかな受け止めの中でこそ一番元気になれる生き物なんだからさ。ほんと、不思議なくらい。ま、いいか…。


