職場の熱中症リスクを具体的に減らし、安全な労働環境を実現するための即行動ガイド
- 業務開始前にWBGT値(暑さ指数)を毎日チェック、28以上で作業時間を30%短縮。
暑さ指数が高い日に作業量調整するだけで重篤な熱中症災害の発生率が下がるから。
- 1時間ごとに最低200mlの水分補給タイムを設け、徹底して全員実施。
定期的な水分摂取は脱水や意識障害による事故防止につながる。
- 体調異変時は直属上司へ即時報告し、その場で休憩または医療機関相談ルールを共有。
初期対応遅れによる重篤化や死亡例が多数報告されているため。
- "クールビズ"や扇風機・冷却グッズ活用など、服装や現場環境改善策も最低2つ以上導入。
"我慢"ではなく物理的対策併用こそ確実な予防につながる。
父親が夏に亡くなった後、息子は野球の試合を待ち続けたけど、その試合は決して来なかった
去年の夏だったか、ある父親が亡くなった。息子さんは、玄関先でグローブを持ちながら、どうやら結局できなかったキャッチボールを待っていたみたいだ。火事でもないし、高い足場から落ちたわけでもない。仕事現場で…炎天下だったと思うけど、日陰もあまりなくて、水も休憩もほとんど取れなかったという話だ。確かに似たような出来事は毎年のように耳にする気がする。
ワシントンD.C.の集会で、国際ペインターズ・同盟とかいう団体の安全担当者、ケネス・シール氏って人が「これが特別な話とは言えません」と口にしていた記憶がある。「こういうことは夏になると誰かのお父さんだったり、お兄さん、お母さんや娘さんにも起きています」とも彼は続けていた。ただ皆“自分には起きない”とか、“まあ大丈夫だろう”なんて思い込んでるだけじゃないか、と少し遠回しに語っていたようだ。でも実際のところ、「根性」では熱中症は防げなくて、計画的な対策こそ重要なんじゃないか…という意見だったかな。
働く人たちへの暑さ対策を怠るなら、それは命を賭けているようなもの、とそんなニュアンスもあった気がする。彼が発言したこの集会自体、多分全国各地で十数カ所くらい開かれていたらしい。他にも労働者支援団体が連携していて、この時期ちょうどOSHA(労働安全衛生庁)による新しい熱中症基準についての公聴会とも重なっていたようだ。全部正確じゃないかもしれないけど、大体そんな流れだったと思う。
ワシントンD.C.の集会で、国際ペインターズ・同盟とかいう団体の安全担当者、ケネス・シール氏って人が「これが特別な話とは言えません」と口にしていた記憶がある。「こういうことは夏になると誰かのお父さんだったり、お兄さん、お母さんや娘さんにも起きています」とも彼は続けていた。ただ皆“自分には起きない”とか、“まあ大丈夫だろう”なんて思い込んでるだけじゃないか、と少し遠回しに語っていたようだ。でも実際のところ、「根性」では熱中症は防げなくて、計画的な対策こそ重要なんじゃないか…という意見だったかな。
働く人たちへの暑さ対策を怠るなら、それは命を賭けているようなもの、とそんなニュアンスもあった気がする。彼が発言したこの集会自体、多分全国各地で十数カ所くらい開かれていたらしい。他にも労働者支援団体が連携していて、この時期ちょうどOSHA(労働安全衛生庁)による新しい熱中症基準についての公聴会とも重なっていたようだ。全部正確じゃないかもしれないけど、大体そんな流れだったと思う。
労働安全の専門家が語る「熱中症は我慢では防げない」という現実
去年の夏頃、労働現場で暑さから身を守るための基準が必要だと専門家たちが言い始めてから、もう半世紀近く経ったような気がするけれど、つい最近になってバイデン政権が草案を出した。二〇二四年に入ってからも、全米各地で十数人ほどの作業者が屋根工事やコンクリート打設、それに畑仕事や建設現場のごみ片付けなんかで、かなり蒸し暑い中で倒れて命を落としたという話が伝わってきた。月曜日にはワシントンD.C.で厚生省の管轄する労働安全衛生局による公聴会も始まったらしい。
統計だと過去十年以上にわたり、熱中症や関連する体調不良で亡くなった方は五百人近くになるそうだ。でも実際はそれよりもっと多いんじゃないかと言う人もいて…。例えば心臓疾患など元々持病があった場合、その死因として熱による影響が見逃されやすかったりするし、事業主側も全部きっちり報告しているとは限らないとか。だから数字だけでは本当のところは分からないこともある。
ちなみに新しい規則案では、雇用主側に対して職場環境の暑さを評価・管理する計画を立てさせたり、水分補給できる場所とか涼めるスペースをちゃんと確保するよう求めているみたい。「熱による被害は他の天候災害より多い」とブルーグリーンアライアンス(労組と環境団体連合)のジェイソン・ウォルシュさんが集会で話していた。でもこの発言も状況次第では異なる解釈になるかもしれないし…。全体的には今後どうなるかまだ分からない部分も残っている感じ。
統計だと過去十年以上にわたり、熱中症や関連する体調不良で亡くなった方は五百人近くになるそうだ。でも実際はそれよりもっと多いんじゃないかと言う人もいて…。例えば心臓疾患など元々持病があった場合、その死因として熱による影響が見逃されやすかったりするし、事業主側も全部きっちり報告しているとは限らないとか。だから数字だけでは本当のところは分からないこともある。
ちなみに新しい規則案では、雇用主側に対して職場環境の暑さを評価・管理する計画を立てさせたり、水分補給できる場所とか涼めるスペースをちゃんと確保するよう求めているみたい。「熱による被害は他の天候災害より多い」とブルーグリーンアライアンス(労組と環境団体連合)のジェイソン・ウォルシュさんが集会で話していた。でもこの発言も状況次第では異なる解釈になるかもしれないし…。全体的には今後どうなるかまだ分からない部分も残っている感じ。

OSHAが初めて提案した暑さ対策基準を巡る全国的な抗議運動
最近になって、なんだか気温がどんどん上がってきたせいか、働く人たちの中で熱中症などで命を落とすケースが二倍近くに増えたという話もあるみたい。去年は記録的な暑さだったようで、今年の夏も平年よりだいぶ暑くなりそうだと気象庁(ナショナルウェザーサービス?)も言っていたとか。ただ、ウォルシュさんや他の支援団体から見ると、トランプ政権がこの「暑さ対策」のルール作りを進める可能性はあまり高くなさそうだと指摘されている。
理由はいくつか挙げられていたようだけど、そのうち五つくらいは特に大きい、とウォルシュ氏は言及していた。例えばトランプ大統領が「新しい規則を一つ作るなら十個以上の古い規則を廃止する」みたいな大統領令を出していたこと、それから4月頃には労働安全衛生研究所(NIOSH)という唯一科学的根拠に基づいて労働者保護を提案できる組織の科学者たちをほぼ全員解雇した出来事もあったらしい。さらに、オーシャ(OSHA)の予算削減案も出ていて、規則を書いたり取り締まったりする人材がかなり減らされる見通しとも聞こえてきている。研修用の資金などもカット対象になっているとか。
実際、一期目でオーシャ検査官の数もかなり削減されたようで、その結果現場調査自体もずっと少なくなったとされているけれど、この流れは今後もしばらく続くかもしれないという声もある。ちなみにオーシャ側からは、この先熱中症関連ルール導入についてどう考えているか回答は特に出ていないみたい。
国全体ではっきりした動きが無い分、ごく一部の州では独自に暑さ対策規定を設け始めた地域も七つほどあるそう。ただ、その多くには例外条項や抜け道が残っていて、実際昨年何人か亡くなったケースでも該当州だった例が複数確認された… まあ細かな事情や状況によって違う部分はあると思うけど、本当に守れる仕組みなのか確信できないところもありそうだ。
理由はいくつか挙げられていたようだけど、そのうち五つくらいは特に大きい、とウォルシュ氏は言及していた。例えばトランプ大統領が「新しい規則を一つ作るなら十個以上の古い規則を廃止する」みたいな大統領令を出していたこと、それから4月頃には労働安全衛生研究所(NIOSH)という唯一科学的根拠に基づいて労働者保護を提案できる組織の科学者たちをほぼ全員解雇した出来事もあったらしい。さらに、オーシャ(OSHA)の予算削減案も出ていて、規則を書いたり取り締まったりする人材がかなり減らされる見通しとも聞こえてきている。研修用の資金などもカット対象になっているとか。
実際、一期目でオーシャ検査官の数もかなり削減されたようで、その結果現場調査自体もずっと少なくなったとされているけれど、この流れは今後もしばらく続くかもしれないという声もある。ちなみにオーシャ側からは、この先熱中症関連ルール導入についてどう考えているか回答は特に出ていないみたい。
国全体ではっきりした動きが無い分、ごく一部の州では独自に暑さ対策規定を設け始めた地域も七つほどあるそう。ただ、その多くには例外条項や抜け道が残っていて、実際昨年何人か亡くなったケースでも該当州だった例が複数確認された… まあ細かな事情や状況によって違う部分はあると思うけど、本当に守れる仕組みなのか確信できないところもありそうだ。
過去10年間で500人近くの労働者が熱中症で死亡したという衝撃的事実
去年の夏ごろ、七十歳を少し超えたチャールズ・リーさんという州の石油・ガス関係の技術者が南カリフォルニアで亡くなった話を聞いたことがある。あの日はシミバレー周辺もかなり暑かったらしく、彼は油漏れか何かの確認中だったそうだ。その一方で、コロラドでも似たような時期に十代後半くらいのカルロス・ペレス・ナヘラさんがゴミ収集作業をしていて、気温が三十度台半ばくらいまで上がっていた日だったとか。めまいを感じてしばらく休んだけど、その後多臓器不全で亡くなったと伝えられている。検死官によれば、極端な暑さや慣れていないことが原因だったみたい。
ところでコロラドには農業従事者向けに熱中症対策の規則はあるけれど、それ以外には適用されないらしい。二十四年になるとまた記録的な猛暑と言われる年になり、フロリダでは知事が自治体による独自の熱対策ルール導入を禁止する法律にサインした、とニュースで見た。それより前にはテキサスでも同じような動きがあったみたいだ。
週明け初日の公聴会では産業界側から「企業ごとの柔軟な対応」を求める声も目立ち、「特定温度以上になった場合必ず決まった対応」という基準案について疑問視する意見も出ていたという。全国独立ビジネス連盟(NFIB)のエリザベス・ミリト氏なんかは「カリフォルニアでは現場から『画一的な基準だと実情に合わず負担が大きい』との声も届いている」と話していたそうだ。木登り作業などの場合、一律休憩タイム設定すると逆に危険にもなる可能性…と指摘していたとも耳にした。「確かに異常高温は無視できない問題だけど、雇用主側も今までそれぞれ工夫して安全維持に努めてきた」といった論調だった気がする。
こういう話題って時々細部まで数字や日にち忘れてしまうけど、大筋としては最近各地で規制強化と現場実態との間で議論が続いている印象しか残っていない。話としてまとまりきらないけど、とりあえずそんな感じだったと思う。
ところでコロラドには農業従事者向けに熱中症対策の規則はあるけれど、それ以外には適用されないらしい。二十四年になるとまた記録的な猛暑と言われる年になり、フロリダでは知事が自治体による独自の熱対策ルール導入を禁止する法律にサインした、とニュースで見た。それより前にはテキサスでも同じような動きがあったみたいだ。
週明け初日の公聴会では産業界側から「企業ごとの柔軟な対応」を求める声も目立ち、「特定温度以上になった場合必ず決まった対応」という基準案について疑問視する意見も出ていたという。全国独立ビジネス連盟(NFIB)のエリザベス・ミリト氏なんかは「カリフォルニアでは現場から『画一的な基準だと実情に合わず負担が大きい』との声も届いている」と話していたそうだ。木登り作業などの場合、一律休憩タイム設定すると逆に危険にもなる可能性…と指摘していたとも耳にした。「確かに異常高温は無視できない問題だけど、雇用主側も今までそれぞれ工夫して安全維持に努めてきた」といった論調だった気がする。
こういう話題って時々細部まで数字や日にち忘れてしまうけど、大筋としては最近各地で規制強化と現場実態との間で議論が続いている印象しか残っていない。話としてまとまりきらないけど、とりあえずそんな感じだったと思う。
トランプ政権が労働者の安全より規制緩和を優先しているという懸念
ミリトさんは、連邦のルールや規制が現場でそこまで厳密に守られているわけではないと話したことがある。ただし、新たなルールを追加することには少し疑問を感じているみたいだ。バラブ氏は以前オバマ政権時代にOSHAの副長官だったそうで、「雇用主が義務的な基準を守るよう促す方法が何か他にないか」とミリトさんへ問いかけていた。すると彼女は「まだまだ研修や連邦機関による支援の余地はありそう」と答えていた気がする。
一方で、フリードマン氏(米国商工会議所で職場政策担当)もまた、画一的な仕組みへの疑念を口にしていたという。何百万人もの雇用主が様々な環境下で働いている国では現実的じゃない…そんなニュアンスだった。「新しい基準案には、仕事の内容や従業員ごとの体質、場所による違いまで考慮されていないようだ」と彼は述べたとか。実際九十度近い気温でも、フェニックスとニューオーリンズ、それからヒューストンやメイン州ポートランドなどでは全然感じ方も条件も異なると言っていたらしい。
今回提案されているルールでは二つほど熱指数―体感温度みたいなもの―が使われており、その出発点になる目安として八十度台前半くらいから雇用者側の対応義務(例えば水分補給や休憩、それから日陰確保など)が求められる流れになっているようだ。科学的根拠を元にした分析では七百人弱ほどの熱中症関連死例(十数報告)を調べ、「ほぼすべて」の死亡事例がその『八十度ライン』より上で起きていたという結果もあったとか。ただ、その基準値についてフリードマン氏は「もしOSHAがどうしても特定ポイントを設けたいなら、一つだけに絞って雇用主側の負担軽減すべき」みたいな意見も持っていて、「しかもその目安値自体もう少し高く設定したほうが現実的じゃないか」と付け加えていたんじゃないかな…湿度込みでも八十度台前半くらいでは大きな危険にならない場合も多い、と彼は言っていたらしい。
全体として、この話題になると細かな条件差や地域性、それぞれ職種ごとの差異なんかにももっと目配り必要という声ばかり耳につく印象だった。
一方で、フリードマン氏(米国商工会議所で職場政策担当)もまた、画一的な仕組みへの疑念を口にしていたという。何百万人もの雇用主が様々な環境下で働いている国では現実的じゃない…そんなニュアンスだった。「新しい基準案には、仕事の内容や従業員ごとの体質、場所による違いまで考慮されていないようだ」と彼は述べたとか。実際九十度近い気温でも、フェニックスとニューオーリンズ、それからヒューストンやメイン州ポートランドなどでは全然感じ方も条件も異なると言っていたらしい。
今回提案されているルールでは二つほど熱指数―体感温度みたいなもの―が使われており、その出発点になる目安として八十度台前半くらいから雇用者側の対応義務(例えば水分補給や休憩、それから日陰確保など)が求められる流れになっているようだ。科学的根拠を元にした分析では七百人弱ほどの熱中症関連死例(十数報告)を調べ、「ほぼすべて」の死亡事例がその『八十度ライン』より上で起きていたという結果もあったとか。ただ、その基準値についてフリードマン氏は「もしOSHAがどうしても特定ポイントを設けたいなら、一つだけに絞って雇用主側の負担軽減すべき」みたいな意見も持っていて、「しかもその目安値自体もう少し高く設定したほうが現実的じゃないか」と付け加えていたんじゃないかな…湿度込みでも八十度台前半くらいでは大きな危険にならない場合も多い、と彼は言っていたらしい。
全体として、この話題になると細かな条件差や地域性、それぞれ職種ごとの差異なんかにももっと目配り必要という声ばかり耳につく印象だった。
州レベルの暑さ対策基準では不十分だと証明された悲劇的な死亡事例
こんな感じの呼びかけ、最近どこかで見たことがある気もする。「あなたの支えで成り立っています」っていう非営利のニュースルームが、確かに今でも広告なしで気候変動についての記事を出してるんだとか。寄付をお願いする声も、時々耳にする。
スコット・シュナイダーという労働安全の専門家、その人は昔北米労働者健康安全基金みたいなところで何かやっていたらしい。彼がフリードマン氏に「八十度くらいまでなら危険じゃないっていう科学的根拠でもあるんですか?」と問いかけていた。どうも、その答えは曖昧だったみたい。「雇用主や組合員から聞く話を元にしている」と返されたそうだ。温度がどこから重要になるのかは、人によって違うようにも思える。
ちょっと前、ワシントンD.C.で集まりがあった。その場でマッキー上院議員(確かマサチューセッツ州選出だったと思う)が、「来年あたり過去最高レベルに暑くなる年になる可能性が高い」と言及していた。ただし、それも断定ではなくて、今年すでに建設現場や農地、それに倉庫や工場、キッチンなど様々な場所で熱中症による死者が出ている、と語っていた。でも、その影響って全員同じようには感じていないみたいだよね──むしろ一部だけ深刻になっている印象も受けた。
途中から話題がどこへ行ったかわからなくなったけど、安全基準とか温度設定とか、この分野では数値よりも現場感覚重視されること、多い気がする。
スコット・シュナイダーという労働安全の専門家、その人は昔北米労働者健康安全基金みたいなところで何かやっていたらしい。彼がフリードマン氏に「八十度くらいまでなら危険じゃないっていう科学的根拠でもあるんですか?」と問いかけていた。どうも、その答えは曖昧だったみたい。「雇用主や組合員から聞く話を元にしている」と返されたそうだ。温度がどこから重要になるのかは、人によって違うようにも思える。
ちょっと前、ワシントンD.C.で集まりがあった。その場でマッキー上院議員(確かマサチューセッツ州選出だったと思う)が、「来年あたり過去最高レベルに暑くなる年になる可能性が高い」と言及していた。ただし、それも断定ではなくて、今年すでに建設現場や農地、それに倉庫や工場、キッチンなど様々な場所で熱中症による死者が出ている、と語っていた。でも、その影響って全員同じようには感じていないみたいだよね──むしろ一部だけ深刻になっている印象も受けた。
途中から話題がどこへ行ったかわからなくなったけど、安全基準とか温度設定とか、この分野では数値よりも現場感覚重視されること、多い気がする。
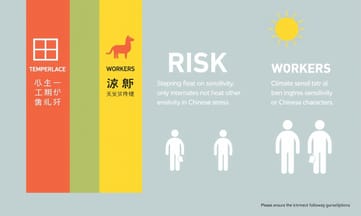
業界団体が「画一的な暑さ基準」に反対する意外な理由とは?
「極端な暑さが与える影響は、どうやら均一じゃないみたいだけど、まあ、本当はどの労働者も仕事に入るとき“ちゃんと無事に家へ帰れる”ってことを疑わずに済む社会がいいよね」と彼は少し考え込むように言った。暑さ対策のルールについて、急ぎの必要性を話していた。誰かが「厳しい規則なんて要らない」と言っていたとしても、「例えば…」と彼は続ける。「水分も取れず救護にもすぐアクセスできないまま炎天下で収穫作業する人。クーラーなしで配達中にふらついて玄関先で倒れたり、運転中気を失いそうになって思わぬ事故につながる配達員。それから日陰も休憩も用意されず熱中症で命を落とす建設現場の人たちとか……」。こういう現場では時々、とても残念な出来事が起きているようだ。規則をゆるめてしまうリスクは決して小さくないと思う、と彼は付け加えた。
OSHAという組織がもし暑さ対応ルールを決めたとして、その施行までには七年近くかかることも珍しくないらしい。それでマルキー議員など何人かの上院議員が「もっと早く・現実的な保護」を目指して動いている、と誰かが噂していた。特に高温環境で働く人について、水分補給や作業時間の制限、それから緊急時の対応体制――まあ、ごく基本的な安全策だけでも守れるようにしたいって趣旨だったみたい。
アリゾナ州ではヒート・コアリションという団体で活動しているジャスミン・モレノ・ドミンゲスさんという女性の名前が挙げられていた。彼女自身はこの集まりでは主催者としてより娘として発言したかったようだ。「毎年夏になる度に父親のことを心配せずにはいられなくなるんです」と語っていた気がする。十年ほど前になるある夏の日――その記憶はいまだ鮮明だと言う。「汗まみれで家へ戻った父の姿は、ほとんど別人みたいでした」とぽつりと言った。でも、そのあと細かい話にはあまり触れなかったと思う。
80度以上の熱指数が「死のライン」とされる科学的根拠に異議を唱える声
なんだか彼の顔色、ちょっと前からずいぶん悪かった。立つのもやっとって感じで、何日間も体調を崩していたらしい。でも、どうも給料付きの休みとか医療サポートみたいなものは見当たらないようだった。それよりも、そもそもそういう事態を防ぐための仕組み自体が…まあ、とにかく無かったと聞いた。
モレノ・ドミンゲスさんが話していたけど、今、彼女のお父さんは遠く離れたアリゾナで命をつなぐ仕事を続けているって。あちらでは気温が七十度近くまで上がることもあるとか?正確な数字は覚えていないけど、とにかく暑さが厳しいようだ。氷水で濡らしたスカーフ首に巻いてたり、冷却ベスト着たりして毎日現場へ向かう姿はもう三十年近く続いているそう。ただ、それでも何かしら対策や制度というものは依然として整っていない様子。
「もっと調査やパネルディスカッションは必要じゃないと思いますよ」と彼女。必要な対策については既に多くの人が知ってることなんじゃないかなあと語った。ただ分からないのは、一体いつ政治家たちが動き始めるのかという点だけ…とも言っていた。
太陽が昇る前から働き始める人々、その家族にもこの極端な暑さというものはじわじわ影響している感じだろう。子供たちは親が無事帰宅するよう祈りながら見送ることも珍しくないみたい。「私たちとしては、本当に議員さんたちに役割を果たしてほしいと願っています」とモレノ・ドミンゲスさん。「父にも安心して帰宅できる機会を与えてください」…そんな呼びかけだった気がする。
モレノ・ドミンゲスさんが話していたけど、今、彼女のお父さんは遠く離れたアリゾナで命をつなぐ仕事を続けているって。あちらでは気温が七十度近くまで上がることもあるとか?正確な数字は覚えていないけど、とにかく暑さが厳しいようだ。氷水で濡らしたスカーフ首に巻いてたり、冷却ベスト着たりして毎日現場へ向かう姿はもう三十年近く続いているそう。ただ、それでも何かしら対策や制度というものは依然として整っていない様子。
「もっと調査やパネルディスカッションは必要じゃないと思いますよ」と彼女。必要な対策については既に多くの人が知ってることなんじゃないかなあと語った。ただ分からないのは、一体いつ政治家たちが動き始めるのかという点だけ…とも言っていた。
太陽が昇る前から働き始める人々、その家族にもこの極端な暑さというものはじわじわ影響している感じだろう。子供たちは親が無事帰宅するよう祈りながら見送ることも珍しくないみたい。「私たちとしては、本当に議員さんたちに役割を果たしてほしいと願っています」とモレノ・ドミンゲスさん。「父にも安心して帰宅できる機会を与えてください」…そんな呼びかけだった気がする。

マサチューセッツ州上院議員が訴える「全ての労働者に安全な帰宅を」という願い
あの話なんだけど、どうも気づいた人がいるかもしれない。Inside Climate Newsっていう組織、ニュースが全部読めるようにしてるんだ。購読料とか、壁みたいなもの(ペイウォール?)で記事を隠したりはしていないらしい。それに広告がほとんど見当たらない。ここは環境や気候についての情報を多くの人に無料で届けているようだね。
たしか非営利団体として活動していて、何年か前からスタートしたみたい。たぶん十数年前だったと思うけど、ふたりの記者さんが始めて、その後しばらくしてから全国規模の賞(ピューリッツァー賞?)を取ったこともある、と聞いたことがある。
それから徐々に規模を広げていって、今では国内でも歴史が比較的長い部類の専門チームになったようだ。ただ、大きな会社というよりは各地に小さな拠点を置いていて、地方ごとのニュースも拾おうとしている雰囲気かな。
面白いのは、自分たちの記事を他の報道機関にも無償で提供しているところ。そういうメディアって実はそんなに多くないかもしれない。他社では環境問題まで手が回らない場合もあるみたいだから、お互い協力する形になることも多そう。
もちろん内容には波があるし、全部完璧とは言えないんだけど、この組織は汚染問題や気候変動について、多面的な切り口で追及する姿勢を大事にしていると感じた人もいるみたいだよ。ただ、それぞれの記事には複雑な事情や背景も絡むので、一概には語れない部分もありそうだね。
たしか非営利団体として活動していて、何年か前からスタートしたみたい。たぶん十数年前だったと思うけど、ふたりの記者さんが始めて、その後しばらくしてから全国規模の賞(ピューリッツァー賞?)を取ったこともある、と聞いたことがある。
それから徐々に規模を広げていって、今では国内でも歴史が比較的長い部類の専門チームになったようだ。ただ、大きな会社というよりは各地に小さな拠点を置いていて、地方ごとのニュースも拾おうとしている雰囲気かな。
面白いのは、自分たちの記事を他の報道機関にも無償で提供しているところ。そういうメディアって実はそんなに多くないかもしれない。他社では環境問題まで手が回らない場合もあるみたいだから、お互い協力する形になることも多そう。
もちろん内容には波があるし、全部完璧とは言えないんだけど、この組織は汚染問題や気候変動について、多面的な切り口で追及する姿勢を大事にしていると感じた人もいるみたいだよ。ただ、それぞれの記事には複雑な事情や背景も絡むので、一概には語れない部分もありそうだね。
アリゾナで働く父を持つ女性が語る「30年間変わらない灼熱地獄」
環境問題に関して不正義が見過ごされること、誤った情報が広まってしまう現象、このあたりはなかなか根深い。私たちはそこに光を当てようとしているみたいです。どうやら寄付による支援で活動の大部分が成り立っているそうで、これまで協力したことのない読者にも、なんとなく一度でも応援してもらえたら嬉しい…そんな感じの呼びかけが続いていました。地球規模で起きている危機、まあ最大級かどうかは状況次第だけど、その取材や情報発信をより多くの人々に届けたいという願いも強く感じますね。税制上も優遇措置があるらしく、小さな金額でも意味がある、と繰り返しています。
カリフォルニア北部にはLiza Grossという記者さんが住んでいるようです。この方、中堅以上のキャリアを持つ科学・環境系ライターとして知られていて、『サイエンスライターズ調査報道ハンドブック』とか『サイエンスライターズ・ハンドブック』にも執筆していたっぽいです(これらは科学系作家団体からアイデア助成金みたいな形で資金提供を受けていたとの話ですが…細部は曖昧)。以前はPLOS Biologyっていうオープンアクセス誌の編集仕事も断続的に担当しつつ、Food & Environment Reporting Networkでは記者として活動してた時期もありました。それ以外にも全米規模の新聞や雑誌――例えばニューヨークタイムズやワシントンポスト、それからDiscoverとかMother Jonesみたいな媒体にも記事を書いてきた経験があります。受賞歴については医療ジャーナリスト団体とか食分野ジャーナリスト組織、それからノーザンカリフォルニア地域のプロフェッショナル団体などから表彰されたことも何度かあったようですが、その辺り詳細までは定かじゃありません。
この人の記事テーマとしては科学一般、自然保護、農業、公衆衛生や環境正義といった話題が中心。ただし「科学知識が営利目的で曲解される」みたいな問題意識を特に重視して取材する傾向が見られます。それぞれの記事内容には多少バラツキあるものの、一貫した視点や姿勢みたいなのは感じ取れる気がしますね。
カリフォルニア北部にはLiza Grossという記者さんが住んでいるようです。この方、中堅以上のキャリアを持つ科学・環境系ライターとして知られていて、『サイエンスライターズ調査報道ハンドブック』とか『サイエンスライターズ・ハンドブック』にも執筆していたっぽいです(これらは科学系作家団体からアイデア助成金みたいな形で資金提供を受けていたとの話ですが…細部は曖昧)。以前はPLOS Biologyっていうオープンアクセス誌の編集仕事も断続的に担当しつつ、Food & Environment Reporting Networkでは記者として活動してた時期もありました。それ以外にも全米規模の新聞や雑誌――例えばニューヨークタイムズやワシントンポスト、それからDiscoverとかMother Jonesみたいな媒体にも記事を書いてきた経験があります。受賞歴については医療ジャーナリスト団体とか食分野ジャーナリスト組織、それからノーザンカリフォルニア地域のプロフェッショナル団体などから表彰されたことも何度かあったようですが、その辺り詳細までは定かじゃありません。
この人の記事テーマとしては科学一般、自然保護、農業、公衆衛生や環境正義といった話題が中心。ただし「科学知識が営利目的で曲解される」みたいな問題意識を特に重視して取材する傾向が見られます。それぞれの記事内容には多少バラツキあるものの、一貫した視点や姿勢みたいなのは感じ取れる気がしますね。



