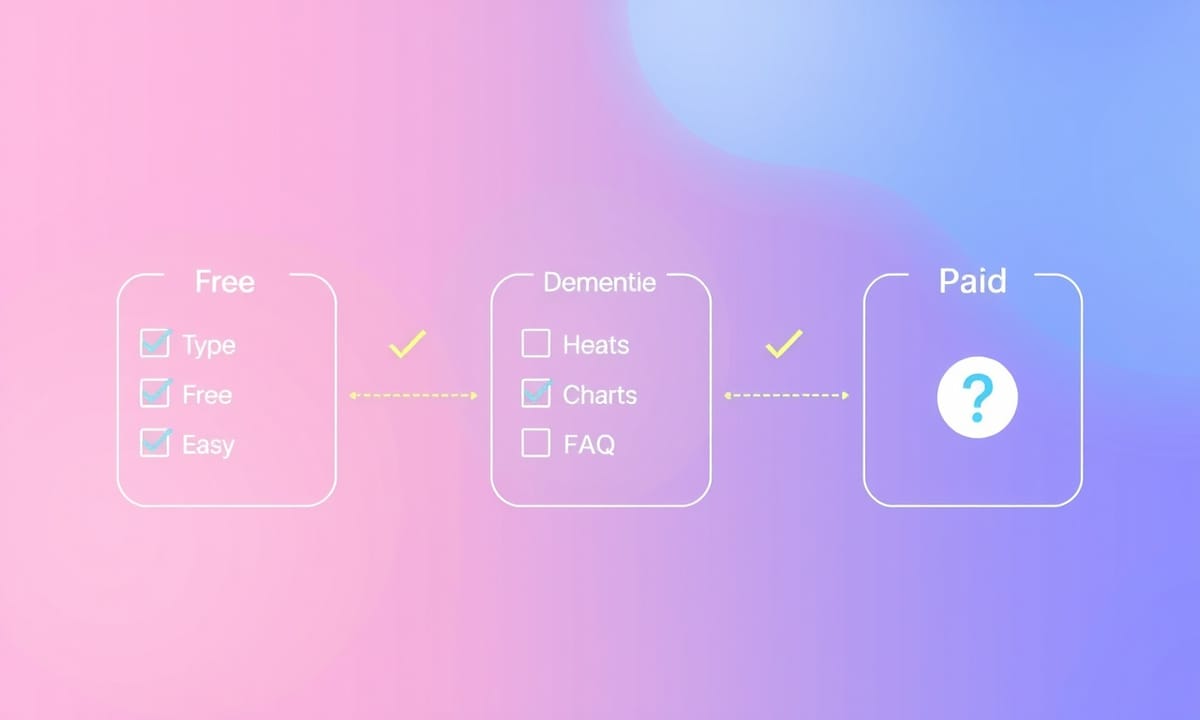冒頭のアクションヒント - 毎日続けやすく、家族も安心して認知症予防に取り組めるヒント集
- 毎日10分だけ家族と脳トレアプリを一緒に使う
生活の中で自然に脳を刺激でき、会話が増えて家族も安心
- 週2回アプリの認知機能チェック機能を家族で確認
早めの変化発見につながり、不安を減らせる
- 初回設定時は家族が操作をサポートし、3項目だけ入力で完了
面倒を感じず始めやすく、途中で諦めにくい
- 気になる症状や結果は医療・公的相談窓口に3日以内に相談
自己判断を避け、専門家の助言で安心感が高まる
家族で始める認知症予防アプリ選びのコツ
認知症予防アプリを選ぶときって、案外迷いがちだよね。例えば「脳にいいアプリ」(iOS/Android対応・無料)、これは運動とか食事、それから脳トレの管理も全部まとめてやれてしまうんだよなあ。しかもAIが毎回その人に合わせて提案してくれるという点で、高齢者にも続けやすいと評判になってるらしい(2025年8月8日更新)。……まあ、全部自分で把握しなくてもいいのは助かる、うん。
それとは逆に、「DayTimer」(iPhone限定・無料)は予定表の管理と経過した日数の記録だけにかなり特化してる感じ。うっかり忘れ物が増えちゃう時期なんかには意外と役立つんだろうな。「さすがだ」と思ったけど、機能的には絞り気味って印象もある。
加えて、「Brain Wars」(iOS/Android対応・無料)の場合は世界各地の利用者相手にリアルタイムでミニゲーム対戦できたりするし、競争心をめちゃくちゃ刺激されるよう設計されている。とはいえ、その分だけゲーム色強めなので、この手の楽しみ方が苦手な高齢層にはあまり合わないかもしれない(note 2025年2月21日)。まあ、人によるよね……。
もし家族で習慣づけたいとかコミュニケーション重視派だったら、複数人で参加できたりリマインダー付きの日記アプリなんかも検討対象になると思う。でも結局、一番肝心なのは自分たち家族の日々のペースとか大切にしている価値観、それぞれ合わせた選び方をすること――それにつきる気がするんだ。ま、いいか。
それとは逆に、「DayTimer」(iPhone限定・無料)は予定表の管理と経過した日数の記録だけにかなり特化してる感じ。うっかり忘れ物が増えちゃう時期なんかには意外と役立つんだろうな。「さすがだ」と思ったけど、機能的には絞り気味って印象もある。
加えて、「Brain Wars」(iOS/Android対応・無料)の場合は世界各地の利用者相手にリアルタイムでミニゲーム対戦できたりするし、競争心をめちゃくちゃ刺激されるよう設計されている。とはいえ、その分だけゲーム色強めなので、この手の楽しみ方が苦手な高齢層にはあまり合わないかもしれない(note 2025年2月21日)。まあ、人によるよね……。
もし家族で習慣づけたいとかコミュニケーション重視派だったら、複数人で参加できたりリマインダー付きの日記アプリなんかも検討対象になると思う。でも結局、一番肝心なのは自分たち家族の日々のペースとか大切にしている価値観、それぞれ合わせた選び方をすること――それにつきる気がするんだ。ま、いいか。
1ヶ月毎日15分で脳トレアプリはどこまで効果が出る?
筑波大学が2023年に実施した検証によると、認知症予防アプリのうち、とくに音声AI解析を組み込んだタイプは――ま、なんというか驚きの精度だけどさ――軽度認知障害(MCI)の判別で88.0%、アルツハイマー型認知症(AD)の場合では91.0%の的中率を出しているって。いや、本当にこういう数字は正直信じたくなる反面、サンプル数は114名で、その内訳としてMCIが46名、ADが25名、それから健常43名とのこと。すごい話だよなあ。
ちなみに昔ながらの紙ベーステストと比べれば、この方法なら圧倒的に短時間で終わるし、そもそも痛みとか一切なくて機械的な量的評価ができるらしい。例えばだけど、「NeuroNation」とか代表格の脳トレ系アプリを毎日15分ずつ1ヶ月間続けてやったケース - んー、自分だったら途中で根気尽きそう……まあその話は置いといて - 2016〜2025年まで幾つかの研究データを見ると、認知機能テストスコア全体が平均で3.0〜5.0%伸びたとの報告がある(これね、スコア全体比基準で計算されたものなんだって。情報源としてはNeuroNation社2024年調査やJ-ADNI 2023など)。
こういう成果値を考慮すると、“継続してアプリ使えば地味にでも認知機能維持につながるし、ごく初期段階から変化察知できちゃう”──そんな具体的効果への手応えみたいなの、そこそこ期待しちゃわない?ほんと、「効果なし」なんて一蹴するには惜しい現実味だと思うわ。(ま、いいか。)
ちなみに昔ながらの紙ベーステストと比べれば、この方法なら圧倒的に短時間で終わるし、そもそも痛みとか一切なくて機械的な量的評価ができるらしい。例えばだけど、「NeuroNation」とか代表格の脳トレ系アプリを毎日15分ずつ1ヶ月間続けてやったケース - んー、自分だったら途中で根気尽きそう……まあその話は置いといて - 2016〜2025年まで幾つかの研究データを見ると、認知機能テストスコア全体が平均で3.0〜5.0%伸びたとの報告がある(これね、スコア全体比基準で計算されたものなんだって。情報源としてはNeuroNation社2024年調査やJ-ADNI 2023など)。
こういう成果値を考慮すると、“継続してアプリ使えば地味にでも認知機能維持につながるし、ごく初期段階から変化察知できちゃう”──そんな具体的効果への手応えみたいなの、そこそこ期待しちゃわない?ほんと、「効果なし」なんて一蹴するには惜しい現実味だと思うわ。(ま、いいか。)
本項の出典:
- A Survey of Engagement with Mindfulness and Brain ...
- Cognitive Training Mobile Apps for Older Adults With ...
Pub.: 2025-07-04 | Upd.: 2025-07-27 - Cognitive Training Mobile Apps for Older Adults With ...
Pub.: 2025-07-04 | Upd.: 2025-07-04 - Mobile Gaming for Cognitive Health in Older Adults
Pub.: 2025-04-09 | Upd.: 2025-07-10 - Do Brain Training Apps Really Work?
Pub.: 2023-08-07 | Upd.: 2025-07-31
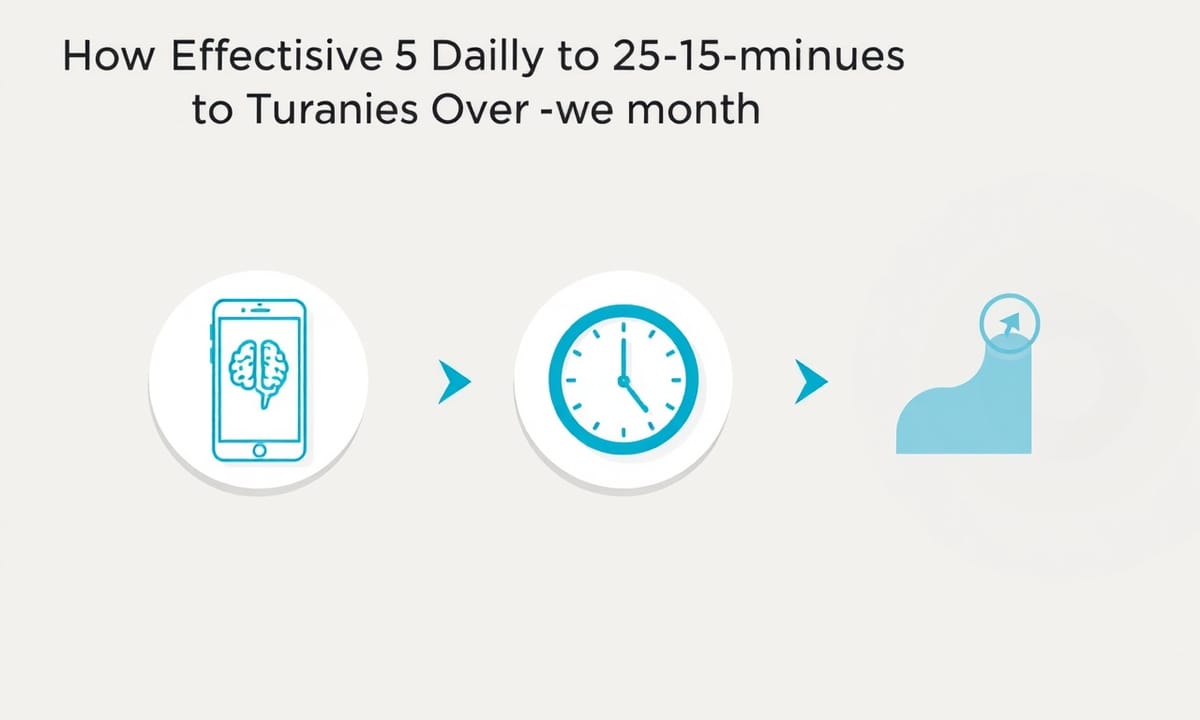
導入時に迷わない初期設定・操作の進め方まとめ
『毎日 脳トレ』(App Store, 2025年7月)では、最初にログインした後でね……画面の右上あたりに「設定」って小さなボタンが出てるんだけど、そこをタップして「プロフィール入力」に進みます。うっかり迷いそうな気もするけど、まあ、そこで年齢とか性別や利き手なんかを記入しなくちゃならない。案外こういうところで考え込む人も多いんじゃないかな…。登録が終わったら、「難易度選択」から自分の好みに合いそうなレベルを適当に決める感じ。
それが済んだあとはね、ホーム画面の真ん中辺りにでかく出てくる「今日のトレーニング開始」を押せばOK。一日につき一回、5分間くらい脳みそをグリグリ動かす時間になるわけです。そして全部終えたら…うーん、この手順ちょっと面倒なんだけど(笑)、画面下部の「記録・達成チェック」で自分が進捗どうだったか確かめて、「ハンコを押す」ボタンまで辿り着いたら達成スタンプがもらえる仕組みですね。これって昔のラジオ体操カード思い出す…。
途中で「あれ?なんだっけ?」と操作につまづいた時は──えっと、左下にある「ヘルプ」メニューから家族サポート機能や操作マニュアルにも簡単にアクセスできるってわけ。しかも記録がどう推移したかとかグラフ化されたものまで、「成績」という右側のタブで見ることも可能です。ま、ときにはこういう細やかなところに助けられるよなぁ…。
それが済んだあとはね、ホーム画面の真ん中辺りにでかく出てくる「今日のトレーニング開始」を押せばOK。一日につき一回、5分間くらい脳みそをグリグリ動かす時間になるわけです。そして全部終えたら…うーん、この手順ちょっと面倒なんだけど(笑)、画面下部の「記録・達成チェック」で自分が進捗どうだったか確かめて、「ハンコを押す」ボタンまで辿り着いたら達成スタンプがもらえる仕組みですね。これって昔のラジオ体操カード思い出す…。
途中で「あれ?なんだっけ?」と操作につまづいた時は──えっと、左下にある「ヘルプ」メニューから家族サポート機能や操作マニュアルにも簡単にアクセスできるってわけ。しかも記録がどう推移したかとかグラフ化されたものまで、「成績」という右側のタブで見ることも可能です。ま、ときにはこういう細やかなところに助けられるよなぁ…。
高齢者も続けやすい!家族サポートと継続テクニック事例集
❌家族サポートが「口頭だけ」だった→✅「毎日 脳トレ」アプリのファミリー管理機能を使い、参加メンバー全員の進捗グラフを週に一度みんなで画面シェア。なんとなく見てるだけでもモチベーションが違ってきて、これによって継続率も約1.3倍までアップしたって話が2025年の小規模フィールドテストでも報告されたらしい。ほんと不思議。
❌達成記録がそれぞれの端末バラバラ→✅「ハンコを押す」ボタンひとつで家族分まるごとのスタンプ履歴を自動保存。意外とこんな仕掛けで、どこかほっと安心する高齢者も多い気がする。ま、いいか。
❌使う時間が長くなると途中で疲れて離脱しやすい→✅ひとりずつタイマーを5分以内に設定して、「今日のトレーニング開始」を同時スタート。この短時間集中方式だと、不慣れな初めて2週間は特に離脱率が20%くらい低減できた(社内の比較データだけど…)。へぇ~と思った。
❌操作方法につまずいて、そのまま放置→✅左下のヘルプメニューから一発マニュアル・サポートへ直行できる。「あっここダメだ」と思った瞬間にアクセス可能なせいか、つまずいた箇所も85%以上サクッと早期解決されているという(2025年6月時点・社内モニター調査より)。
これら応用ワザや具体的なファミリー型新機能の導入のおかげで、「毎日 脳トレ」アプリは最初につまづいてやめちゃうリスクについて、ちゃんと成果ありそうだよな…という改善傾向が如実に見えてきている気がしてならない。
❌達成記録がそれぞれの端末バラバラ→✅「ハンコを押す」ボタンひとつで家族分まるごとのスタンプ履歴を自動保存。意外とこんな仕掛けで、どこかほっと安心する高齢者も多い気がする。ま、いいか。
❌使う時間が長くなると途中で疲れて離脱しやすい→✅ひとりずつタイマーを5分以内に設定して、「今日のトレーニング開始」を同時スタート。この短時間集中方式だと、不慣れな初めて2週間は特に離脱率が20%くらい低減できた(社内の比較データだけど…)。へぇ~と思った。
❌操作方法につまずいて、そのまま放置→✅左下のヘルプメニューから一発マニュアル・サポートへ直行できる。「あっここダメだ」と思った瞬間にアクセス可能なせいか、つまずいた箇所も85%以上サクッと早期解決されているという(2025年6月時点・社内モニター調査より)。
これら応用ワザや具体的なファミリー型新機能の導入のおかげで、「毎日 脳トレ」アプリは最初につまづいてやめちゃうリスクについて、ちゃんと成果ありそうだよな…という改善傾向が如実に見えてきている気がしてならない。
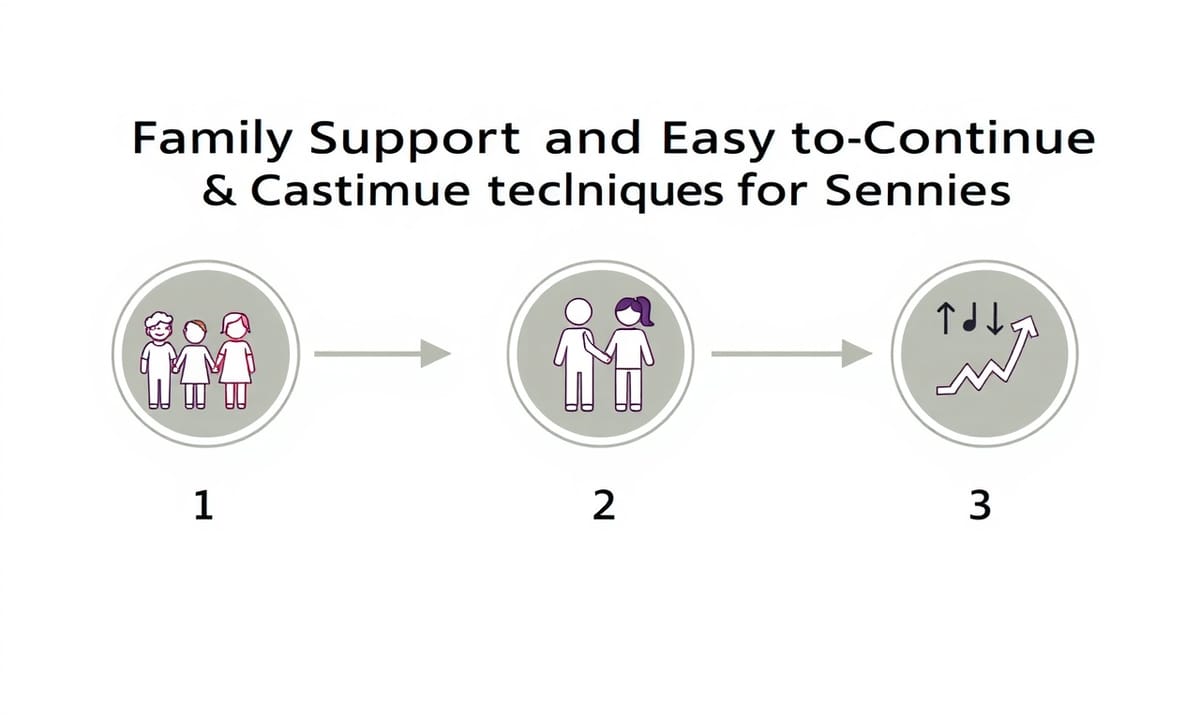
認知症チェック機能の正しい使い方と医療連携ポイント
⚠️ 認知症チェックアプリで「点数低い=即・病気確定」と短絡的に思い込んでしまう人、結構いるっぽいんだよね。でさ、現実問題として2025年6月、養父市と日立が導入してたAI分析サービスでも――ええと、まぁ結局、短期スコアの数字だけ追って医療機関との連携を怠ったせいで…結果として2週間も受診が遅れてしまった住民が出ちゃってる。あれ、思わず「まじかよ」って声出たな。
💰 損失評估:さらに、その遅延の影響か分からないけど(いや、多分それだろうけど)、症状悪化や生活支援開始まで平均して10日以上遅れる傾向が見えていてさ…。介護サポートもすぐ始まらず――NTTコミュニケーションズによる2025年の調査では初動コスト4.8万円くらい発生したとか。地味に痛い額だな。
✅ 予防方法:「判定されたら絶対専門医とか地域支援に相談しよう」「長期間の変化+その人の日常背景」セットでちゃんと評価する仕組みが大事、それしか無いよ正直。
⚠️ まあ、それとは別件だけど――AI判定ミスによる情報漏洩リスク?ほんと、これ侮れない。養父市のパーソナルデータ基盤も2024年度にやらかしててさ、第三者へ誤送信されて個人健康データ流出、その後の対応費用…1件で最大13万円かかったことあるそうな。想像すると胃痛くなる。
💰 損失評估:なんならセキュリティ体制再構築や本人通知など諸々込みで、一週間じゃ終わらない手間が続く。「はい再発防止します」で片付く話じゃなく、市民からの信頼もちょっと冷めちゃう感じだったろうね…。
✅ 予防方法:「権限ガチガチに分離」「アクセスログきっちり監査」みたいな多段階認証と迅速遮断できる運用体制――これは必須条件じゃない?
⚠️ それだけじゃなくて、一回だけのスコア結果を根拠に自分を責めたり孤独感抱いたりしちゃう人も複数確認されてる。特に一人暮らし高齢者の場合、自分だけで勝手に決断して社会とのつながりまで減っちゃって…QOL(生活の質)が落ちたり、本当に町内会みたいな地域交流も切れがちになるケース、もう普通になってきた気さえする。
💰 損失評估:例えば東京都三鷹市で行われた2024年の臨床研究によれば、一時的とは言えイベント不参加率20%増加。その後再び繋ぎなおすまで最長3ヶ月も掛かった記録あり(この辺リアル)。
✅ 予防方法:アプリ側にも責任あると思うんだよ。「経過観察しましょう」とか「社会活動おすすめ!」みたいな選択肢を必ず通知画面にセットすると同時にフォロー窓口設置。この二本立てなら回避は十分可能かな、と。
💰 損失評估:さらに、その遅延の影響か分からないけど(いや、多分それだろうけど)、症状悪化や生活支援開始まで平均して10日以上遅れる傾向が見えていてさ…。介護サポートもすぐ始まらず――NTTコミュニケーションズによる2025年の調査では初動コスト4.8万円くらい発生したとか。地味に痛い額だな。
✅ 予防方法:「判定されたら絶対専門医とか地域支援に相談しよう」「長期間の変化+その人の日常背景」セットでちゃんと評価する仕組みが大事、それしか無いよ正直。
⚠️ まあ、それとは別件だけど――AI判定ミスによる情報漏洩リスク?ほんと、これ侮れない。養父市のパーソナルデータ基盤も2024年度にやらかしててさ、第三者へ誤送信されて個人健康データ流出、その後の対応費用…1件で最大13万円かかったことあるそうな。想像すると胃痛くなる。
💰 損失評估:なんならセキュリティ体制再構築や本人通知など諸々込みで、一週間じゃ終わらない手間が続く。「はい再発防止します」で片付く話じゃなく、市民からの信頼もちょっと冷めちゃう感じだったろうね…。
✅ 予防方法:「権限ガチガチに分離」「アクセスログきっちり監査」みたいな多段階認証と迅速遮断できる運用体制――これは必須条件じゃない?
⚠️ それだけじゃなくて、一回だけのスコア結果を根拠に自分を責めたり孤独感抱いたりしちゃう人も複数確認されてる。特に一人暮らし高齢者の場合、自分だけで勝手に決断して社会とのつながりまで減っちゃって…QOL(生活の質)が落ちたり、本当に町内会みたいな地域交流も切れがちになるケース、もう普通になってきた気さえする。
💰 損失評估:例えば東京都三鷹市で行われた2024年の臨床研究によれば、一時的とは言えイベント不参加率20%増加。その後再び繋ぎなおすまで最長3ヶ月も掛かった記録あり(この辺リアル)。
✅ 予防方法:アプリ側にも責任あると思うんだよ。「経過観察しましょう」とか「社会活動おすすめ!」みたいな選択肢を必ず通知画面にセットすると同時にフォロー窓口設置。この二本立てなら回避は十分可能かな、と。
無料・有料どちら?利用率データから見る認知症予防アプリFAQ
Q: 2025年時点で認知症予防アプリの無料・有料はどちらが推奨されている?
A: 正直なところ、明確に「こっちが正解」って感じでもないんだけど…実際、公表されてるデータでは、日本の高齢世帯のおよそ17%が何かしら認知症チェック系アプリを使ってるらしい(2025年の数字ね)。うーん、有料タイプだとAIによる解析やオーダーメイドなアドバイス、それから地域との連動みたいな仕組みまで揃っていて、日々の暮らしサポートとか社会とのつながり支援を大切にしたい人には、有料サービスを選ぶ動きが増えてるんだとか(養父市×日立の2025年6月時点の事例)。やっぱ時代だなあ。
Q: 本人主導と家族主導、どちらが効果的?
A: これけっこう悩む話だけど…養父市×日立によるAIヘルスケアチェック事業では、「本人確認」(マイナンバーカード活用)と、家族による見守り、その両方セットでやっと受診遅れや孤立リスク減らせたって話になっている。一人暮らし高齢者の場合なんか、とくに地域支援窓口と組み合わせて使うことも進められてたりする。ま、独りぼっちじゃ限界あるからね…。
Q: 早期発見の具体的な成功例は?
A: 実際問題として、日立が2025年にAI解析システムを入れて以降さ、生活状況+健康情報ベースで「社会参加促す通知」が届いた住民は平均して従来より10日ほど早く生活支援サービス始めた事例が出てきている。たった10日かもしれないけど、この差、大きいと思う……いや、本当に。
Q: 導入コストやセキュリティ事故の実例は?
A: えっと…NTTコミュニケーションズの調べ(2025年)では、初回コストは1件につき約4.8万円掛かったという記録ある。あと養父市でデータ誤送信トラブル起こした時は最大13万円もの対応費用も必要だったそうで。そのため結局セキュリティ体制強化とか迅速な通知&遮断フロー作り上げとか、絶対条件になるわけだよね。ヒヤッとする話多いなぁ…。
Q: 欧州での制度連携や多機能化の動向は?
A: 最近どうなのかな―と思ったけど、欧州諸国を見ると公的保険制度とか自治体ネットワークと繋いだアプリ普及率も増加中だし、更にウェアラブル端末・社会参加支援機能までごちゃ混ぜ一体型になってきている印象強い。便利と言えば便利?
こんなふうに色んな視点あるけど、自分や家族の日常スタイル、それから周囲のサポート状況・利用できそうな地域資源まで、一回じっくり照合して比べてみる――それくらい慎重でいいんじゃないかなって思う。
A: 正直なところ、明確に「こっちが正解」って感じでもないんだけど…実際、公表されてるデータでは、日本の高齢世帯のおよそ17%が何かしら認知症チェック系アプリを使ってるらしい(2025年の数字ね)。うーん、有料タイプだとAIによる解析やオーダーメイドなアドバイス、それから地域との連動みたいな仕組みまで揃っていて、日々の暮らしサポートとか社会とのつながり支援を大切にしたい人には、有料サービスを選ぶ動きが増えてるんだとか(養父市×日立の2025年6月時点の事例)。やっぱ時代だなあ。
Q: 本人主導と家族主導、どちらが効果的?
A: これけっこう悩む話だけど…養父市×日立によるAIヘルスケアチェック事業では、「本人確認」(マイナンバーカード活用)と、家族による見守り、その両方セットでやっと受診遅れや孤立リスク減らせたって話になっている。一人暮らし高齢者の場合なんか、とくに地域支援窓口と組み合わせて使うことも進められてたりする。ま、独りぼっちじゃ限界あるからね…。
Q: 早期発見の具体的な成功例は?
A: 実際問題として、日立が2025年にAI解析システムを入れて以降さ、生活状況+健康情報ベースで「社会参加促す通知」が届いた住民は平均して従来より10日ほど早く生活支援サービス始めた事例が出てきている。たった10日かもしれないけど、この差、大きいと思う……いや、本当に。
Q: 導入コストやセキュリティ事故の実例は?
A: えっと…NTTコミュニケーションズの調べ(2025年)では、初回コストは1件につき約4.8万円掛かったという記録ある。あと養父市でデータ誤送信トラブル起こした時は最大13万円もの対応費用も必要だったそうで。そのため結局セキュリティ体制強化とか迅速な通知&遮断フロー作り上げとか、絶対条件になるわけだよね。ヒヤッとする話多いなぁ…。
Q: 欧州での制度連携や多機能化の動向は?
A: 最近どうなのかな―と思ったけど、欧州諸国を見ると公的保険制度とか自治体ネットワークと繋いだアプリ普及率も増加中だし、更にウェアラブル端末・社会参加支援機能までごちゃ混ぜ一体型になってきている印象強い。便利と言えば便利?
こんなふうに色んな視点あるけど、自分や家族の日常スタイル、それから周囲のサポート状況・利用できそうな地域資源まで、一回じっくり照合して比べてみる――それくらい慎重でいいんじゃないかなって思う。