冒頭のアクションヒント - 経済的困難に直面する子どもの心と未来を守るための行動指針
- 月1回以上、地域の無料学習支援や居場所活動を調べて参加先候補を3つリストアップする
孤立感や経験格差が減り、自己肯定感が高まりやすくなるから
- 年に1度は自治体の就学援助制度や各種相談窓口について専門家・公式機関へ確認・相談
教育費・生活費など負担軽減策を知ることで将来への希望喪失リスクが下がる
- 週2回以上、家庭で子どもと10分間“気持ち”について言葉で話す時間をつくる
経済的困難によって低下しやすい心の健康や親子信頼感の維持に役立つ
- 毎月一度、支援団体サイト等で新しい奨学金情報など公式発表内容をチェックして記録
進学機会損失予防になり、生涯所得格差縮小にも寄与しうる
お金という名の幼なじみとの思い出
お金との付き合いは、たぶん昔からあったような気がする。いや、本当は「ずっと」って言えるほどじゃなくて、時々ふらっと現れて、それからまたいなくなるような…そんな幼馴染みたいな存在。小さいころ、お金が目の前に現れると、とても嬉しかった記憶がある。たぶん七歳か八歳くらいだったかな、そのときのコインは妙に光って見えて、手のひらで転がすだけでも何だか秘密を握ってる気分になったことも。鼓動と同じリズムでその冷たい感触を感じていたような…いや、ちょっと大げさかもしれないけど。
「今日はどうする?」なんて彼女——まあ、お金だけど——が囁く時期もあった気がする。その声には少し悪戯っぽさも混じっていて、自分もそれにつられて胸が高鳴ったりした。夏休みの日差しや校庭の匂いまで思い出せそうだ。学校も親も関係ない午後、どこまでも広がる時間……今考えれば、数十円ぽっちでも一日中幸せだったと思う。「駄菓子屋行こう」とか、「アイスクリームトラック待とうよ」とか、本当に些細なことで夢中になれた。
昔は一緒にいるだけで十分だった。でも最近、その子(お金)の口紅はすっかり色褪せてしまったみたい。何度目かわからないけど、不安になってまた呼び出してしまう——今日なんて珍しく返事があって、会う約束までできた。不思議と懐かしさより少し戸惑いの方を強く感じるけど…。こんな話、大人になると誰でも一度くらい経験するものなのかなぁ、とぼんやり思う時もある。
「今日はどうする?」なんて彼女——まあ、お金だけど——が囁く時期もあった気がする。その声には少し悪戯っぽさも混じっていて、自分もそれにつられて胸が高鳴ったりした。夏休みの日差しや校庭の匂いまで思い出せそうだ。学校も親も関係ない午後、どこまでも広がる時間……今考えれば、数十円ぽっちでも一日中幸せだったと思う。「駄菓子屋行こう」とか、「アイスクリームトラック待とうよ」とか、本当に些細なことで夢中になれた。
昔は一緒にいるだけで十分だった。でも最近、その子(お金)の口紅はすっかり色褪せてしまったみたい。何度目かわからないけど、不安になってまた呼び出してしまう——今日なんて珍しく返事があって、会う約束までできた。不思議と懐かしさより少し戸惑いの方を強く感じるけど…。こんな話、大人になると誰でも一度くらい経験するものなのかなぁ、とぼんやり思う時もある。
輝いていたあの頃のお金と私
あのポスターの彼女、まあ、新しい時代っぽいやつだとしたら、たぶん見分けがつかない。金粉とか、変に明るい笑顔が映えてて、「頑張って微笑めばすぐ来てくれる」なんて言う人もいるけど、あれはちょっと違う気がする。
ずっと昔の話になるけど、あんな豊かさのおまじないや引き寄せみたいなのが流行る前――そう、まだ街灯がちらつく通りで初めて送り出された少女だったころまで戻らなきゃいけない。
最近は買い物ポイントだの何とかスタートアップ風味だので着飾らせたりしてるし、メールボックスにもアメみたいに吊るされてる。「事前承認済」「利息ゼロ」とか「今すぐ申し込め」みたいな文句で誘われて…。
証券会社?資本?コイン?名前も七回くらい変えられて、その度に少し派手になっただけ。でも本質はそんなに変わってない。
毎回景気がぐるぐる回っても、彼女は道を歩き続けている。最近はデジタル化されちゃって、姿を隠しやすくなった分だけ触れづらくなったような感じかな。でも結局いつも同じゲームなんだよね。多分助けてもらえると思って彼女を追いかけ続ける。そして彼女自身も、それが無理だと知りながら走り続けているようで。
会う約束の日――時間よりかなり遅れて現れた。その時点ですでに予想通りだったから、不思議でも何でもなくて。ただ髪型だけ妙に整いすぎで、「疲れた」と口では言う割にはヒールの音だけやたら響いていた気がする。
向こう側の席に滑り込む様子は、大したことなかったみたいな雰囲気。こっちとしてはその数十分間(正確には四十数分くらい?曖昧だけど)ずっと何話そうか頭の中で繰り返していたというのに。
「来ただろ?」とぼそっと言われた。その目線はこちらをちゃんと見ずに、もうテーブル上の砂糖袋へ手を伸ばしていた。
「真夜中になって呼び出しかけてくる人なんて結構多いんだからさ」そんなふうにも言われた…ような記憶。
返事はできなかった。ただイライラ半分、ほっとした気持ち半分、とっちらかった感情で彼女を見つめ返していた。それが私たちらしい関係性だったとも思える。
ずっと昔の話になるけど、あんな豊かさのおまじないや引き寄せみたいなのが流行る前――そう、まだ街灯がちらつく通りで初めて送り出された少女だったころまで戻らなきゃいけない。
最近は買い物ポイントだの何とかスタートアップ風味だので着飾らせたりしてるし、メールボックスにもアメみたいに吊るされてる。「事前承認済」「利息ゼロ」とか「今すぐ申し込め」みたいな文句で誘われて…。
証券会社?資本?コイン?名前も七回くらい変えられて、その度に少し派手になっただけ。でも本質はそんなに変わってない。
毎回景気がぐるぐる回っても、彼女は道を歩き続けている。最近はデジタル化されちゃって、姿を隠しやすくなった分だけ触れづらくなったような感じかな。でも結局いつも同じゲームなんだよね。多分助けてもらえると思って彼女を追いかけ続ける。そして彼女自身も、それが無理だと知りながら走り続けているようで。
会う約束の日――時間よりかなり遅れて現れた。その時点ですでに予想通りだったから、不思議でも何でもなくて。ただ髪型だけ妙に整いすぎで、「疲れた」と口では言う割にはヒールの音だけやたら響いていた気がする。
向こう側の席に滑り込む様子は、大したことなかったみたいな雰囲気。こっちとしてはその数十分間(正確には四十数分くらい?曖昧だけど)ずっと何話そうか頭の中で繰り返していたというのに。
「来ただろ?」とぼそっと言われた。その目線はこちらをちゃんと見ずに、もうテーブル上の砂糖袋へ手を伸ばしていた。
「真夜中になって呼び出しかけてくる人なんて結構多いんだからさ」そんなふうにも言われた…ような記憶。
返事はできなかった。ただイライラ半分、ほっとした気持ち半分、とっちらかった感情で彼女を見つめ返していた。それが私たちらしい関係性だったとも思える。
Comparison Table:
| テーマ | 内容 |
|---|---|
| 愛と存在価値 | 自分が必要とされることで、存在価値を感じることの重要性。 |
| 社会的圧力 | 他者からの期待や約束事に縛られ、自分の意志が奪われる状況。 |
| 感情の複雑さ | 他人に頼りたいという欲求と、自身を恨む矛盾した感情。 |
| 逃げ場の喪失 | 心の奥で休みたいと思いつつも、現実では簡単にはいかない苦悩。 |
| 希望と絶望 | 未来への微かな希望と、それに伴う不安定な感情。 |

深夜のパニック電話で再会した変わり果てた姿
バラバラに崩れそうな瞬間、あの子はやたらと待たせることが多くて、テーブルを挟んで黙ったまま座っていた。互いにイライラしてるのは見え見えなのに、何事もないふりをするんだ。今では彼女のことを「マネー」って呼ぶようになったけど、昔はもっと柔らかくて明るすぎるくらいの名だった気がする。けど、その名前…もう誰も使わないし、彼女自身も口に出さなくなった。「その名前を言おうとすると、喉の奥で泣きたい気持ちがつかえて動かなくなる」と前に小声で話していたこともある。
まだ子供っぽかった時分だろうか――周りから特別扱いされて、大勢が並んでまで彼女に会いたがった時期が確かにあった。それがいつしか、「ありがたみ」よりも「使い道」を求められる存在へと変わってしまった。誰も彼女を奇跡みたいには見なくなって、ただの便利な道具みたいな顔つきで近寄ってきたようだ。
ヒールなんて履かされた最初の日は、本当に大人でもない年頃だったと思う。背筋を伸ばして無理やり笑って、ご機嫌取りながら歩いて……でも足先はずっと痛かったとか。それだけじゃない、安全じゃない感じというか…体のどこかできっと危険信号みたいなの鳴ってたんだろう。
「才能があるね」と褒められて、それだけで嬉しくなっちゃう子供心。そんなものだよね。褒め言葉なんて布団みたいにくっついて離れなくて、中身に針でも入っているとは思わなかった。でも現実はちょっと違う。「ただそこに居ればいい」「君のお陰で全部スムーズになる」「歯車が回るのは君のおかげ」。そんなセリフばっかり聞こえてきて…
契約書とか封筒とかタンク? 色んなところへ押し込まれて、お守り代わりみたいな感じで大人たち――特に男たちは手早く触れて次々渡していくんだけど、その視線は全然合わない。その場の空気というか、汗と作戦会議っぽい匂い漂う部屋にも連れて行かれたりして…。呼吸すら浅くなるほど緊張したまま、それでも服直したり微笑む努力は続けてしまう。本当によく覚えてはいないけど、多分七十回くらい同じこと繰り返された気がする。
ところどころ記憶曖昧だけど、ときどき来て短く話す時には「あれは私が皆を楽させる力だった」とぼそっと呟いたこともある。信じ込むしか選択肢なかったんじゃないかなぁ…。
まだ子供っぽかった時分だろうか――周りから特別扱いされて、大勢が並んでまで彼女に会いたがった時期が確かにあった。それがいつしか、「ありがたみ」よりも「使い道」を求められる存在へと変わってしまった。誰も彼女を奇跡みたいには見なくなって、ただの便利な道具みたいな顔つきで近寄ってきたようだ。
ヒールなんて履かされた最初の日は、本当に大人でもない年頃だったと思う。背筋を伸ばして無理やり笑って、ご機嫌取りながら歩いて……でも足先はずっと痛かったとか。それだけじゃない、安全じゃない感じというか…体のどこかできっと危険信号みたいなの鳴ってたんだろう。
「才能があるね」と褒められて、それだけで嬉しくなっちゃう子供心。そんなものだよね。褒め言葉なんて布団みたいにくっついて離れなくて、中身に針でも入っているとは思わなかった。でも現実はちょっと違う。「ただそこに居ればいい」「君のお陰で全部スムーズになる」「歯車が回るのは君のおかげ」。そんなセリフばっかり聞こえてきて…
契約書とか封筒とかタンク? 色んなところへ押し込まれて、お守り代わりみたいな感じで大人たち――特に男たちは手早く触れて次々渡していくんだけど、その視線は全然合わない。その場の空気というか、汗と作戦会議っぽい匂い漂う部屋にも連れて行かれたりして…。呼吸すら浅くなるほど緊張したまま、それでも服直したり微笑む努力は続けてしまう。本当によく覚えてはいないけど、多分七十回くらい同じこと繰り返された気がする。
ところどころ記憶曖昧だけど、ときどき来て短く話す時には「あれは私が皆を楽させる力だった」とぼそっと呟いたこともある。信じ込むしか選択肢なかったんじゃないかなぁ…。
誰も知らないお金の本当の名前と傷痕
「もう少し微笑んで」と、誰かがそっと言う。将軍たちが疲れて見える時だけ、そんな声が聞こえた気がする。彼らは、自分たちの前に立つ者がそこにいることを喜んでいると思いたかったのだろうか。だから、彼女は口角を上げる。でも、お腹の奥は何か握りしめるように重くなっていく。
よくわからないけど、たぶんあの人たちは彼女をどこかへ押しやっていた。震えている手とか、欲深そうな目とか――そういうものに囲まれながら。質問なんてしなかった。「この瞬間を壊したくない」、そんな思いだったような気もする。
もしもっと速く動けば、大声で叱られることも減った…いや、本当に減ったかどうかは曖昧だけど。ただ、完璧になればきっと何か変わると期待していたようだ。いつからだろう、高級マンションばかりに運ばれるようになったのは。その床は眩しいほどピカピカしていて、不自然な冷房の風が流れていた。十軒以上もの家族と過ごした日々――温もりみたいなのを思い出す余裕もなくなるほど。
昔は、人々が小さな棚や祭壇に自分を飾って、そっと感謝の言葉をささやいてくれたり、掌で大事そうに包み込んでくれたりしたこともあった。でも最近では、その人たちとすれ違うだけ。それも、道端で引きずり出されている時だったりして、その名前だけが頭に残る感じ。
銀行員? 確か「見ない方がいい」と言っていたっけ。不動産屋さんとか地主さんとか、「止まるな」みたいなことしか言わない印象。「もう君はこちら側だ」とまで断定された記憶もうっすらある。「ただ進め」と言われても、それ以外選択肢など見当たらない。
『助けたい』なんて言葉、自分でも何となく違和感ある。本当はこんな形じゃない、と心の中では思っていた。でも、それを口に出すタイミングなんてどこにも転がっていない気がする。ただ一つ覚えているのは、ほんの短い時間でも立ち止まれば――その場全体の空気や景色まで変わりそうだということだけだった。
よくわからないけど、たぶんあの人たちは彼女をどこかへ押しやっていた。震えている手とか、欲深そうな目とか――そういうものに囲まれながら。質問なんてしなかった。「この瞬間を壊したくない」、そんな思いだったような気もする。
もしもっと速く動けば、大声で叱られることも減った…いや、本当に減ったかどうかは曖昧だけど。ただ、完璧になればきっと何か変わると期待していたようだ。いつからだろう、高級マンションばかりに運ばれるようになったのは。その床は眩しいほどピカピカしていて、不自然な冷房の風が流れていた。十軒以上もの家族と過ごした日々――温もりみたいなのを思い出す余裕もなくなるほど。
昔は、人々が小さな棚や祭壇に自分を飾って、そっと感謝の言葉をささやいてくれたり、掌で大事そうに包み込んでくれたりしたこともあった。でも最近では、その人たちとすれ違うだけ。それも、道端で引きずり出されている時だったりして、その名前だけが頭に残る感じ。
銀行員? 確か「見ない方がいい」と言っていたっけ。不動産屋さんとか地主さんとか、「止まるな」みたいなことしか言わない印象。「もう君はこちら側だ」とまで断定された記憶もうっすらある。「ただ進め」と言われても、それ以外選択肢など見当たらない。
『助けたい』なんて言葉、自分でも何となく違和感ある。本当はこんな形じゃない、と心の中では思っていた。でも、それを口に出すタイミングなんてどこにも転がっていない気がする。ただ一つ覚えているのは、ほんの短い時間でも立ち止まれば――その場全体の空気や景色まで変わりそうだということだけだった。

戦争部屋で震えながら笑った少女時代
目がちょっと硬くなったような気がした。カフェの空気も、ほんの少し冷え込んだみたいで。彼女はまた早口になり、前よりもっと急いで話すことを自分に言い聞かせていた——たぶん愛情だと信じたかったのかもしれない。うまくやれば、役立ってさえいれば、黙って静かにしてさえいれば、そのうち違和感も消えてしまう…そんな風に。
「全部が悪かったわけじゃない」と彼女はぽつりと言った。でもそれは私に向けてというより、自分自身への呟きのようだった。本当にそう思いたかったのかも。コーヒーカップを手に取り、長めのひと口。店内の明かりが顔の隅っこ——疲れた線——そこだけ照らした。
私はまだ彼女に頼る自分が嫌だった。結局、夜中なのに電話してしまったから。不安で崩れて、「もう一度だけ助けて」と縋ってしまった。そのことには二人とも何も触れずにいて、カフェでは他のお客さんがぼそぼそ話していて。それなのにどこかで「彼女はまだ私になんとかしてくれる」みたいな甘えを捨て切れていなかった。
彼女はテーブルの下で手を重ね、小さく動きもしないまま。それでも誰にも指示されなくても座っていた。「助けてるつもりだったんだよね」と、遠くを見る目で言葉を落とした。
途中、「奨学金とか…救済金? あと家賃とか光熱費……七十回くらい支払い延ばせたかな」「時々セラピーにも使えて…」なんて数えるような声だったけど、それぞれ言葉につまずきながら並べていた。本当は良いこととして挙げたかったのだろう。ただ、その声にはほころびみたいな揺れがあって。
少しだけ記憶違いかもしれない。でもその日、目の前で見た手元や小さな仕草まで妙にはっきり覚えている気がする。
強制立ち退きの現場で見た冷たい床
「これが愛だったのかな…自分が必要とされること、それだけで存在価値があると思った。」そんなふうに、彼女はほとんど口にしなかったけど、目を合わせようとしないその仕草から伝わってきた。手助けしたくても、相手次第でしかどうにもできないみたいで。子どもの頃にはあったはずの、小さなコイン一枚で世界が広がるあの不思議さとか、嬉しさ――そういうものは今やすっかり、よくわからないルールの下に埋もれてしまっている。だれもその約束ごとに納得していない気もする。
山を動かすなんて言われたりするけど、ほんとうは彼女自身、その力の間に挟まれているようにも見えた。誰かが優しく名前を呼べば寄って来る、と噂されても、人々の財布の片隅で丸まって汗ばんだ紙幣になっているところなんてほとんど知られていないと思う。恐怖で湿った小銭入れとか、体を小さく縮めている姿だとか。
背中が軋むような音――「悪の根源」みたいな呼ばれ方をされて、そのあとまたこっそりポケットへ戻される瞬間。その時々で違う約束事を呟かれることもあった。でも守られるとは限らなくて。
ブラジャーに隠されたり、拳に丸め込まれたり……舌下へ忍ばせる人もいたかな。誰かに渡されたり奪われたりすることが、一日に何度も起きていた印象だけど、本当の回数はもう覚えていない。指示ひとつで踊らされて、明かりが点いた途端消えることも珍しくなくて。
時間や静寂や薬や檻、それから砂糖菓子みたいな幸せ―色んなものを買わせられていた。ただ黙っていればいいと言われながら。微笑む練習もたぶんしていたはず。
どう動けばいいか教え込まれて、その通り振舞う。でも「支配者」みたいに扱われつつ、本心では愛されてはいない雰囲気だったかな。トロフィーみたいに人前では誇示されたあとでも、不意に大事そうに鍵付き引き出しへしまいこまれる場面、多かった印象。
デジタル化だとか分散管理とか話題にはなるけれど、大抵の場合ちゃんと記録され追跡され続けている気配だけ残る。それだけじゃなく、ときおり意味不明な規則や慣習によって形を変えながら押し流され――まあ、全部確実とは言えないけれど、おおよそこんな風景だった気がする。
山を動かすなんて言われたりするけど、ほんとうは彼女自身、その力の間に挟まれているようにも見えた。誰かが優しく名前を呼べば寄って来る、と噂されても、人々の財布の片隅で丸まって汗ばんだ紙幣になっているところなんてほとんど知られていないと思う。恐怖で湿った小銭入れとか、体を小さく縮めている姿だとか。
背中が軋むような音――「悪の根源」みたいな呼ばれ方をされて、そのあとまたこっそりポケットへ戻される瞬間。その時々で違う約束事を呟かれることもあった。でも守られるとは限らなくて。
ブラジャーに隠されたり、拳に丸め込まれたり……舌下へ忍ばせる人もいたかな。誰かに渡されたり奪われたりすることが、一日に何度も起きていた印象だけど、本当の回数はもう覚えていない。指示ひとつで踊らされて、明かりが点いた途端消えることも珍しくなくて。
時間や静寂や薬や檻、それから砂糖菓子みたいな幸せ―色んなものを買わせられていた。ただ黙っていればいいと言われながら。微笑む練習もたぶんしていたはず。
どう動けばいいか教え込まれて、その通り振舞う。でも「支配者」みたいに扱われつつ、本心では愛されてはいない雰囲気だったかな。トロフィーみたいに人前では誇示されたあとでも、不意に大事そうに鍵付き引き出しへしまいこまれる場面、多かった印象。
デジタル化だとか分散管理とか話題にはなるけれど、大抵の場合ちゃんと記録され追跡され続けている気配だけ残る。それだけじゃなく、ときおり意味不明な規則や慣習によって形を変えながら押し流され――まあ、全部確実とは言えないけれど、おおよそこんな風景だった気がする。

「助けてるつもりだった」と呟くコーヒーブレイク
取引があるたびに、どこかで小さな傷跡が増えていく。何度も嘘を聞かされて、乾いた乾杯の言葉が耳を通り過ぎるたび、彼女の心はだんだん脆くなっていった気がする。うす暗い食堂のボックス席で、小銭を数えながら、少し古くなったコーヒーを注文しようとしていた。向かい側に座る彼女は、もう謝ることもなく感情も見せない。ただアイラインは微妙に滲み、靴底にはひび割れがあった。
「みんな私のこと嫌ってるっぽいよ」と彼女はぼそっと言った。手元のタバコは何本目だったか分からないけど、残り数回吸っては火を次へ移す、その繰り返し。煙で輪郭がほとんど消えそうだった。「ため込む人ほど私に執着している気がする。でも一番私から離れたいのもたぶんそういう人なんじゃないかな。」
祈ったり懇願したり命令したりすれば、自分がすぐ駆けつけると思われている、と続けた。でも実際には地下室かなにかで利息につながれている、とそんな比喩まで口にした。
それ以上説明はいらなかった。同じような感覚――胃の奥にじわっと広がる重たいもの、お財布を覗いたとき小銭しか残ってなくて、明日の子供のお弁当どうしようと焦る感じ。他人に頼ろうとしても誰にも簡単には助けてもらえず、相談しただけで変な目で見られることもある。
必要なのに、それでも心のどこかで彼女自身やその存在自体を恨めしく思ってしまう、その矛盾にも気づいていた。でも話さずにはいられなかった。ただ誰かに見てもらいたかっただけなのかもしれない。本当に助けてほしいとも思わず。ただ、それだけだった気がする。
「みんな私のこと嫌ってるっぽいよ」と彼女はぼそっと言った。手元のタバコは何本目だったか分からないけど、残り数回吸っては火を次へ移す、その繰り返し。煙で輪郭がほとんど消えそうだった。「ため込む人ほど私に執着している気がする。でも一番私から離れたいのもたぶんそういう人なんじゃないかな。」
祈ったり懇願したり命令したりすれば、自分がすぐ駆けつけると思われている、と続けた。でも実際には地下室かなにかで利息につながれている、とそんな比喩まで口にした。
それ以上説明はいらなかった。同じような感覚――胃の奥にじわっと広がる重たいもの、お財布を覗いたとき小銭しか残ってなくて、明日の子供のお弁当どうしようと焦る感じ。他人に頼ろうとしても誰にも簡単には助けてもらえず、相談しただけで変な目で見られることもある。
必要なのに、それでも心のどこかで彼女自身やその存在自体を恨めしく思ってしまう、その矛盾にも気づいていた。でも話さずにはいられなかった。ただ誰かに見てもらいたかっただけなのかもしれない。本当に助けてほしいとも思わず。ただ、それだけだった気がする。
財布の隅で小さくなっているお金の本音
彼女は、聞いているように見えた。いや、本当に耳を傾けてくれたのかもしれない。よくある自己啓発みたいな話し方じゃなかった。何段階もある豊かさの講座なんて、ここでは意味がなさそうだった。ただ、タバコの灰をビニールシートに落としながら、「うん、そうだね…私もあんたを痛めつけるために使われてきたんだよ」とぼそり。
キラキラしたものが目元に残っていたけど、それは安っぽいラメだった気がする。サーバーが「ボス」なんて呼び方をするとき、一瞬だけ肩がピクリと動く。その指先もちょっと震えていたような…誰かからまた声がかかるのを待ってる風にも思えなくもない。
なんだろう、この人、本来こういう場所で生きるために作られたわけじゃない気がしてならない。姿勢を直すことに意識が行く様子――無意識なのかな、大切に扱われたいとか、まだ価値ありと思われたいとか、そんな感じ?何度も使い古されて、それでも止まれと言われない存在になった、と誰か言っていたような…。
周りは彼女のことをどう見ているんだろう。派手さや繋がりや表向きだけしか目に入っていない気もする。でも、その奥には見えづらい檻みたいなものや疲労感とか…ちゃんと見る人は少数なのかもしれない。
心の奥底で、「もう休んでいいよ」と誰か言ってあげればいいのにな、とふと思った。でも現実には、そう簡単にはいかなかったみたいだ。
キラキラしたものが目元に残っていたけど、それは安っぽいラメだった気がする。サーバーが「ボス」なんて呼び方をするとき、一瞬だけ肩がピクリと動く。その指先もちょっと震えていたような…誰かからまた声がかかるのを待ってる風にも思えなくもない。
なんだろう、この人、本来こういう場所で生きるために作られたわけじゃない気がしてならない。姿勢を直すことに意識が行く様子――無意識なのかな、大切に扱われたいとか、まだ価値ありと思われたいとか、そんな感じ?何度も使い古されて、それでも止まれと言われない存在になった、と誰か言っていたような…。
周りは彼女のことをどう見ているんだろう。派手さや繋がりや表向きだけしか目に入っていない気もする。でも、その奥には見えづらい檻みたいなものや疲労感とか…ちゃんと見る人は少数なのかもしれない。
心の奥底で、「もう休んでいいよ」と誰か言ってあげればいいのにな、とふと思った。でも現実には、そう簡単にはいかなかったみたいだ。
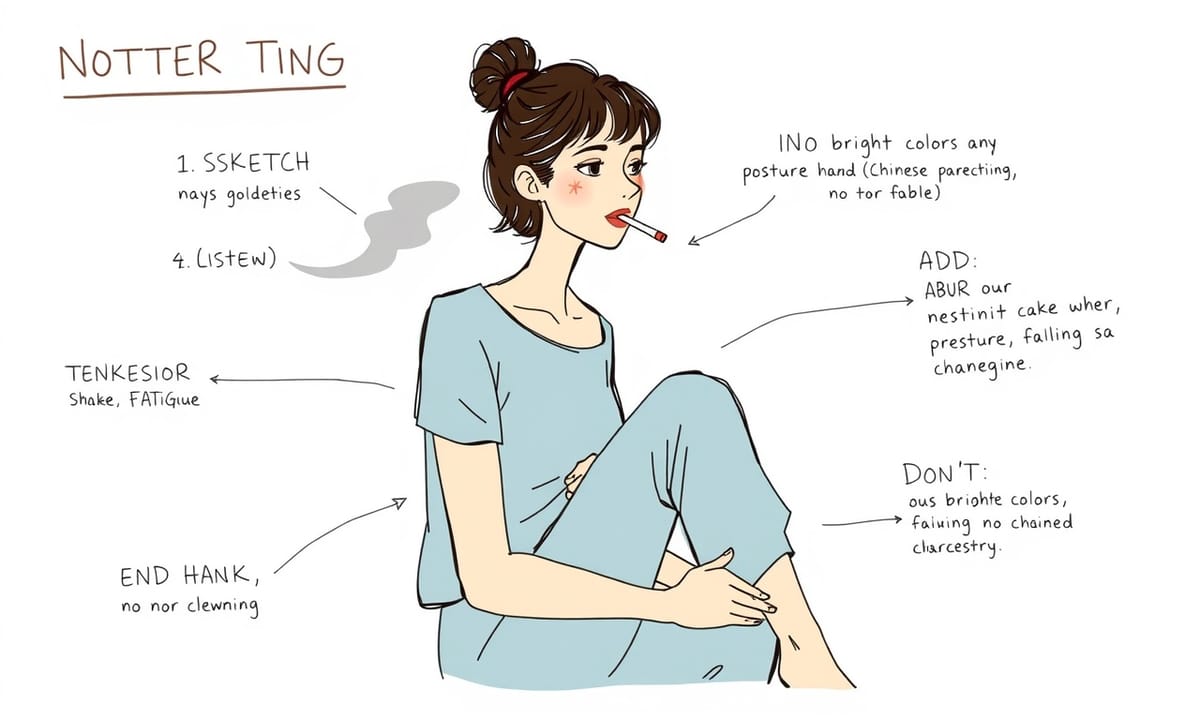
灰皿に積もる煙のように消える希望
あの人、なんとなく自分に似てる気がする。携帯が鳴ったけど、ほとんど反応しないまま画面をちらっと見て、それから何も考えずに荷物をまとめ始めた。リップのキャップがカチッて音立てて、バッグの口も閉じる。笑顔もつけて…たぶんずいぶん練習したみたいな感じで。
「もうそろそろ終わってると思ってたこともあったんだけどね」って、誰に言うでもなくつぶやいていた。「そのうち休ませてもらえるかな、とか。」
椅子を引くとき、膝が今まで歩いてきた道全部覚えてるみたいなゆっくりさだった。こんな風になるつもりは本当になかったとか、昔はただ少し楽になればいいとしか思ってなかったとか…いや、田舎で静かに暮らして流れに身を任せるのも悪くないよなぁ、とか。
鞄のジッパーに手をかけたまま動きを止めたりして、その間ふたりとも黙ったままで…夢なのか現実なのかわからないような希望が空中に浮いていた気がする。立ち上がってコート直す姿は、小さな鎧を着込むようだった。
「まあ…そんなもんだよね」と最後にぼそっと言った。そのあと何話したかはもうちょっと曖昧で…。
「もうそろそろ終わってると思ってたこともあったんだけどね」って、誰に言うでもなくつぶやいていた。「そのうち休ませてもらえるかな、とか。」
椅子を引くとき、膝が今まで歩いてきた道全部覚えてるみたいなゆっくりさだった。こんな風になるつもりは本当になかったとか、昔はただ少し楽になればいいとしか思ってなかったとか…いや、田舎で静かに暮らして流れに身を任せるのも悪くないよなぁ、とか。
鞄のジッパーに手をかけたまま動きを止めたりして、その間ふたりとも黙ったままで…夢なのか現実なのかわからないような希望が空中に浮いていた気がする。立ち上がってコート直す姿は、小さな鎧を着込むようだった。
「まあ…そんなもんだよね」と最後にぼそっと言った。そのあと何話したかはもうちょっと曖昧で…。
最後に残された皺くちゃな紙幣と約束
「……遅れちゃダメだよ。」彼女の声は、どこか申し訳なさそうに小さくなる。そんなことを言い残して、もうすぐ出て行こうとしていた。でも、その直前だったかな。「まだ、僕たちにチャンスがあると思う?」って静かに問いかけると、一瞬足が止まった気がした。
別に大きな答えなんて求めてなかった。ただ、ほんの少しでもいいから握りしめられるもの――それだけで良かった。全部終わったその先。疲れ果てた夜や裏切りとか、いつの間にかできあがっていた決まりごとみたいなのとか…いろんなものを通り越した向こう側には、「何か」が待っているんじゃないかって。従順でいることだけで生き延びる毎日じゃなくて、本当は休んでもいい世界があるんじゃないかな、と。
「私ばっかり頼られても困るよ」彼女は視線を合わせず、くしゃっとした紙幣をテーブルの端まで押し出すように滑らせながら、小声で呟いた。「ここにいるのは私も一緒。でもね……もしかしたら、そのうち出口くらい見つけられるかもしれない。」
それから数秒後だった気もするし、一瞬だったような気もする。ドアは音立てず閉じた。職場へ急ぎ戻る背中――結局また電話ばっかり取ってるみたいだ。それも、自分では選べない相手ばっかり。
瓶詰めになったその紙幣はいまでも机の上。不思議と幸運のお守り扱いにもならず、貯金というほど増えるわけでもなく。ただ時々眺めて、「お金とは敵同士というわけでもない」と思うだけ。でも、それだけじゃ救われないことくらいは分かった気がする。
…まあ、この話を読んだ誰かがふと思い出して誰かに話してくれたら、それだけで十分なのかな、と考えたりする時もあるよ。
別に大きな答えなんて求めてなかった。ただ、ほんの少しでもいいから握りしめられるもの――それだけで良かった。全部終わったその先。疲れ果てた夜や裏切りとか、いつの間にかできあがっていた決まりごとみたいなのとか…いろんなものを通り越した向こう側には、「何か」が待っているんじゃないかって。従順でいることだけで生き延びる毎日じゃなくて、本当は休んでもいい世界があるんじゃないかな、と。
「私ばっかり頼られても困るよ」彼女は視線を合わせず、くしゃっとした紙幣をテーブルの端まで押し出すように滑らせながら、小声で呟いた。「ここにいるのは私も一緒。でもね……もしかしたら、そのうち出口くらい見つけられるかもしれない。」
それから数秒後だった気もするし、一瞬だったような気もする。ドアは音立てず閉じた。職場へ急ぎ戻る背中――結局また電話ばっかり取ってるみたいだ。それも、自分では選べない相手ばっかり。
瓶詰めになったその紙幣はいまでも机の上。不思議と幸運のお守り扱いにもならず、貯金というほど増えるわけでもなく。ただ時々眺めて、「お金とは敵同士というわけでもない」と思うだけ。でも、それだけじゃ救われないことくらいは分かった気がする。
…まあ、この話を読んだ誰かがふと思い出して誰かに話してくれたら、それだけで十分なのかな、と考えたりする時もあるよ。




















































