高機能不安を抱える人が、日常で無理なく睡眠の質を底上げできるヒント
- 毎朝同じ時間に起きて、7日間続ける。
体内時計が整い、不安な夜も自然と眠気を感じやすくなるから。
- 就寝90分前に38~40℃のお風呂に15分入ってみる。
体温変化が眠気スイッチになり、頭の中の雑念リセットにも有効。
- 寝る前10分だけ紙の本か静かな音楽だけ楽しむ。
脳への刺激を減らし、不安で過活動な思考回路も徐々に鎮まるため。
- `今`の呼吸や感覚に意識集中するマインドフルネスを5分実践。
`もしまた同じ悩みが浮かんでも、その瞬間は脳と心がお休みできるから。
眠れぬ夜と完璧なスリープルーチン…高機能不安の静かな闘い#
去年の夏、たぶん四晩くらい連続で天井を見つめていた。眠れない理由ばかりが頭をぐるぐるして、他のことはほとんど考えられなかった気がする。寝る前には本を読んだり、スマホも触らずにいたし、決まった手順はだいたいやってたと思うけど、それでも電気を消すと急に目が冴えてしまって。
睡眠のための習慣みたいなのも、まあまあちゃんとしてた方だったかな。部屋は涼しくしてあったし、ベッドには本当に寝る時しか座らなかったし。ブルーライトカットも使っていたし、ときどきデカフェのお茶なんか飲んで落ち着こうとしてみたり。でも結局、またソファに移動して、隣でぐっすり寝ているパートナーを起こさないようにして…夜中ずっと天井眺めながら、「何でこんなに考えごと止まらないんだろう」って思ってた。
何やってもうまくいかない夜が重なると、不安とか焦りみたいなのが増えてきて、それがまた眠れなくするという悪循環になることもあるかもしれない。人によっては違う感じ方するかもしれないけど、自分の場合はそんなふうだった気がする。
睡眠のための習慣みたいなのも、まあまあちゃんとしてた方だったかな。部屋は涼しくしてあったし、ベッドには本当に寝る時しか座らなかったし。ブルーライトカットも使っていたし、ときどきデカフェのお茶なんか飲んで落ち着こうとしてみたり。でも結局、またソファに移動して、隣でぐっすり寝ているパートナーを起こさないようにして…夜中ずっと天井眺めながら、「何でこんなに考えごと止まらないんだろう」って思ってた。
何やってもうまくいかない夜が重なると、不安とか焦りみたいなのが増えてきて、それがまた眠れなくするという悪循環になることもあるかもしれない。人によっては違う感じ方するかもしれないけど、自分の場合はそんなふうだった気がする。
薬と副作用、SSRI体験記&精神的疲労って何だろう。
どれだけ瞑想やマインドフルネスに取り組んでも、カフェインを控えても、睡眠リズムを整えてみても、どうも頭の中が静かになることはなかった気がする。たしか何度目かの夜だったと思うけど、結局は近くのお医者さんに相談することになった。診察室での会話はあっさりしていて、「ミルタザピン」という薬を勧められた。もう少し検討とかあるかな…と思ったけど、案外すぐだった。
飲み始めてから最初の数日間――正確には七日以内だったかもしれない――骨まで疲れるようなだるさが続いた。頭も体も重くて、アパートの部屋をふらふら歩き回っていた覚えがある。その間は何事にも集中できず、ゾンビみたいになっていた、と言えばちょっと大げさかもしれない。ただ、その状態がいつまでも続くわけじゃなくて、大体一週間もしないうちに落ち着いてきた。
そういえば、それ以降は寝付きで困ることはほとんどなくなった。でも不思議なことに、考えごと自体が消えるわけではなくて、雑念や不安みたいなのは残っている感じ。以前SSRI系の薬を使っていた時期から数年(正確には七十ヶ月には満たないと思う)経つけれど、不眠や焦燥感が完全になくなるというより、「なんとなく前より過ごしやすい」と思う場面が増えている気がする。
全部解決したわけじゃないし、人によって違いそうだけど、自分の場合は今まで試した方法よりは合っているようだ。ただ、それも状況次第だから、一概におすすめとは言えないかもしれない。
飲み始めてから最初の数日間――正確には七日以内だったかもしれない――骨まで疲れるようなだるさが続いた。頭も体も重くて、アパートの部屋をふらふら歩き回っていた覚えがある。その間は何事にも集中できず、ゾンビみたいになっていた、と言えばちょっと大げさかもしれない。ただ、その状態がいつまでも続くわけじゃなくて、大体一週間もしないうちに落ち着いてきた。
そういえば、それ以降は寝付きで困ることはほとんどなくなった。でも不思議なことに、考えごと自体が消えるわけではなくて、雑念や不安みたいなのは残っている感じ。以前SSRI系の薬を使っていた時期から数年(正確には七十ヶ月には満たないと思う)経つけれど、不眠や焦燥感が完全になくなるというより、「なんとなく前より過ごしやすい」と思う場面が増えている気がする。
全部解決したわけじゃないし、人によって違いそうだけど、自分の場合は今まで試した方法よりは合っているようだ。ただ、それも状況次第だから、一概におすすめとは言えないかもしれない。
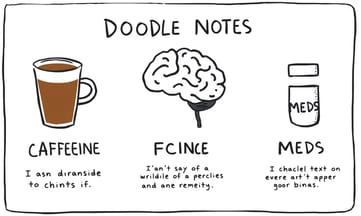
世代ギャップ×メンタルヘルス問題、昔話に潜む誤解!
時間が経つにつれて、なんだか「ハイファンクショニング不安」っていう言葉が頭をよぎることが多くなった気がする。まあ、普通に見えても内心で悩んでいる人は案外多いのかも?そう思うと、「みんな当たり前のように日々をやり過ごせばいい」という話もちょっと違和感ある。
それから、最近よく耳にするのは「昔は精神的な問題なんて誰もなかった」「自分たちの時代にはそんな言葉すらなかった」みたいな発言。正直、その手の話になると世代間で溝ができる印象。政治や宗教だけじゃなく、健康や心のことでも、年齢によって感じ方や捉え方は微妙にズレてくるものなんだろう。
「あの日々はただベッドから出て行動していた、それだけだった」と語る人もいる。でもね、そういう簡単な一言で片付けてしまう空気には少し危うさもあると思う。実際、心のケアを怠ることで何か見落としてしまうことだってあるはず。
ちなみに私はこれまで何度か診断を受けていて、不安障害にも種類があるらしい。たしか全般性不安障害とか社交不安障害とか…名前もうろ覚えだけど、とにかく二つくらい指摘されたような記憶がある。どれくらいの人が似た経験をしているかは分からないけど、このテーマについて話す機会自体が増えてきたという印象は拭えない。
実際、本当に今になって急にメンタルヘルス問題を抱える人が増えたのか、それとも単純に話題にしやすくなっただけなのか――そのあたり、まだ定まった答えはない気がする。ただ一つ言えるとしたら、「昔から存在していたけど表面化しづらかった」という見方もできるんじゃないかな、なんて思ってしまう。
それから、最近よく耳にするのは「昔は精神的な問題なんて誰もなかった」「自分たちの時代にはそんな言葉すらなかった」みたいな発言。正直、その手の話になると世代間で溝ができる印象。政治や宗教だけじゃなく、健康や心のことでも、年齢によって感じ方や捉え方は微妙にズレてくるものなんだろう。
「あの日々はただベッドから出て行動していた、それだけだった」と語る人もいる。でもね、そういう簡単な一言で片付けてしまう空気には少し危うさもあると思う。実際、心のケアを怠ることで何か見落としてしまうことだってあるはず。
ちなみに私はこれまで何度か診断を受けていて、不安障害にも種類があるらしい。たしか全般性不安障害とか社交不安障害とか…名前もうろ覚えだけど、とにかく二つくらい指摘されたような記憶がある。どれくらいの人が似た経験をしているかは分からないけど、このテーマについて話す機会自体が増えてきたという印象は拭えない。
実際、本当に今になって急にメンタルヘルス問題を抱える人が増えたのか、それとも単純に話題にしやすくなっただけなのか――そのあたり、まだ定まった答えはない気がする。ただ一つ言えるとしたら、「昔から存在していたけど表面化しづらかった」という見方もできるんじゃないかな、なんて思ってしまう。
診断されない高機能型不安という言葉、正体は?雑念。
正式に「ハイファンクショナル不安」って診断されたことは、まあ一度もなかったと思う。けど、ほぼ毎日、なんとなく自分がそれっぽいんじゃないかって感じてる。Arlin Cuncicという人がverywellmindで書いていた説明によると、「ハイファンクショナル不安」という言葉は、不安を抱えつつも、ある程度普通に生活しているように見える人たちを指すらしい。もっとも、医学的な診断名としては認められていないみたいだけど。
……このエッセイを書きながら気付いたのは、自分が今後正式に診断される可能性って、実際そんなになさそうだなあってこと。でもまあ、それは置いといて。小さい頃からずっと、人から「落ち着いて見える」とか「整理整頓できてるね」「しっかりしてるよね」みたいなことを言われてきた記憶がある。それを聞くと、その場では適当に相槌を打つものの、あとでこっそり何だったんだろう…と考えてしまう癖も抜けない。
最近になって思うのは――こういう部分って、生まれ持った性格や資質とかじゃなくて、不安とうまく付き合おうと必死で身につけた生き方なのかもしれない。年齢を重ねるにつれて少しずつわかってきた気がする。結局、人間って意外と環境や状況に合わせて変わろうとする力を持っているものなのかな、とふと思ったりする時もある。
……このエッセイを書きながら気付いたのは、自分が今後正式に診断される可能性って、実際そんなになさそうだなあってこと。でもまあ、それは置いといて。小さい頃からずっと、人から「落ち着いて見える」とか「整理整頓できてるね」「しっかりしてるよね」みたいなことを言われてきた記憶がある。それを聞くと、その場では適当に相槌を打つものの、あとでこっそり何だったんだろう…と考えてしまう癖も抜けない。
最近になって思うのは――こういう部分って、生まれ持った性格や資質とかじゃなくて、不安とうまく付き合おうと必死で身につけた生き方なのかもしれない。年齢を重ねるにつれて少しずつわかってきた気がする。結局、人間って意外と環境や状況に合わせて変わろうとする力を持っているものなのかな、とふと思ったりする時もある。
整理整頓・過剰達成、仮面の裏の本音@焦りや自己肯定感
外から見ると、なんとなく落ち着いているように見えることが多い。すごく整理整頓できてるとか、何かしらきっちりしてるって言われたりもする。ただ、その裏側では、「ちゃんとやれてるかな」とか「このままで大丈夫なのか」みたいな考えがぐるぐる回ってしまうこともある。人にどう思われているのか気になったり、変に思われたら嫌だなあと、不安になる瞬間もある。
昔から仕事を任されると、とにかく頑張って結果は残せていた気がする。評価の紙を見ると、やたら褒め言葉が並んでたり。でも、その過程では色々と心配事が尽きなくて、時には眠れない夜もあったような…。そういえば最近、自分の会社がアイルランドへの旅行を手に入れるきっかけを作った、と同僚から聞いた。出張というよりご褒美みたいな三日間で、周囲はみんな「すごいね!」と言ってくれる。
でも、それだけじゃなくて、この出来事そのものが自分の“いつも成果を出さなきゃ”っていう感覚――どこかで過剰になりやすい不安――そんな部分の現れにも思えてきた。まあ、人によっては全然違う風に感じるかもしれないけど、自分にはそんな一面もあるんじゃないかな、とふと思ったりする。
昔から仕事を任されると、とにかく頑張って結果は残せていた気がする。評価の紙を見ると、やたら褒め言葉が並んでたり。でも、その過程では色々と心配事が尽きなくて、時には眠れない夜もあったような…。そういえば最近、自分の会社がアイルランドへの旅行を手に入れるきっかけを作った、と同僚から聞いた。出張というよりご褒美みたいな三日間で、周囲はみんな「すごいね!」と言ってくれる。
でも、それだけじゃなくて、この出来事そのものが自分の“いつも成果を出さなきゃ”っていう感覚――どこかで過剰になりやすい不安――そんな部分の現れにも思えてきた。まあ、人によっては全然違う風に感じるかもしれないけど、自分にはそんな一面もあるんじゃないかな、とふと思ったりする。
成果=安心?褒められても止まらぬ証明欲求…
最近、メンタルヘルスって流行りみたいに話題になったりするけど、実際はそんな簡単なものじゃないと感じる人もいるかもしれませんね。誰かが怠けてるとか、やる気がないから苦しんでるって言われてしまうことも、まだちょくちょく耳にします。でも本当にそうでしょうか?自分の心の状態を隠してまで頑張り続けている人って、結構多い印象です。あまり表に出さないだけで、その裏ではずっと不安を抱えていたり。
たぶん、自分自身も昔からかなり無理して働いてきた方だと思います。それは認められたい気持ちから来ていたのかなぁ、と今になると考えたり。ただ、それが必ずしも健康的とは限らないというのは、この頃ようやく気づき始めました。だから何か失敗した時でも、「どうしてできなかったんだろう」と必要以上に自分を責めなくてもいい、と少し思えるようになってきた…そんな感覚です。
周囲を見ると、わたしたちの世代は前よりずっと心の問題を真剣に受け止めている雰囲気がある気がします。布団から出られないほど落ち込む日には仕事を休むとか、本当に無理そうな予定には「ごめんなさい」と断れるようになった人もちらほら見かけますよね。この変化について賛否あるとしても、人間らしく生きるためには大切な一歩なのかなぁとも思います。
逆に全部我慢してしまうと、いつの間にか機械みたいになってしまって、大事なものや日々の実感がどこかへ行ってしまいそうです。本当はもっと自然体でいたいし、それが一番難しい時代なのかもしれません。明確な答えなんてわからないままですが、「自分の心」を無視し続けなくてもいいんじゃないかな、と最近ぼんやり考えています。
たぶん、自分自身も昔からかなり無理して働いてきた方だと思います。それは認められたい気持ちから来ていたのかなぁ、と今になると考えたり。ただ、それが必ずしも健康的とは限らないというのは、この頃ようやく気づき始めました。だから何か失敗した時でも、「どうしてできなかったんだろう」と必要以上に自分を責めなくてもいい、と少し思えるようになってきた…そんな感覚です。
周囲を見ると、わたしたちの世代は前よりずっと心の問題を真剣に受け止めている雰囲気がある気がします。布団から出られないほど落ち込む日には仕事を休むとか、本当に無理そうな予定には「ごめんなさい」と断れるようになった人もちらほら見かけますよね。この変化について賛否あるとしても、人間らしく生きるためには大切な一歩なのかなぁとも思います。
逆に全部我慢してしまうと、いつの間にか機械みたいになってしまって、大事なものや日々の実感がどこかへ行ってしまいそうです。本当はもっと自然体でいたいし、それが一番難しい時代なのかもしれません。明確な答えなんてわからないままですが、「自分の心」を無視し続けなくてもいいんじゃないかな、と最近ぼんやり考えています。

精神疾患は流行じゃない*沈黙の苦しみと現代社会の偏見。
「ハイファンクショニングって呼ばれるものは、まあ、何にでも当てはまるかもしれない。強迫性障害とか気分の落ち込みとか、生理前のあれこれもそうだろうし。他の名前が付いた症状でも似たようなもの。結局、その呼び方自体にこだわる必要はあまりないんじゃないかなと感じたりすることもある。なんで自分が“ハイファンクショニング”という枠を使いたくなるのか…そこがむしろ気になったりして。
年齢を重ねてくると、自分の不安感みたいなものの根っこがどこにあるのか考える時間が増えた気もする。心理療法士としていろんな話を聞いてきたせいか、小さい頃を振り返らずにはいられなくなることも多くて。その頃、今よりもっと曖昧だったけど、何となく理由を求めてしまうんだよね。
幼少期はけっこう複雑だったと思う。何度も家が変わったり、一時的に他人の家で過ごす期間が続いた後、やっと新しい家族と出会えたのは小学生くらいだったかな。それ以降、「できるだけ良い子でいなきゃ」みたいな意識が自然とついてまわっていた気がする。本当にそのせいかわからないけど、それまで満足に誰かから認められる経験が少なかった反動なのか、「周囲より一歩抜きん出て見せたい」みたいな思考パターンが身についてしまったようにも思える。
今ではその辺りもうまく説明できない部分も多いけど、昔感じたモヤモヤや焦燥感って、大人になってからふとした瞬間によみがえってくることもまだある。この話題になるとどうしても記憶違いや細部を混ぜ込んで語ってしまうし…なんだか纏まらなくなっちゃった。でも、ときには細かな分析より自分自身への問い直しそのものに意味があるようにも思える。」
年齢を重ねてくると、自分の不安感みたいなものの根っこがどこにあるのか考える時間が増えた気もする。心理療法士としていろんな話を聞いてきたせいか、小さい頃を振り返らずにはいられなくなることも多くて。その頃、今よりもっと曖昧だったけど、何となく理由を求めてしまうんだよね。
幼少期はけっこう複雑だったと思う。何度も家が変わったり、一時的に他人の家で過ごす期間が続いた後、やっと新しい家族と出会えたのは小学生くらいだったかな。それ以降、「できるだけ良い子でいなきゃ」みたいな意識が自然とついてまわっていた気がする。本当にそのせいかわからないけど、それまで満足に誰かから認められる経験が少なかった反動なのか、「周囲より一歩抜きん出て見せたい」みたいな思考パターンが身についてしまったようにも思える。
今ではその辺りもうまく説明できない部分も多いけど、昔感じたモヤモヤや焦燥感って、大人になってからふとした瞬間によみがえってくることもまだある。この話題になるとどうしても記憶違いや細部を混ぜ込んで語ってしまうし…なんだか纏まらなくなっちゃった。でも、ときには細かな分析より自分自身への問い直しそのものに意味があるようにも思える。」
幼少期トラウマ→証明癖へ、不安症マインドセットを考察*
最初の数年間――七年とか、たぶんそれくらいだったと思うけど、その間は家族が味方になってくれる感じはなかった気がする。だから、多分なんでも自分でやらなきゃって思い込むようになったかもしれない。今も昔も、何か証明し続けなきゃ落ち着かないというか、不安なのに表面上は元気に見える…そんなふうに見られがちだろうね。仕事ではいつも頑張りすぎてしまって、まあよく言えば成果を出そうと必死。でもプライベートになると、自由な時間をちゃんと活用できていないような罪悪感がつきまとってることも多い。週末だって何もせず過ごすだけで、どこか自分を責めたりしてさ。本当は次の作品とか書けるんじゃないか、とか頭をよぎる時もある。でも、そればっかり考えている生活が健全とは言えないかなぁ…。外から見れば「高機能不安」みたいなのって良い面ばかり強調されてる感じだけど、その内側にはもう少し複雑なものが隠れている場合もあるみたい。
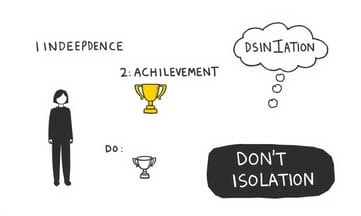
外面は理想社員、中身は不安でボロボロ…持続可能性の罠。
表面的には、どう見ても資本主義社会の働く人間の理想像みたいなものかもしれない。落ち着いてて、真面目で、普段からちゃんとやってるように映ることが多い。ただ、それは外側への顔と言われたりもするし、多分、不安を抱えている人が現代の生活圧力に適応するために自然と身につけてきた一種の方法だと思う。まあ、そうやって何とか日々を過ごすしかなかったんじゃないかな。
ところが、それがいつまでも続けられるかという話になると…正直よく分からない。人生って意外と長いし、例えば仕事を辞めるまであと数十年近くある気がする。もう少し具体的に言うと四十年弱くらい残っているかもしれない。でも、その間ずっと今みたいな働き方で健康的にやり切れる自信はそんなにない。
だからと言って急に怠け者になるつもりも全然なくて、別に投げやりになるわけでもない。ただ、このままずっと続けていたらどこかで無理が出る可能性もありそうだし…何となく漠然としている感覚だけど、本当にこの状態で全部乗り越えられるかは分からないなと思ったりして。
ところが、それがいつまでも続けられるかという話になると…正直よく分からない。人生って意外と長いし、例えば仕事を辞めるまであと数十年近くある気がする。もう少し具体的に言うと四十年弱くらい残っているかもしれない。でも、その間ずっと今みたいな働き方で健康的にやり切れる自信はそんなにない。
だからと言って急に怠け者になるつもりも全然なくて、別に投げやりになるわけでもない。ただ、このままずっと続けていたらどこかで無理が出る可能性もありそうだし…何となく漠然としている感覚だけど、本当にこの状態で全部乗り越えられるかは分からないなと思ったりして。
正直な対話が未来を変える!自分を守るための勇気と柔軟性
たとえば、自分の持っているエネルギーって、なんとなく限りがある気がしてきて――最近は、それを無理なく使う方法をちょっとずつ考えるようになった。遅刻しないで現れること、できる範囲で仕事に向き合うこと、それだけでも案外十分なのかもしれない。全部完璧にやろうとしても、結局どこかで疲れてしまいそうだし……ずっと仮面みたいな顔のままで過ごすのは、多分しんどい。
世の中もここ数年くらいで、気付けばメンタルヘルスについて話す機会が増えているらしい。むしろ前よりオープンに感じる人も多いとか。でも、何となくまだ「普通」に生きなくちゃと思い込んでいる人もいて、高機能に振る舞おうとすると逆にバランス崩しちゃうこともあるっていう話を聞いた。それよりは、自分の抱えてるものを認めて、ちょっと仕事や生活を調整する方が楽になる場合もあるかもしれない。「弱さ」と呼ばれることもあるけど、それって本当は強さと言える部分じゃないかな、と誰かがぽつりと言っていた記憶がある。
このテーマには明確な答えや期限なんてなさそうだけど、「グリーフ:時間割も正解もない旅」みたいな言葉を見かけた時、まあ焦らなくてもいいかなと少し思った。あ、この話題について知りたいなら、たまに情報をチェックしてみるのも悪くないかもしれない。
世の中もここ数年くらいで、気付けばメンタルヘルスについて話す機会が増えているらしい。むしろ前よりオープンに感じる人も多いとか。でも、何となくまだ「普通」に生きなくちゃと思い込んでいる人もいて、高機能に振る舞おうとすると逆にバランス崩しちゃうこともあるっていう話を聞いた。それよりは、自分の抱えてるものを認めて、ちょっと仕事や生活を調整する方が楽になる場合もあるかもしれない。「弱さ」と呼ばれることもあるけど、それって本当は強さと言える部分じゃないかな、と誰かがぽつりと言っていた記憶がある。
このテーマには明確な答えや期限なんてなさそうだけど、「グリーフ:時間割も正解もない旅」みたいな言葉を見かけた時、まあ焦らなくてもいいかなと少し思った。あ、この話題について知りたいなら、たまに情報をチェックしてみるのも悪くないかもしれない。



