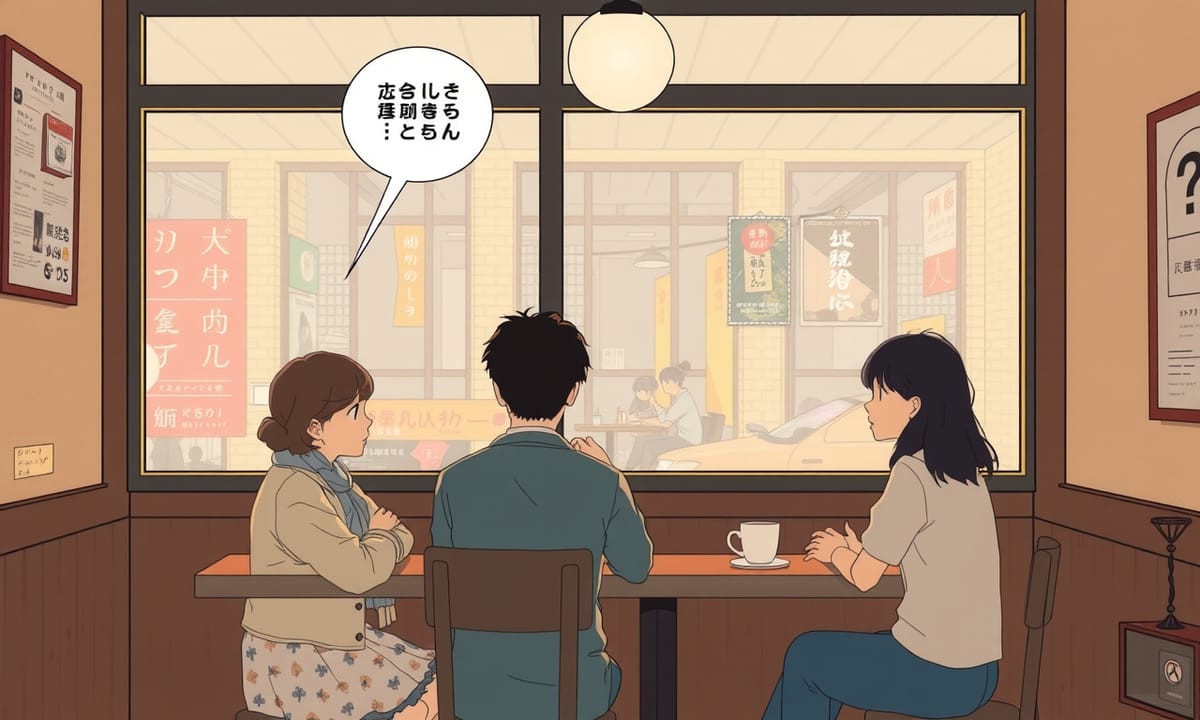性とジェンダーをめぐる日常の曖昧さ
今の法律だと、トランスジェンダーな人は「性別違和症」という診断が必要なんだって。うーん……なんか、医者ってほんとは誰かのアイデンティティを裁定する存在じゃなくて、たしか本分は健康守る方だった気がするけど。正直、「性」とか「ジェンダー」の話になると頭に霧がかかったみたいで、「そもそも一緒?」とか「あれ、この場合は?」みたいにもやっとする人、意外と多い気がしてさあ。ま、いいか。でも近ごろは声高な反論も目につくし、その議論で出てくる語句自体すらLGBTQやフェミニズムの周辺でも明快にはなりきれてない事柄ばっかという感じ。
遺伝子もホルモンも、それに器官……身体はいろんなものに規定されていて、「男女」って簡単に名付けて済むものなのかなぁって時々思う。ぱっと見だけじゃ判別できないことなんて山ほどあるしね。セックス――つまり生物学的な性――って所詮医学上の分類でしかなくて、それを絶対視する空気が昔から一部には根強い印象だった。でも、数十年前と比べればずっと揺らぎを含むようになったかな。皆すぐ腑に落ちたわけでもなく、その変化だって案外グレーなまま漂っている。
それでいて、「自分のジェンダーをどう認識したいか」とか「社会がどう扱うのか」なんて問いは、とても手短に整理できる範疇ではなくなってると思う。それぞれ考え方だいぶ異なるし、大づかみに輪郭決めちゃうには収まりきらない複雑さがつきまとっている――少なくとも、自分にはそう映る日がよくある。
遺伝子もホルモンも、それに器官……身体はいろんなものに規定されていて、「男女」って簡単に名付けて済むものなのかなぁって時々思う。ぱっと見だけじゃ判別できないことなんて山ほどあるしね。セックス――つまり生物学的な性――って所詮医学上の分類でしかなくて、それを絶対視する空気が昔から一部には根強い印象だった。でも、数十年前と比べればずっと揺らぎを含むようになったかな。皆すぐ腑に落ちたわけでもなく、その変化だって案外グレーなまま漂っている。
それでいて、「自分のジェンダーをどう認識したいか」とか「社会がどう扱うのか」なんて問いは、とても手短に整理できる範疇ではなくなってると思う。それぞれ考え方だいぶ異なるし、大づかみに輪郭決めちゃうには収まりきらない複雑さがつきまとっている――少なくとも、自分にはそう映る日がよくある。
本段の参照元: https://www.sasmadrid.org/index_php/noticias/sanidad/9967-somos-medicos-no-policias-del-genero-30-06-2022
社会に潜む見えない壁と言葉の戸惑い
たとえば、なんとなく思い当たるのは――日本みたいな場所だと「性」とか「ジェンダー」みたいな話題についてね、少しでも掘り下げて誰かと語り合おうとすると、不意に壁が出てきたりして。…自分だけかなと思ったけど、このあいだカフェでぽつりと話をした時もそんな風だったんだよね。正直、多くの人って日常生活でそういう言葉に全然触れなくて、「そこはちょっと自分にはピンとこないかなぁ」と最初から曖昧に濁して会話が止まってしまう。それになぜか新聞の記事になる時も、やたら慎重な言い回しになったりして、一歩踏み違えればすぐに誤解されちゃう気がする、というか……まあ、仕方ない部分もあるかな。
実感としては、社会全体では開放的になったようでいても、まだ透明な隔たりみたいなのが薄ぼんやり残っている感じが消えない。本当はもっと単純で素朴な疑問を投げかけてもいい場面なのに、それすら口ごもること結構多かった気がする。なんとなく発信者側にも昔々の価値観、そのまま引きずっちゃっている部分が今なおちらほら混じっていたりするから、不確かな説明だけで終わってしまう場合もしばしば。しかもさ、ごく最近いきなり新しい表現とか用語が続々登場してしまったものだから、受け取る側もすんなりついていけてない印象。「ジェンダー? 何それ?」と不意につぶやいてしまう場面、本当に身近な会話でも現れる。
……別にまとめるつもりじゃないんだけどさぁ、自分含め今こういう感覚を完全には咀嚼できず戸惑ってる人、多分想像以上に多いと思えてならない。ま、いいか。
実感としては、社会全体では開放的になったようでいても、まだ透明な隔たりみたいなのが薄ぼんやり残っている感じが消えない。本当はもっと単純で素朴な疑問を投げかけてもいい場面なのに、それすら口ごもること結構多かった気がする。なんとなく発信者側にも昔々の価値観、そのまま引きずっちゃっている部分が今なおちらほら混じっていたりするから、不確かな説明だけで終わってしまう場合もしばしば。しかもさ、ごく最近いきなり新しい表現とか用語が続々登場してしまったものだから、受け取る側もすんなりついていけてない印象。「ジェンダー? 何それ?」と不意につぶやいてしまう場面、本当に身近な会話でも現れる。
……別にまとめるつもりじゃないんだけどさぁ、自分含め今こういう感覚を完全には咀嚼できず戸惑ってる人、多分想像以上に多いと思えてならない。ま、いいか。