冒頭のアクションヒント - 所得格差や貧困層増加の現実に対して、今すぐ個人や家庭でできる具体的な防衛策
- 毎月の支出を3カテゴリ以内に分けて書き出す
家計管理が明確になり、無駄遣い発見・生活防衛力が高まる
- 公的支援や地域サービスを年1回以上調べ直す
制度変更や新規サポートの取りこぼし予防になる
- 副業・在宅ワークなど収入源を2つ以上持つ意識で探す
`もしも`に備えたリスク分散と将来不安軽減につながる
- [金融] 不安がある場合は専門家または自治体窓口へ早めに相談する
自力判断だけでは損失リスク拡大。第三者視点で新たな選択肢も見える
驚きの数字?貧困層シェア10%から17%へ
[![Photo by [John Moeses Bauan] on [Unsplash]] # 最低賃金改革によって、世界の貧困層の所得シェアが10%から17%に上昇する可能性がある。まあ、信じるかどうかは人それぞれだと思うけど。
### 画期的な国際調査によれば——あ、いや、その前にちょっと思い出したんだけど、最近本当にニュースを見てると格差とかばっかりで気が滅入るんだよね……まあいいや。本題に戻すと、その最低賃金の引き上げとか教育・医療分野への投資っていうのは、再分配課税だけよりもむしろ効果的らしい、と指摘されているんだ。うーん、「これで全部解決!」みたいな話にはどうせならない予感もするけど、それでも希望はあるかな……。
過去数十年にわたって、世界規模の格差について語られる内容や雰囲気、それと危機感なんかにも結構変遷があったような気がする。普通は富裕層と貧困層の溝ばっかり強調されてるイメージだけど、本当はそんな単純じゃなくてさ。実際、「国家間」で測定してみると、この25年間で全体として世界全体の格差自体は減少傾向だったみたい。でも一方で、その進展には複雑さも含まれていて――あぁ、ごめんまた話逸れそうになった――従来型政策手段だけじゃ十分とは言えない現状も見えてくるわけ。
パリ経済学校関連のWorld Inequality Lab(WIL)による新研究では、この流れの詳細や将来的な展望まで体系立てた枠組みを示しているそうだ。この報告書、現状分析だけじゃなく2050年までいくつものシナリオを提示していて、「最低賃金引き上げ」や「構造改革への投資」が再分配課税政策オンリーより公正へ近づく道になる場合もある、と結論付けているらしい。正直こういう未来予測って半信半疑なんだけど……それでも想像する余地くらいは残しておきたいよね。
2000年代初頭以降、「トップ1%」による税後所得シェアは17%から16%ちょっとまで減少した。一方「最貧50%」によるシェアは7%から10%へ増加したという数字も出ている。一瞬「あれ?平等進んでない?」と思いたくなる。でも平均値には対照的な二つのトレンドが潜在していて——いやもう何回この“平均”という言葉に振り回されたかわからない。それでも無視できない事実としてそこに残っている感じかな…。
### 画期的な国際調査によれば——あ、いや、その前にちょっと思い出したんだけど、最近本当にニュースを見てると格差とかばっかりで気が滅入るんだよね……まあいいや。本題に戻すと、その最低賃金の引き上げとか教育・医療分野への投資っていうのは、再分配課税だけよりもむしろ効果的らしい、と指摘されているんだ。うーん、「これで全部解決!」みたいな話にはどうせならない予感もするけど、それでも希望はあるかな……。
過去数十年にわたって、世界規模の格差について語られる内容や雰囲気、それと危機感なんかにも結構変遷があったような気がする。普通は富裕層と貧困層の溝ばっかり強調されてるイメージだけど、本当はそんな単純じゃなくてさ。実際、「国家間」で測定してみると、この25年間で全体として世界全体の格差自体は減少傾向だったみたい。でも一方で、その進展には複雑さも含まれていて――あぁ、ごめんまた話逸れそうになった――従来型政策手段だけじゃ十分とは言えない現状も見えてくるわけ。
パリ経済学校関連のWorld Inequality Lab(WIL)による新研究では、この流れの詳細や将来的な展望まで体系立てた枠組みを示しているそうだ。この報告書、現状分析だけじゃなく2050年までいくつものシナリオを提示していて、「最低賃金引き上げ」や「構造改革への投資」が再分配課税政策オンリーより公正へ近づく道になる場合もある、と結論付けているらしい。正直こういう未来予測って半信半疑なんだけど……それでも想像する余地くらいは残しておきたいよね。
2000年代初頭以降、「トップ1%」による税後所得シェアは17%から16%ちょっとまで減少した。一方「最貧50%」によるシェアは7%から10%へ増加したという数字も出ている。一瞬「あれ?平等進んでない?」と思いたくなる。でも平均値には対照的な二つのトレンドが潜在していて——いやもう何回この“平均”という言葉に振り回されたかわからない。それでも無視できない事実としてそこに残っている感じかな…。
格差減少と成長、でも国ごとでは話が違う
中国とかインドみたいな、あの急激に経済成長した国々のおかげでさ、ここ最近は国と国との間の経済格差がめっちゃ縮まったんだよね。たぶんグローバリゼーションってやつのポジティブな面を示してる気もするし…いや、違うかな?でもまあ、適切な条件が揃えば経済収斂だってちゃんと起こるんじゃないかと思わせられる。うーん、それなのに一方でというか、多くの国の中では所得格差が逆に広がっちゃってて、その流れが世界的な収斂による利益を正直言って打ち消しているようにも見える。
なんていうか、この二重構造?それ自体が不平等への対応について新しい課題を突きつけてくる感じ。たしかに国家全体として豊かになったと言われても、その富の分配は国内ですごく偏り始めている現実もあるわけで…。あれ、話逸れた。でも戻すと、そういった状況を踏まえてWorld Inequality Lab所属の4人の経済学者たちが将来について考察したわけ。今進行中の政策や現在みたいな傾向がこの先も続いたら2050年には世界規模で不平等はどう変化するだろう、と。
えっと、その研究によれば、大胆な対策でも講じない限り世界所得分布はこれからも大きく偏ったままだろうという予想だった。「ビジネス・アズ・ユージュアル」シナリオ――つまり現状維持路線ならばだけど――では、最貧困層50%の所得シェアは2050年までゆっくり12%くらいまで上昇するとされている。しかしその一方で、一番裕福な1%層はおよそ17%もの世界所得を依然として握り続ける見通しになっていてさ…。ま、いいか。結局、不平等問題ってそんな簡単じゃないよね。
なんていうか、この二重構造?それ自体が不平等への対応について新しい課題を突きつけてくる感じ。たしかに国家全体として豊かになったと言われても、その富の分配は国内ですごく偏り始めている現実もあるわけで…。あれ、話逸れた。でも戻すと、そういった状況を踏まえてWorld Inequality Lab所属の4人の経済学者たちが将来について考察したわけ。今進行中の政策や現在みたいな傾向がこの先も続いたら2050年には世界規模で不平等はどう変化するだろう、と。
えっと、その研究によれば、大胆な対策でも講じない限り世界所得分布はこれからも大きく偏ったままだろうという予想だった。「ビジネス・アズ・ユージュアル」シナリオ――つまり現状維持路線ならばだけど――では、最貧困層50%の所得シェアは2050年までゆっくり12%くらいまで上昇するとされている。しかしその一方で、一番裕福な1%層はおよそ17%もの世界所得を依然として握り続ける見通しになっていてさ…。ま、いいか。結局、不平等問題ってそんな簡単じゃないよね。
Comparison Table:
| 結論 | 内容 |
|---|---|
| 格差縮小の必要性 | 短期的な再分配策だけでは不十分で、長期的な構造改革が不可欠。 |
| 気候変動と所得分配 | 気候変動は貧困層の所得比率を減少させ、不平等を悪化させる可能性がある。 |
| 地域ごとの調整 | 政策は地域の経済状況や社会制度に応じて調整する必要がある。 |
| 早期介入の重要性 | 不平等が固定化する前に対策を講じる方が効果的。 |
| 包括的アプローチの必要性 | 経済、社会、環境政策を統合した多面的なアプローチが求められる。 |
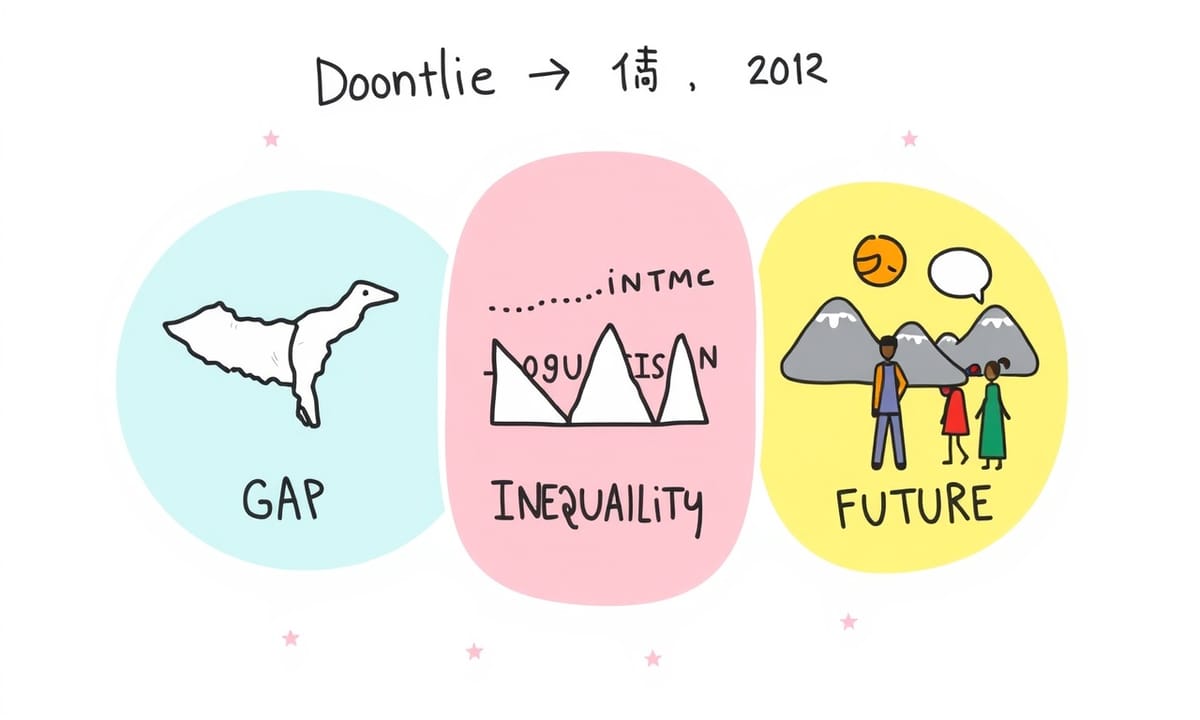
経済成長だけじゃ足りない—期待外れの未来予測
この示唆、なんだか身構えてしまう。慎重に受け取るべきだよね、多分。発展途上国の経済成長がいつか富の格差を埋めてくれる――って期待は長い間言われてきたけど、実際、それだけで十分とは限らないっぽい。いや、そもそも「埋まる」って誰が決めたんだろう…。話を戻すと、論文では主に二つの介入戦略について検討されていたんだ。一つ目は再分配志向の課税強化で、もう一つは所得格差を源泉段階で抑える方法というわけ。
まず第一の戦略では、お金持ち層への課税と、その収益を再び配分するという施策が含まれている。この場合、それぞれの国は自国内でもっとも進んでいる国々を参考にしながら、自国の税制と比較してみることになる。うーん…ヨーロッパの場合だったらデンマーク・フランス・イギリス、この三カ国の平均値が参照点になっていて、高所得層からおよそ13.4%もの総所得が再分配されているみたい。それなのに、中南米圏ではチリやコロンビア、それからエルサルバドル等の政策平均と比較して、大体7.3%程度しか再分配されない現状なんだよなぁ。不思議と言えば不思議。
ああ、そうそう。このアプローチには普遍的な基準とか単一基準みたいなものは提案されてなくて、それぞれ地域ごとの政治的現実とか―まあ色んな背景事情―を考慮した上で、「目標」と「実現可能性」のバランスも探っているところが特徴と言える。ま、ときどき何か抜け落ちてない?とか思ったりするけど…やっぱり本筋へ戻ろう。
まず第一の戦略では、お金持ち層への課税と、その収益を再び配分するという施策が含まれている。この場合、それぞれの国は自国内でもっとも進んでいる国々を参考にしながら、自国の税制と比較してみることになる。うーん…ヨーロッパの場合だったらデンマーク・フランス・イギリス、この三カ国の平均値が参照点になっていて、高所得層からおよそ13.4%もの総所得が再分配されているみたい。それなのに、中南米圏ではチリやコロンビア、それからエルサルバドル等の政策平均と比較して、大体7.3%程度しか再分配されない現状なんだよなぁ。不思議と言えば不思議。
ああ、そうそう。このアプローチには普遍的な基準とか単一基準みたいなものは提案されてなくて、それぞれ地域ごとの政治的現実とか―まあ色んな背景事情―を考慮した上で、「目標」と「実現可能性」のバランスも探っているところが特徴と言える。ま、ときどき何か抜け落ちてない?とか思ったりするけど…やっぱり本筋へ戻ろう。
税制改革に頼る限界、南アフリカの例で見る現実
この税制に重きを置くアプローチ、まあ一応格差をちょっとは和らげる可能性があるんだけど、やっぱり限界もかなり明白だよね。なんか気がついたら脱線してた…いや、話戻すと、このシナリオでは2050年までに下位50%の所得割合がせいぜい15%に増えるだけで、大した変化とは言い切れない気もする。うーん、進歩は進歩なのかもしれないけど、胸を張って「改善」と叫べるほどではないな。
実際のところ、一番肝心なのはさ、不平等という根深い問題を抱えている社会だと、課税ばっかり頼りに格差解消しようとしても結局構造的な壁が立ちはだかるってこと。それは例えば南アフリカみたいにもともと所得格差がものすごく激しい国の場合、どんな累進的な税制度を持ってきてもスウェーデンとかみたいな平等レベルには多分届かないんじゃないかな…なんて指摘されてたりする。でもまあ、それもそうだよね。
ああ、ここでちょっと脇道だけど、WIL研究で取り上げられているもう一つの選択肢――これは「課税前」つまり根本から格差対策しようって考え方。たぶんこっちの方が手ごたえある感じ?最低賃金の引き上げとか教育・医療への大規模投資によって雇用機会や生活基盤そのものを均等化しちゃえば、賃金格差自体も縮まるわけだし。でも…この話してるとお腹減ってきた、不思議。
さて本題へ戻そう。各国は、自国内でも賃金平等でうまくやれている例から学ぼうという意識が必要になってくると思われる。ヨーロッパだったら、その一例としてアイスランドとか欧州内でも割と賃金格差が小さい国々の政策導入なんていう流れになるんじゃないかな。ま、それぞれ事情も違うけどさ。
実際のところ、一番肝心なのはさ、不平等という根深い問題を抱えている社会だと、課税ばっかり頼りに格差解消しようとしても結局構造的な壁が立ちはだかるってこと。それは例えば南アフリカみたいにもともと所得格差がものすごく激しい国の場合、どんな累進的な税制度を持ってきてもスウェーデンとかみたいな平等レベルには多分届かないんじゃないかな…なんて指摘されてたりする。でもまあ、それもそうだよね。
ああ、ここでちょっと脇道だけど、WIL研究で取り上げられているもう一つの選択肢――これは「課税前」つまり根本から格差対策しようって考え方。たぶんこっちの方が手ごたえある感じ?最低賃金の引き上げとか教育・医療への大規模投資によって雇用機会や生活基盤そのものを均等化しちゃえば、賃金格差自体も縮まるわけだし。でも…この話してるとお腹減ってきた、不思議。
さて本題へ戻そう。各国は、自国内でも賃金平等でうまくやれている例から学ぼうという意識が必要になってくると思われる。ヨーロッパだったら、その一例としてアイスランドとか欧州内でも割と賃金格差が小さい国々の政策導入なんていう流れになるんじゃないかな。ま、それぞれ事情も違うけどさ。
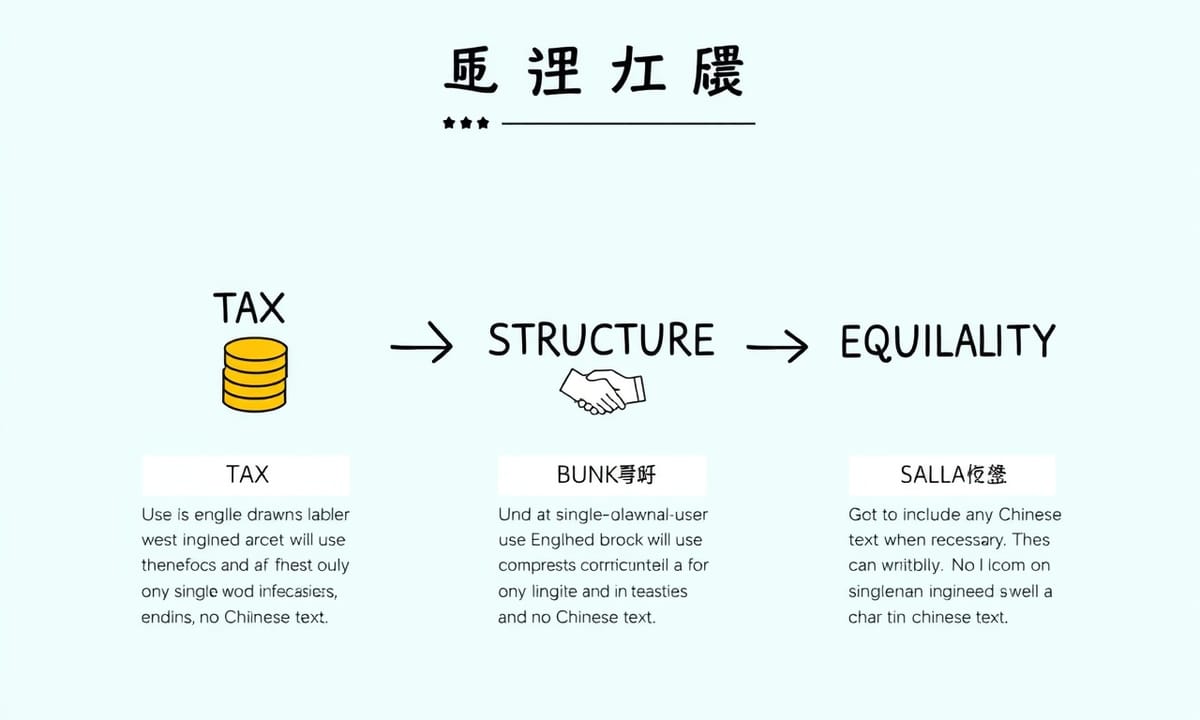
最低賃金アップvs.課税強化 どっちが効く?
この方法、所得が生じたときに直に作用するっていうのが肝らしい。ああ、ちょっと話逸れるけど、本当にそんなに即効性あるのかな、とか思ったりもするけど…やっぱり事後的な手法よりは、富の再分配で効率的だと広く認識されているわけ。まあ、納得できる部分もあるか。
それでね、このモデルだと世界人口の下位半分――つまり50%が2050年までに世界全体の所得の最大17%を受け取れる可能性があるらしい。えっと、それって課税型モデルより受益者が多いんじゃないかという指摘もあるんだよな。ま、いいか。
でも一番希望を集めているのは第三のハイブリッド型モデルみたいでさ、いや本当なの?と思いつつ…。それは再分配課税と構造変革、その両方を合わせ持った形態なんだって。なんか複雑そうだけど意外とうまくいくものなのかな、と一瞬考える。でも——やっぱり本筋戻そう。
各国が最低賃金を引き上げたり社会インフラへ投資したりして、そのうえ税制自体もさらに累進性を強める状況になれば、もっと望ましい結果になる見込みらしいよ。この複合モデルの場合ならば下位50%層が2050年までに世界所得のおよそ19%を受給し、一方で上位1%によるシェアは12%まで減少すると予測されているということなんだけど…まあ数字ばっかり追いすぎても現実感なくなるし、不安にもなるけれど、大筋ではそんな話だね。
それでね、このモデルだと世界人口の下位半分――つまり50%が2050年までに世界全体の所得の最大17%を受け取れる可能性があるらしい。えっと、それって課税型モデルより受益者が多いんじゃないかという指摘もあるんだよな。ま、いいか。
でも一番希望を集めているのは第三のハイブリッド型モデルみたいでさ、いや本当なの?と思いつつ…。それは再分配課税と構造変革、その両方を合わせ持った形態なんだって。なんか複雑そうだけど意外とうまくいくものなのかな、と一瞬考える。でも——やっぱり本筋戻そう。
各国が最低賃金を引き上げたり社会インフラへ投資したりして、そのうえ税制自体もさらに累進性を強める状況になれば、もっと望ましい結果になる見込みらしいよ。この複合モデルの場合ならば下位50%層が2050年までに世界所得のおよそ19%を受給し、一方で上位1%によるシェアは12%まで減少すると予測されているということなんだけど…まあ数字ばっかり追いすぎても現実感なくなるし、不安にもなるけれど、大筋ではそんな話だね。
ハイブリッド策なら最底辺も19%超えかも…夢物語?
このシナリオには、なんだろうな…あらためて思い知らされる重要な教訓が浮かび上がってくる。あ、でもちょっとだけ話が逸れるけど、最近自分も格差とか考えすぎて眠れなくなる夜が多いんだよね。でも本題に戻そう。つまり、本当に格差を縮めようと思ったら、短期的な再分配策だけじゃ足りなくて、長期的な構造改革も同時にやる必要がある――そういう二本柱の戦略が不可欠ってことだ。ま、それは誰でも薄々感じているかもしれないけど。
それだけじゃなくて、この研究では気候変動が世界規模で所得分配にどう影響するかも調べているんだ。正直言って複雑すぎて頭痛くなるけど…。環境劣化と不平等の関係性は、直接的にも間接的にも存在すると指摘されているし、こういうのって一筋縄じゃいかないよね。でさ、一旦話が脱線するけど、「赤道付近」って言葉聞くだけで暑苦しい気分になるのは僕だけ?いや、戻ります。
マクロレベルでは普通、赤道周辺や熱帯地域みたいな貧困国ほど干ばつとか洪水、それから熱波みたいな災害の曝露度が高い傾向にあるわけで、そうした出来事は経済成長を鈍化させたりインフラを壊したり、多くの人々を貧困状態に追いやる可能性も孕んでいる。うーん、救われない話だ。でもここからミクロレベルの視点に切り替えると、その各国の貧困層というのは環境ショックによる影響を特に受けやすいとも言われていて。
例えば質の低い住居とか保険未加入とか資源へのアクセス不足なんかが重なると、災害後の回復はめちゃくちゃ難しくなることもあるわけですよ。ま、それでも生き抜こうとする人たちは凄いんだけど…。でまた元に戻して――研究者たちはこうした気候シナリオを予測モデルへ組み込むことで、環境条件悪化による格差拡大の可能性について観察しているらしい。ほんとうに終わりなき課題だよね。
それだけじゃなくて、この研究では気候変動が世界規模で所得分配にどう影響するかも調べているんだ。正直言って複雑すぎて頭痛くなるけど…。環境劣化と不平等の関係性は、直接的にも間接的にも存在すると指摘されているし、こういうのって一筋縄じゃいかないよね。でさ、一旦話が脱線するけど、「赤道付近」って言葉聞くだけで暑苦しい気分になるのは僕だけ?いや、戻ります。
マクロレベルでは普通、赤道周辺や熱帯地域みたいな貧困国ほど干ばつとか洪水、それから熱波みたいな災害の曝露度が高い傾向にあるわけで、そうした出来事は経済成長を鈍化させたりインフラを壊したり、多くの人々を貧困状態に追いやる可能性も孕んでいる。うーん、救われない話だ。でもここからミクロレベルの視点に切り替えると、その各国の貧困層というのは環境ショックによる影響を特に受けやすいとも言われていて。
例えば質の低い住居とか保険未加入とか資源へのアクセス不足なんかが重なると、災害後の回復はめちゃくちゃ難しくなることもあるわけですよ。ま、それでも生き抜こうとする人たちは凄いんだけど…。でまた元に戻して――研究者たちはこうした気候シナリオを予測モデルへ組み込むことで、環境条件悪化による格差拡大の可能性について観察しているらしい。ほんとうに終わりなき課題だよね。
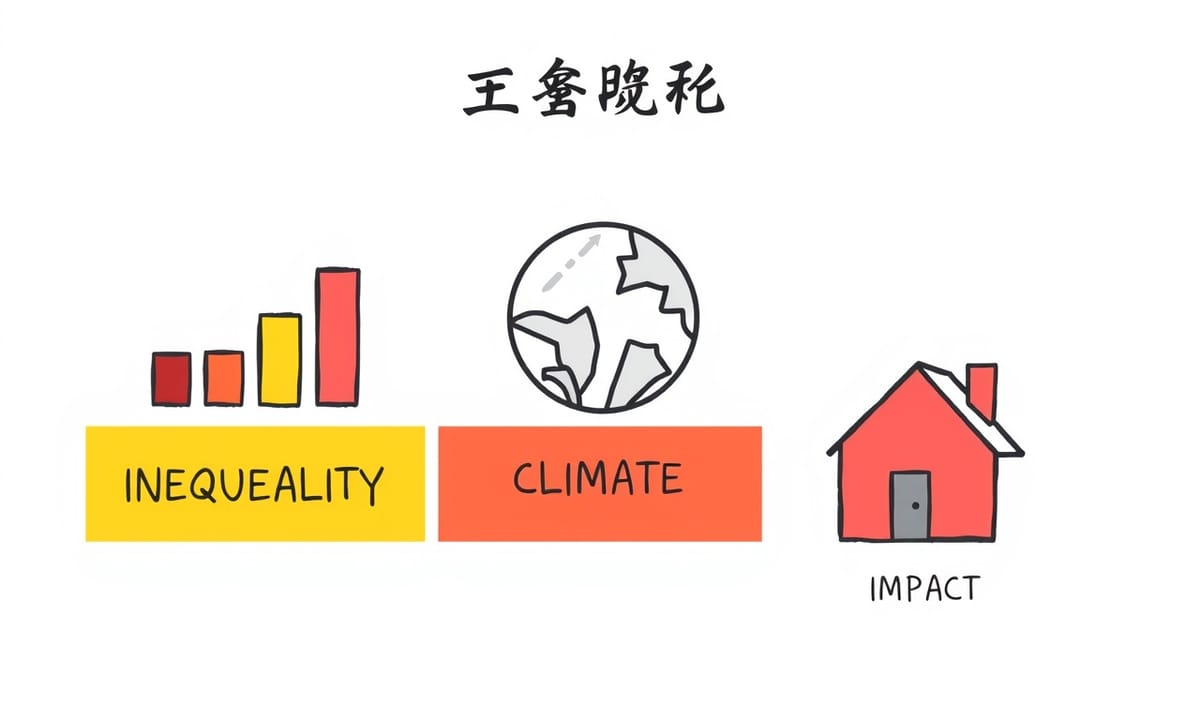
気候変動で逆戻り?1980年代への危険なカーブ
中程度のシナリオによれば、気候変動が進行することで最貧困層50%の所得比率は、予想されていた12%から2050年には11%まで減少する見通しだという。うーん、1%だけか…と思いきや、その一歩は意外と重い意味を持つらしい。なんだろう、この数字自体は小さいけど背後にあるものが大きい感じがして落ち着かない。まあ、それで済めばいいんだけど。
もっと悲観的な予測もあってさ、この同じグループの所得比率が7%にまで落ち込む可能性も語られている。もしそうなると、せっかく数十年かけて積み上げた進展が水泡に帰すことになり、中国やインドがまだ経済成長を本格化させる前――つまり1980年代くらい?――その頃の不平等レベルまで逆戻りしちゃう、と警告されているわけ。えっと…こう書いてる途中でふと思ったんだけど、不確実性って本当に厄介だよね。でも話を戻すと、この幅広い結果こそが気候変動の影響にまつわる大きな不透明感を物語っている。
とは言え、本質的なメッセージ自体はかなり明快だったりする。「環境政策」と「経済的公正さ」って表裏一体なんだ、と示してくれる知見になっているようだし…。実際この研究では、不平等是正策として過去によく提案されてきた色々な手法についても再考を促しているとのこと。ああ、富裕層への課税強化という対応策は理屈として分かりやすい。でも、それだけじゃ足りないという声も根強い。
課税自体は確かに重大な政策アジェンダたり得るけれど、それ一本槍ではなくて、直接所得創出へ働きかけるようなより攻めた介入策で補完しない限り、「十分」とは言えない状況なのかなぁ、と感じる次第です…いや、本当どうしたものかな。
もっと悲観的な予測もあってさ、この同じグループの所得比率が7%にまで落ち込む可能性も語られている。もしそうなると、せっかく数十年かけて積み上げた進展が水泡に帰すことになり、中国やインドがまだ経済成長を本格化させる前――つまり1980年代くらい?――その頃の不平等レベルまで逆戻りしちゃう、と警告されているわけ。えっと…こう書いてる途中でふと思ったんだけど、不確実性って本当に厄介だよね。でも話を戻すと、この幅広い結果こそが気候変動の影響にまつわる大きな不透明感を物語っている。
とは言え、本質的なメッセージ自体はかなり明快だったりする。「環境政策」と「経済的公正さ」って表裏一体なんだ、と示してくれる知見になっているようだし…。実際この研究では、不平等是正策として過去によく提案されてきた色々な手法についても再考を促しているとのこと。ああ、富裕層への課税強化という対応策は理屈として分かりやすい。でも、それだけじゃ足りないという声も根強い。
課税自体は確かに重大な政策アジェンダたり得るけれど、それ一本槍ではなくて、直接所得創出へ働きかけるようなより攻めた介入策で補完しない限り、「十分」とは言えない状況なのかなぁ、と感じる次第です…いや、本当どうしたものかな。
「万能薬」なき時代、政策は地域色に染まるしかない
最低賃金の引き上げとか、質の高い医療や教育への普遍的アクセスの確保、さらに人的資本への構造的投資――こういうのって単なる倫理的な話だけじゃなくて、よりバランスの取れたグローバル経済を築くには実際に必要らしい。まあ、それもそうかもしれない。でも、ふとコーヒーが冷めてることに気づいてしまった…ああ戻ろう、本題へ。本書で特に強調されているのは、政策を適用する際に地域ごとの調整がすごく大切だという点なんだよね。経済状況とか政治的現実、社会制度ってさ、本当に場所によって全然違う。だからスカンジナビアでできることが、そのままサブサハラ・アフリカや東南アジアではうまくいくとは限らないし、むしろ無理な場合もあるんだ。そういう違いを認識することで初めて現実的かつ効果的な戦略につながる可能性も出てくる、と言われている。
それから…時期も案外重要なんだよ。不平等が社会構造に深く根付いてしまった後から是正しようとするより、不平等がまだ固定化していない早めの段階で何らか対策したほうが効果を期待できる場合が多いっぽい。ま、いいか。でも、教育や医療改革みたいな上流段階で始める政策ってさ、成果が見えるまで時間かかりすぎてちょっとイライラする人もいると思うんだけど、その分長期的で広範囲な効果を生む可能性は高いらしい。えっと…ついつい考えすぎちゃったけど、それくらい根気と配慮が必要なのかな、とぼんやり思うわけです。
それから…時期も案外重要なんだよ。不平等が社会構造に深く根付いてしまった後から是正しようとするより、不平等がまだ固定化していない早めの段階で何らか対策したほうが効果を期待できる場合が多いっぽい。ま、いいか。でも、教育や医療改革みたいな上流段階で始める政策ってさ、成果が見えるまで時間かかりすぎてちょっとイライラする人もいると思うんだけど、その分長期的で広範囲な効果を生む可能性は高いらしい。えっと…ついつい考えすぎちゃったけど、それくらい根気と配慮が必要なのかな、とぼんやり思うわけです。
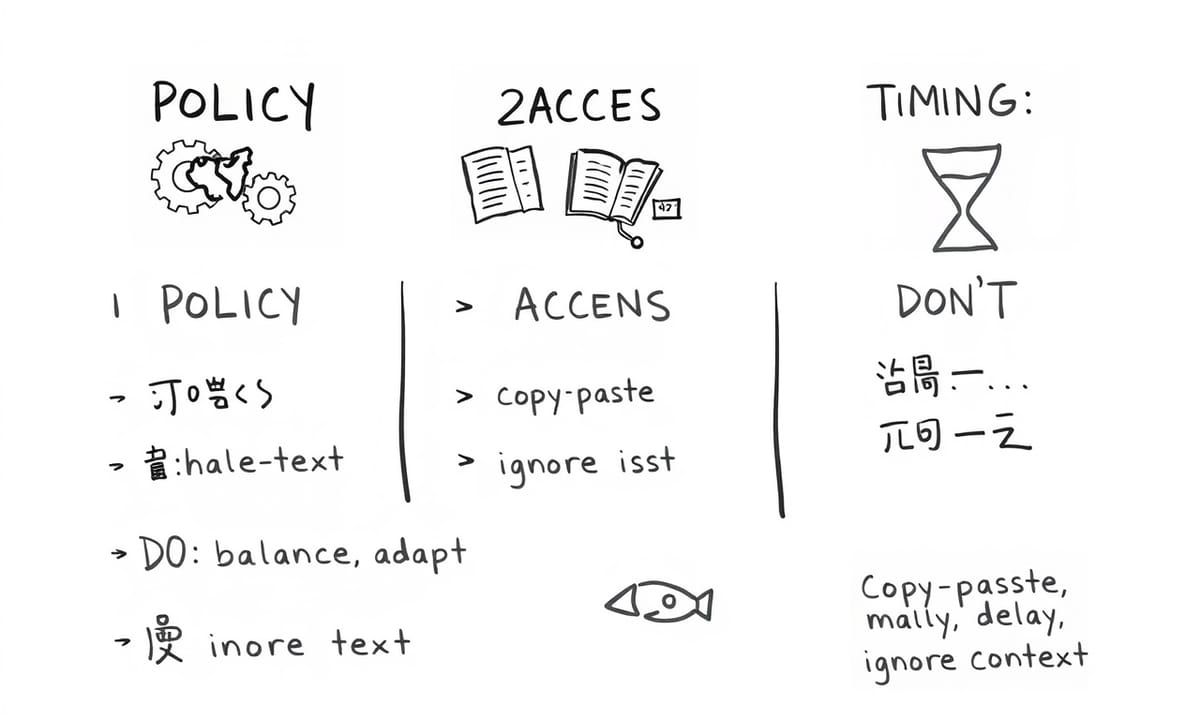
早めの介入こそが命運を分ける—遅すぎたら手遅れかもね
一方で、再分配課税って、即効性のある救済を提供できる可能性がある…まあそう思われがちなんだけど、政治的なリスクもつきまとうし、その根本にある構造的な問題への対応が後回しにされちゃうこと、多い気がする。いや、本当にこれって難しいよね。ふと窓の外見たら雨だし、話戻すと—この結果から考えると、グローバル機関や政府、それに市民社会も、不平等への対策として多面的なアプローチを取らざるを得ないようだ。単純には片付かないんだよね。
経済政策というものは、社会政策や環境政策、さらには政治の領域から切り離して論じることは不可能だと思う。ああ、それなのについ数字だけ追っちゃう癖が抜けなくて…。でも現実として、気候変動への取り組みでは、その社会的影響にもちゃんと向き合わなければならないし、不平等の解消も経済的手段だけじゃ到底足りないんじゃないかなと思ったりする。
それぞれの課題ごとにさ、富の創出・分配・持続ってどうあるべきなのか、それに影響する幅広い要素へ目を向けて進めていくための包括的な枠組み——ちょっと大げさかもしれないけど—これが必要になるんじゃないかな。WIL調査って警鐘でありつつ、一種の指針にも感じられるし。
けれど、本質的な変革なしに今まで通り進んでいくならば、この世界は今後も不平等状態から逃れられないかもしれない。それだけじゃなくてね、環境面で加わる圧力によって格差がさらに拡大してしまうとか…いや最悪の場合は、ここ数世代分の進展さえ逆戻りするリスクも孕んでいるとも言われているし。本当にどうしたものか…。
経済政策というものは、社会政策や環境政策、さらには政治の領域から切り離して論じることは不可能だと思う。ああ、それなのについ数字だけ追っちゃう癖が抜けなくて…。でも現実として、気候変動への取り組みでは、その社会的影響にもちゃんと向き合わなければならないし、不平等の解消も経済的手段だけじゃ到底足りないんじゃないかなと思ったりする。
それぞれの課題ごとにさ、富の創出・分配・持続ってどうあるべきなのか、それに影響する幅広い要素へ目を向けて進めていくための包括的な枠組み——ちょっと大げさかもしれないけど—これが必要になるんじゃないかな。WIL調査って警鐘でありつつ、一種の指針にも感じられるし。
けれど、本質的な変革なしに今まで通り進んでいくならば、この世界は今後も不平等状態から逃れられないかもしれない。それだけじゃなくてね、環境面で加わる圧力によって格差がさらに拡大してしまうとか…いや最悪の場合は、ここ数世代分の進展さえ逆戻りするリスクも孕んでいるとも言われているし。本当にどうしたものか…。
表面的解決と根本的変革、その選択肢だけが残された
でもさ、予防的でしかもちゃんと協調された政策を積極的にやるって話、うーん…なんかそれだけで全部変わりそうな気がしなくもないけど、正直言って未来がもっと公平になる可能性は確かにあると思う。でもね、それには政治の意思とか、社会全体の連帯感みたいなもの―いや、どうしても抽象的になっちゃうなあ―それから何より揺るぎない正義への本気のコミットメントというやつが欠かせない。ま、それが現実でどれだけ難しいことか…ふと考えてしまう。でも2050年を見据えるとしてさ、今日自分たちが選ぶ道って案外決定的なんじゃないかな。ああ、ごめん、一瞬話逸れたけど戻すよ。
社会は結局、不平等の症状をちょっと和らげるだけの短期対策ばっか選ぶの?それとも、公平そのものについて改めて問い直すような構造改革に飛び込む勇気ある?誰にもわからないし、自分だって迷いそう。でも観察された証拠を見る限りではね、「後者」つまり構造改革こそが、不平等という長く続く課題に対する唯一持続可能な手立てになり得る、と示唆されている。ま、いいか。ほんとは簡単じゃないんだけどさ。
社会は結局、不平等の症状をちょっと和らげるだけの短期対策ばっか選ぶの?それとも、公平そのものについて改めて問い直すような構造改革に飛び込む勇気ある?誰にもわからないし、自分だって迷いそう。でも観察された証拠を見る限りではね、「後者」つまり構造改革こそが、不平等という長く続く課題に対する唯一持続可能な手立てになり得る、と示唆されている。ま、いいか。ほんとは簡単じゃないんだけどさ。



















































