消費社会で孤独や本物志向に悩む心を柔らかくする即行動ガイド
- 週1回10分、身近な自然や静かな場所でスマホを手放す
外界から離れることで思考がクリアになり、自己と向き合いやすくなる
- 月2回以上、自分の気持ちや欲望を書き出し、本当に欲しいものを見直す
ラカン的な他者視点に流されず、本心の発見と納得感につながる
- 友人か家族1人以上に最近感じた孤独や満たされなさを率直に話してみる
感情共有が承認欲求の健全化や孤立感緩和へ作用するから
- `買う前`の商品・サービスは24時間寝かせて選択する癖づけ
衝動消費による空虚さを減らし、本当に必要な体験だけ選べるようになる
迷路する郊外、嫌悪と自然への憧れ
【引退と人間性の商品化】
なんか最近、19歳だししょうがないのかもしれないけど、将来について考えることがやたら増えた気がする。うーん、大学のこともあるし、ジャーナリズム系で働きたいっていう夢も一応持ってる。でも正直、一番気になっちゃうのは「引退」っていう人生のステージなんだよね。本当に仕事を続けていく意味とか、その先に何が残るのか、ときどきわからなくなる瞬間があったりして。ま、それでもパートナーとか犬と静かな暮らしを送れたら…って勝手に妄想したりもする。ああ、つい話題が逸れそうだけど、引退後ゆっくり過ごせる時期―それがどういうものなのか、本当に興味深い。
さて、自分が今住んでいる南ニュージャージー州なんだけど、大体イメージとしては農地と郊外、それからリタイアメントコミュニティ(つまり引退者向け住宅地)が点在している地域。実はそうした場所ってさ、迷路みたいに複雑だったりすることもあるんだよね。例えば目立つランドマークみたいなものもほぼなくて、似たり寄ったりな家並みや木々ばっかりだから、不思議と道にも迷いやすい構造になっている。そういう経験を繰り返すうちに、自分はこの種のコミュニティにはもう苦手意識しか持てなくなった感じ。でもまあ、人によって居心地いいところは違うし…いや自分には合わないかなと思いつつ、本筋へ戻ろう。
逆に考えてみると、「否定形」として浮かぶもの―つまり人里離れた自然豊かな美しい空間、本当の生き物たちが息づくような場所―そこで迎える引退生活への憧れというか関心が段々強まった気がするんだよね。こんな風に書いておいて、本当にそんな環境で落ち着いた日々を送れるのかなあとふと思ったりもするけど…まあ、それでも今は「いつの日か叶えばいいな」というくらいで止めておこうと思う。
なんか最近、19歳だししょうがないのかもしれないけど、将来について考えることがやたら増えた気がする。うーん、大学のこともあるし、ジャーナリズム系で働きたいっていう夢も一応持ってる。でも正直、一番気になっちゃうのは「引退」っていう人生のステージなんだよね。本当に仕事を続けていく意味とか、その先に何が残るのか、ときどきわからなくなる瞬間があったりして。ま、それでもパートナーとか犬と静かな暮らしを送れたら…って勝手に妄想したりもする。ああ、つい話題が逸れそうだけど、引退後ゆっくり過ごせる時期―それがどういうものなのか、本当に興味深い。
さて、自分が今住んでいる南ニュージャージー州なんだけど、大体イメージとしては農地と郊外、それからリタイアメントコミュニティ(つまり引退者向け住宅地)が点在している地域。実はそうした場所ってさ、迷路みたいに複雑だったりすることもあるんだよね。例えば目立つランドマークみたいなものもほぼなくて、似たり寄ったりな家並みや木々ばっかりだから、不思議と道にも迷いやすい構造になっている。そういう経験を繰り返すうちに、自分はこの種のコミュニティにはもう苦手意識しか持てなくなった感じ。でもまあ、人によって居心地いいところは違うし…いや自分には合わないかなと思いつつ、本筋へ戻ろう。
逆に考えてみると、「否定形」として浮かぶもの―つまり人里離れた自然豊かな美しい空間、本当の生き物たちが息づくような場所―そこで迎える引退生活への憧れというか関心が段々強まった気がするんだよね。こんな風に書いておいて、本当にそんな環境で落ち着いた日々を送れるのかなあとふと思ったりもするけど…まあ、それでも今は「いつの日か叶えばいいな」というくらいで止めておこうと思う。
ツイン・ピークスの夢―山奥で静けさを求めて
「ツイン・ピークス」って、私の好きなテレビ番組のひとつなんだよね。もし観たことがないなら、あ、そういえば写真をここに挿入しようと思ったけど…やっぱり言葉で説明した方がいいかな。ま、とにかく。山々に囲まれてさ、世間からちょっと離れてる感じで、自然の中で生きている――そんな暮らしに妙に惹かれちゃうんだよね。[ツイン・ピークス;出典:Nevertwhere] まあでも、それって実際にはなかなか難しい話なんだよなぁ。引退してシンプルで満ち足りた静寂の日々を送るとか、一見素敵だけど現実的じゃない願いなのかも…いや、誰が決めたんだろう? いや、違う。本当にそれが夢物語なのか自分でもわからなくなる。
えっと、このエッセイで言いたいのは結局こういうことなんだ――欲望に溢れた世界では本当の意味で満足することって無理なんじゃないかって思う。現代社会は一見進化しているようだけど、その裏側では皮肉にも何かを失って後退している気がするんだよね。不思議なもので、消費というものなしには成り立たなくて、人間の欲求を絶えず刺激するためだけに巧妙につくられた仕組みに私たちは四六時中踊らされているみたい。それなのにさ、「少しだけで十分」と心から思える瞬間はほとんど訪れないし、多くを手に入れてもなお満ち足りない気持ちになることすらある。不条理と言えば不条理だけど…。ま、いいか。また話が逸れそうになったけど、本筋へ戻そう。
えっと、このエッセイで言いたいのは結局こういうことなんだ――欲望に溢れた世界では本当の意味で満足することって無理なんじゃないかって思う。現代社会は一見進化しているようだけど、その裏側では皮肉にも何かを失って後退している気がするんだよね。不思議なもので、消費というものなしには成り立たなくて、人間の欲求を絶えず刺激するためだけに巧妙につくられた仕組みに私たちは四六時中踊らされているみたい。それなのにさ、「少しだけで十分」と心から思える瞬間はほとんど訪れないし、多くを手に入れてもなお満ち足りない気持ちになることすらある。不条理と言えば不条理だけど…。ま、いいか。また話が逸れそうになったけど、本筋へ戻そう。
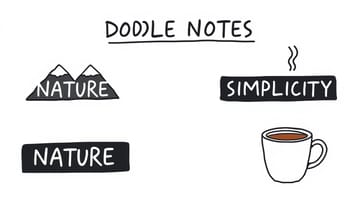
足りない満足、消費社会の無限ループ
主張に入る前に、ちょっとだけ、人がどうやって「満足」するかを考えてみたい。うーん、なんだっけ、この話…ああそう、今回はフランスの精神分析家ジャック・ラカンの理論を使いたい気分。人間というものは本質的に何かしらを追い続ける性(さが)だと言われていて、それが完全な形で手に入る日は来ない、とよく語られる。でもさ、欲しいものが仮に手元に来ても、不思議とまた新しい欲望が湧いてしまうんだよね。なんだろうこれ、本当に面倒な性質。
現代アメリカはこの心理的構造を活用している――って話も耳にするけど、本当なのか少し疑わしい気もする。まあそれはそれとして…。つまり我々の背中に誰かが乗ってて、前方には棒からぶら下げたニンジン、そのニンジン(商品)めがけて延々歩かされる羽目になる。そのあと、新しくより大きなニンジン(広告だったりiPhoneだったり)が差し出されてさ、それがずっと繰り返される…おそらく人生の終わりまで。こんな仕打ち、もうやめたいと思った時には、多分死ぬことでしか解放されないのでは、とすら言える。
この欲望を媒介している存在こそ、人間社会全体にも巨大な影響力を持つと考えられている…いやほんと、厄介極まりない。それって国家とか企業とか英雄とか悪役とか色々あるよね。あと忘れちゃいけないのは、「私たち自身」が自分で欲望をコントロールしているようでも実際は違ってて、周囲の世界とか文化とか言語や教育、それから「学ばないこと」すら含めて外部から管理されている――そんな視点もちらほら見受けられる。本当に、自分で選んでるつもりでも全部仕組まれてたりして。怖いよね。でもま、いいか……話戻すか。
現代アメリカはこの心理的構造を活用している――って話も耳にするけど、本当なのか少し疑わしい気もする。まあそれはそれとして…。つまり我々の背中に誰かが乗ってて、前方には棒からぶら下げたニンジン、そのニンジン(商品)めがけて延々歩かされる羽目になる。そのあと、新しくより大きなニンジン(広告だったりiPhoneだったり)が差し出されてさ、それがずっと繰り返される…おそらく人生の終わりまで。こんな仕打ち、もうやめたいと思った時には、多分死ぬことでしか解放されないのでは、とすら言える。
この欲望を媒介している存在こそ、人間社会全体にも巨大な影響力を持つと考えられている…いやほんと、厄介極まりない。それって国家とか企業とか英雄とか悪役とか色々あるよね。あと忘れちゃいけないのは、「私たち自身」が自分で欲望をコントロールしているようでも実際は違ってて、周囲の世界とか文化とか言語や教育、それから「学ばないこと」すら含めて外部から管理されている――そんな視点もちらほら見受けられる。本当に、自分で選んでるつもりでも全部仕組まれてたりして。怖いよね。でもま、いいか……話戻すか。
ラカン的欲望:本当は自分の願いじゃない?
欲望って、結局のところ他者の欲望なんだよなあ。あ、自分だけのものじゃないって話ね。たぶんさ、人は「自分が何を求めているか」よりも、「他人にどう見られたいか」とか、「こう思われたい」みたいなのを優先してたりするし。えっと……いや、これ本当にそうなんだろうか? ちょっと前にラカンの話読んで、それ以来ずっと頭から離れなくてさ。「理想的な私(Ideal-I)」――そんなものになりたくて、自分自身を必死で演じちゃうとか、まあ、馬鹿みたいだと思いつつもやめられない。
……おっと話逸れてるけど、とにかく、その投影こそが自己同一性になるわけ。でも実際は、私たちは「常に他者の領域にいる」――これはラカンが書いてたっけ――という状況下で満足について悩む羽目になる。ま、いいか。
欲望の世界ってさ、自分だけじゃ完結しないんだよね。本当は全部自分由来だったら楽なんだけど、象徴界(symbolic order)っていう記号体系によって支配されてるから厄介なんだ。それ考えると、「本当らしさ(Authenticity)」って自己そのものが偉いわけじゃなくて、「自己たちの選択」が優位性持つ感じになる。ああ、この言い方変かな。でも……まぁ、大体そんな感じ。
……おっと話逸れてるけど、とにかく、その投影こそが自己同一性になるわけ。でも実際は、私たちは「常に他者の領域にいる」――これはラカンが書いてたっけ――という状況下で満足について悩む羽目になる。ま、いいか。
欲望の世界ってさ、自分だけじゃ完結しないんだよね。本当は全部自分由来だったら楽なんだけど、象徴界(symbolic order)っていう記号体系によって支配されてるから厄介なんだ。それ考えると、「本当らしさ(Authenticity)」って自己そのものが偉いわけじゃなくて、「自己たちの選択」が優位性持つ感じになる。ああ、この言い方変かな。でも……まぁ、大体そんな感じ。
他者から見られる私、理想像と自己欺瞞
主体ってさ、伝統的な「実存主義」だとかリバタリアンの言うところのオーセンティシティ――ほんとにそんなものを持てるんだろうか。うーん、まあ…持てない気がしてしょうがない。ジャン=ポール・サルトルの話を例に出すなら、マネキンを本物の人間だと思い込んでいる自分と、それがやっぱり偽物だって気づいた瞬間の自分――どっちも同じ一つの存在なんだよね、不思議なほど。結局その両者は全体としてアイデンティティという大きい塊の、等しい部分になってるらしい。
えっと、個人のアイデンティティはたぶん、自分が「こう見られたい」みたいな願望?…いや希望かな、それによって形作られていくような気がする。でも不思議なのは、その理想像を追い求めてる時こそ幸福感に満たされやすかったりして、もう既に「理想通りになった!」と感じても他人から認められてなければ案外不安になったりもする。それって皮肉じゃない?
ちなみに、「他者から見えてる自分」とか「誰にも見られていない時の自分」、どちらも結局それぞれ一つのバージョンと言えるわけで…。ああでも、一応断っておくけど、それだけが唯一無二の自己ではなくて―なんというか色々違う自己たちが並走してるイメージなんだよね。「ま、いいか。」ちょっと脱線したかも。
内面的には理想的な自我(Ideal-I)をどうしようもなく追求しようと頑張っちゃう。その過程ではふと自己欺瞞――ごまかしみたいなの――が顔を出したりして。また逆側では外部への投影という手段で、「こんな自分です!」と表現することもしばしば。でも結局この話題になると、「オーセンティック(真正)」になるためにはまず、その状態そのものが根本的に無理なんじゃないかな、と認めちゃうしか道は残されてない…そんな気もしなくはない。
えっと、個人のアイデンティティはたぶん、自分が「こう見られたい」みたいな願望?…いや希望かな、それによって形作られていくような気がする。でも不思議なのは、その理想像を追い求めてる時こそ幸福感に満たされやすかったりして、もう既に「理想通りになった!」と感じても他人から認められてなければ案外不安になったりもする。それって皮肉じゃない?
ちなみに、「他者から見えてる自分」とか「誰にも見られていない時の自分」、どちらも結局それぞれ一つのバージョンと言えるわけで…。ああでも、一応断っておくけど、それだけが唯一無二の自己ではなくて―なんというか色々違う自己たちが並走してるイメージなんだよね。「ま、いいか。」ちょっと脱線したかも。
内面的には理想的な自我(Ideal-I)をどうしようもなく追求しようと頑張っちゃう。その過程ではふと自己欺瞞――ごまかしみたいなの――が顔を出したりして。また逆側では外部への投影という手段で、「こんな自分です!」と表現することもしばしば。でも結局この話題になると、「オーセンティック(真正)」になるためにはまず、その状態そのものが根本的に無理なんじゃないかな、と認めちゃうしか道は残されてない…そんな気もしなくはない。
本物らしさは幻想?選択が生む偽りの自分
オーセンティシティ(本物らしさ)って、まあ神話だよね。でもなぜか、それが人間の幸福にとっては、かなり重要だったりもする。なんでそんなに気になるんだろう……ああ、そういえば昔から「自分らしく」みたいな言葉が氾濫してるけど、本当に必要なのか?とも思う。で、この神話はやっぱり批判されて然るべきものなんだけど、実はそれだけじゃなくて、非神話的なアイデアによって置き換えるべき時期なのかもしれない。
つまり、「絶対的な自己認識」を追い求めるよりも、「絶対的な選択による認識」に至るほうが現実的なんじゃないか、と考えたりするわけだ。ま、いいか。この発想では、自分がどう認知されたいのかを自分で決めて、そのイメージを手に入れるために行動していく。その過程で、自分の理想と異なるふうに見てくる集団からは自然と離れていったりもする。いやほんと、付き合いたくない人とは距離を取ればいいということなのかな。
だからオーセンティシティって、必ずしも集団的アイデンティティ全否定とかじゃなくて、自分が所属したいグループを選ぶという形でも現れるんだと思う。「こう見られたい」という姿を他者にも認めてもらえる人たちを周囲に選びつつ、自分自身の感覚や価値観まで無理して周囲に合わせようとはしない。その逆で――他者や環境そのものを少しずつ、自分のイメージ像に近づけたり調整したりする感じだろうか。
この辺から推察すると、人間って根本的にはコレクティビスト(集団志向)的存在なのかな、と結論づけたくなる瞬間もある。しかし反社会的行動って、多くの場合「承認の危機」から生じるんじゃないかと思えてならない。他者(Other)が主体(subject)として個人をちゃんと承認できず、その結果として幸福の前提条件となる承認から疎外されちゃうことになる。えっと、それで一部の人々は承認そのものを拒むようになったり、人間特有と言われがちな共同体意識や関係性そのものから距離を取り始めたりもする。
これら全部まとめて考えると…利他的行為とか倫理的行動こそが個人の幸福感につながりやすい理由もちょっと見えてくる気がする。本当かわからないけどね。
つまり、「絶対的な自己認識」を追い求めるよりも、「絶対的な選択による認識」に至るほうが現実的なんじゃないか、と考えたりするわけだ。ま、いいか。この発想では、自分がどう認知されたいのかを自分で決めて、そのイメージを手に入れるために行動していく。その過程で、自分の理想と異なるふうに見てくる集団からは自然と離れていったりもする。いやほんと、付き合いたくない人とは距離を取ればいいということなのかな。
だからオーセンティシティって、必ずしも集団的アイデンティティ全否定とかじゃなくて、自分が所属したいグループを選ぶという形でも現れるんだと思う。「こう見られたい」という姿を他者にも認めてもらえる人たちを周囲に選びつつ、自分自身の感覚や価値観まで無理して周囲に合わせようとはしない。その逆で――他者や環境そのものを少しずつ、自分のイメージ像に近づけたり調整したりする感じだろうか。
この辺から推察すると、人間って根本的にはコレクティビスト(集団志向)的存在なのかな、と結論づけたくなる瞬間もある。しかし反社会的行動って、多くの場合「承認の危機」から生じるんじゃないかと思えてならない。他者(Other)が主体(subject)として個人をちゃんと承認できず、その結果として幸福の前提条件となる承認から疎外されちゃうことになる。えっと、それで一部の人々は承認そのものを拒むようになったり、人間特有と言われがちな共同体意識や関係性そのものから距離を取り始めたりもする。
これら全部まとめて考えると…利他的行為とか倫理的行動こそが個人の幸福感につながりやすい理由もちょっと見えてくる気がする。本当かわからないけどね。
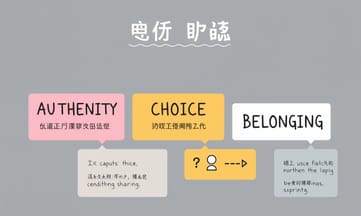
コミュニティと承認、孤立した時の心の傷み
資本主義が、いや、そもそもなんでこう…得意なのは、認知を手に入れるための奇妙な仕掛けを次々と編み出すことだと思う。たとえば、時計とか服とか靴とか音楽――まあ、消費できる商品ってやつ、どれもそう。うーん、この辺り考えているとつい昔買った変なTシャツ思い出しちゃうんだけど、それはさておき。これらの商品、一見するとただのモノだけどね、自分自身を別のアイデンティティへ作り替える方法になったり、選んだ集団になじもうとする時にも使われたりしてるわけ。
えっと、この前ちょっと話題にした比喩を引っ張るなら、「商品=ニンジン」、で「企業=そのニンジンぶら下げて歩いてる人」とか言えそう。変な例えかな。でも、本物じゃなくても認知されることで妙に満足感が出てくる瞬間があるんだ。不思議だよね。例えばさあ…仏教の僧侶って質素なミニマリズム生活してるイメージだけど、その閉じた集団内では確実に承認されていて――外から見ればそれで純粋に満足しているようにも映っちゃう。
それでも結局さ、どんな辛い思いがあっても、その先に在る“もっと求めているもの”――つまり真の悟り――には届かない、と昔から言われているらしい。この辺、ご住職さん本人たちはどう感じてるんだろう? ま、ともかくとして。欲望が苦痛を飛び越えて、その渇望そのものや社会的認知によって意味付けされた時、人間は幸福感を得たりする考え方もあるわけで。ところで最近ラーメン食べ過ぎなんだよね自分……でも戻ろう。
この欲望と痛みの重なり合いの中から、ときには逆説的な執着、“つまり痛みそのものへのこだわり”が生まれることすらあるという。この苦しみの源泉自体が新たな欲望を引き寄せたりして、それゆえ困難な時期にも、その欲望というやつが不思議と導き手になる可能性まで示唆されていたりする。不条理だけど現実味ある気もしなくはない…。
えっと、この前ちょっと話題にした比喩を引っ張るなら、「商品=ニンジン」、で「企業=そのニンジンぶら下げて歩いてる人」とか言えそう。変な例えかな。でも、本物じゃなくても認知されることで妙に満足感が出てくる瞬間があるんだ。不思議だよね。例えばさあ…仏教の僧侶って質素なミニマリズム生活してるイメージだけど、その閉じた集団内では確実に承認されていて――外から見ればそれで純粋に満足しているようにも映っちゃう。
それでも結局さ、どんな辛い思いがあっても、その先に在る“もっと求めているもの”――つまり真の悟り――には届かない、と昔から言われているらしい。この辺、ご住職さん本人たちはどう感じてるんだろう? ま、ともかくとして。欲望が苦痛を飛び越えて、その渇望そのものや社会的認知によって意味付けされた時、人間は幸福感を得たりする考え方もあるわけで。ところで最近ラーメン食べ過ぎなんだよね自分……でも戻ろう。
この欲望と痛みの重なり合いの中から、ときには逆説的な執着、“つまり痛みそのものへのこだわり”が生まれることすらあるという。この苦しみの源泉自体が新たな欲望を引き寄せたりして、それゆえ困難な時期にも、その欲望というやつが不思議と導き手になる可能性まで示唆されていたりする。不条理だけど現実味ある気もしなくはない…。
時計や服や音楽…商品で埋める空虚な幸福感
痛みって、欲望をなんとなく感情的に近づけてしまう…そういう役割がある気がする。いや、違うかもしれないけど、でも、やっぱり強くしてるよね、多分。仏教の僧侶たちが説く「満足」というのはさ、普通に売られている「幸福」とは似て非なるものだと思うんだ。ああ、それについて考えてたら急に冷蔵庫の音が気になったけど、とりあえず戻ろう。
幸福のレシピ――まあ言い方変だけど――って数千年経ってもほぼ変わらないんだよな。不思議だよね、物質的な条件とかすごく様変わりしたはずなのに。でも実際にはそれは主として社会的な側面から成り立っている。幸福とはつまり承認されることで得られる充足感なんじゃないかと僕は思っていて…いや、本当に?自信ないなあ。でもそう書かれてきたし。
で、「満足」についてだけど、これはもう完全に物質的条件から離れた場所で成立する承認による充足――だからこそ純粋な幸福と言えるのでは?いやーどうなんだろう。それと現代の「幸福」は明らかに異質でさ、商品化を通して媒介されちゃっている感じが強い。ま、それも時代かな。
考えてみれば社会的なもの全般が今や商品化されていて、その上で幸福も社会由来だから結局商品化されたものもまた社会的という理屈になる……うーん、ごちゃごちゃしてきた。でもつまり、「幸福」自体すら商品っぽい存在になっちゃったとも受け取れるわけで。
この仕組みのおかげで現代では、「商品」と「幸福」がしばしば同じものとして扱われやすい状況になっている気がする。ふとベランダ見てボーッとしたけど、本題へ戻る。この構造では、人々は短命的な存在――例えば仏教僧侶と一緒に消えてしまう何かだったり、アメリカの消費者が新製品を買う度に消滅していく何かだったり――そんなものへの欲望を抱きやすい世の中になったんじゃないかな、とぼんやり思う。ま、いいか。
幸福のレシピ――まあ言い方変だけど――って数千年経ってもほぼ変わらないんだよな。不思議だよね、物質的な条件とかすごく様変わりしたはずなのに。でも実際にはそれは主として社会的な側面から成り立っている。幸福とはつまり承認されることで得られる充足感なんじゃないかと僕は思っていて…いや、本当に?自信ないなあ。でもそう書かれてきたし。
で、「満足」についてだけど、これはもう完全に物質的条件から離れた場所で成立する承認による充足――だからこそ純粋な幸福と言えるのでは?いやーどうなんだろう。それと現代の「幸福」は明らかに異質でさ、商品化を通して媒介されちゃっている感じが強い。ま、それも時代かな。
考えてみれば社会的なもの全般が今や商品化されていて、その上で幸福も社会由来だから結局商品化されたものもまた社会的という理屈になる……うーん、ごちゃごちゃしてきた。でもつまり、「幸福」自体すら商品っぽい存在になっちゃったとも受け取れるわけで。
この仕組みのおかげで現代では、「商品」と「幸福」がしばしば同じものとして扱われやすい状況になっている気がする。ふとベランダ見てボーッとしたけど、本題へ戻る。この構造では、人々は短命的な存在――例えば仏教僧侶と一緒に消えてしまう何かだったり、アメリカの消費者が新製品を買う度に消滅していく何かだったり――そんなものへの欲望を抱きやすい世の中になったんじゃないかな、とぼんやり思う。ま、いいか。

僧侶が笑う一方で消費者は短命な喜びに沈む
仏教の僧侶って、ああ、なんだろうね、生涯ずっと極めて原始的な物質環境に身を置きつつも、それで案外満ち足りていられるらしいんだ。でもさ、一方で商品化された現代人というやつは、消費してる間だけしか幸せじゃない気がする。いや、そういう話どこかで聞いた気もするけど、自分がそう感じてるだけかもしれない。結局、本当の満足にはなかなか辿り着けなくて、偽りの歓喜とか一瞬の快楽に縋ってるような…まあ、そんな感じ。うーん、言い換えるとヘドニズムなのかな。ま、それはさておき。
これが実は、自分の不安の根源なんだよね。変な話だけど、自分は退職後にちゃんと満足できるのかって思ったりする。だってさ、この社会で生き抜くためにはインターネット使いこなしたり携帯電話持ったり、それからメディア理解したりしなくちゃならないわけじゃない?時々それ全部投げ出したくなるけど、隠遁者になる勇気も正直ないし…資本主義的欲望というか――消費主義?それがもう逃れがたいものになっちゃってると思うんだよ。
アメリカで満ち足りて暮らすこと自体が、どれほど努力しても年々難しくなっているみたいでさ(たぶん他所でも似たようなもんだけど)、課題としては達成可能ではあるものの、その先に立ちはだかる崖みたいなのを想像してしまう瞬間がある。えっと、とにかく……だからこそ、自分は老後について漠然とした不安を抱えてしまうんだよね。
これが実は、自分の不安の根源なんだよね。変な話だけど、自分は退職後にちゃんと満足できるのかって思ったりする。だってさ、この社会で生き抜くためにはインターネット使いこなしたり携帯電話持ったり、それからメディア理解したりしなくちゃならないわけじゃない?時々それ全部投げ出したくなるけど、隠遁者になる勇気も正直ないし…資本主義的欲望というか――消費主義?それがもう逃れがたいものになっちゃってると思うんだよ。
アメリカで満ち足りて暮らすこと自体が、どれほど努力しても年々難しくなっているみたいでさ(たぶん他所でも似たようなもんだけど)、課題としては達成可能ではあるものの、その先に立ちはだかる崖みたいなのを想像してしまう瞬間がある。えっと、とにかく……だからこそ、自分は老後について漠然とした不安を抱えてしまうんだよね。
資本主義を楽しみながらも、本物を渇望して
私は、正直なところ、もうすぐこんなことをしなくてもよくなるんじゃないかなって願ってる。ああ、いや、それだけが切実な願いかもしれないけど。こうして文章を書いてMediumやインターネットのどこかに載せている自分――うーん、ちょっと皮肉だよね、とふと思ったりもする。でもまあ、この感覚…なんというか商品とか無限の情報アクセスとか、結局は私自身も楽しんでしまってる現状があるわけで。ま、いいか。
資本主義って短いスパンでは楽しい気がする。夜中に急に思い立って何か買っちゃったり、その瞬間だけ満たされる幸福感?でもさ、長い目で見るとアメリカ生活の商品化による課題――満足感とか、本当に大丈夫なのかなと疑問になることも多い。本当の「欲望」みたいなものって、たぶん時間をかけて意味を持つものなんだろうなとも感じたり。
それで結局、この現代社会そのものが存在意義の希薄さとか浅っぽい幸福しか生まなくなってきている気がして…。一瞬だけ錯覚的に個性的になれたような気分になるけど、それ以上の何者にもならず、本物らしい生き方からは離れてしまうばかり。そう、「本物らしさ」自体も個人主義文化ではやたら強調されがちなんだけど、その「本物です!」みたいなのすら……結局また新しい商品として消費されているようで、不思議だよね。本筋に戻すと、自分でも何が真実味なのかわからなくなる時がある。
資本主義って短いスパンでは楽しい気がする。夜中に急に思い立って何か買っちゃったり、その瞬間だけ満たされる幸福感?でもさ、長い目で見るとアメリカ生活の商品化による課題――満足感とか、本当に大丈夫なのかなと疑問になることも多い。本当の「欲望」みたいなものって、たぶん時間をかけて意味を持つものなんだろうなとも感じたり。
それで結局、この現代社会そのものが存在意義の希薄さとか浅っぽい幸福しか生まなくなってきている気がして…。一瞬だけ錯覚的に個性的になれたような気分になるけど、それ以上の何者にもならず、本物らしい生き方からは離れてしまうばかり。そう、「本物らしさ」自体も個人主義文化ではやたら強調されがちなんだけど、その「本物です!」みたいなのすら……結局また新しい商品として消費されているようで、不思議だよね。本筋に戻すと、自分でも何が真実味なのかわからなくなる時がある。



