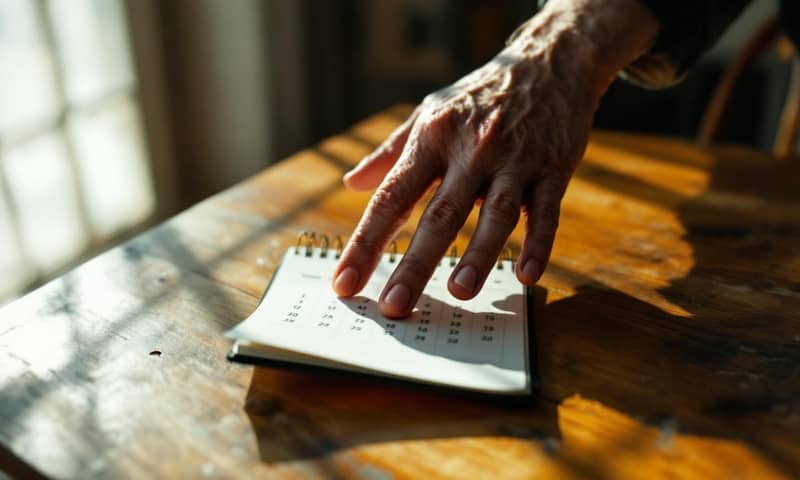最近、ちょっと気になることがあって。親のこととか、将来の自分のこととか…。認知症って言葉、重いよね。😥
でも、いきなり「認知症」になるわけじゃないみたい。その手前の、ほんの小さな「あれ?」っていうサインを見逃さないのが、すごく大事なんだって、いろんな記事を読んでて思ったんだ。今日はそんな、ちょっと気づきにくい変化について、チャットで話すみたいに、つぶやいてみようかなって思います。
「ただの物忘れ」と「あれ?」と思うことの違い
まず、一番わかりにくいのが「物忘れ」だよね。誰だって、歳をとれば物忘れはするし。じゃあ、どこからが「気にした方がいいサイン」なんだろう?
これ、すごく個人的な分け方だけど、無理やり言葉にするとこんな感じかな。病院のサイトとかにも色々書いてあるけど、もっと生活の中での感覚的な違いというか。

| 大丈夫な「物忘れ」 | ちょっと心配な「物忘れ」 | |
|---|---|---|
| 忘れ方 | 「あれ、俳優さんの名前なんだっけ…ほら、あのドラマの…」みたいに、ヒントがあれば思い出せる感じ。 |
朝ごはんを食べたこと自体を、すっぽり忘れてる感じ。「食べてないよ」って本気で思ってたりする。体験そのものが抜け落ちてる、みたいな…。 |
| 自覚 | 「あー、また忘れちゃった、やだなぁ」って、忘れたこと自体はわかってる。 |
忘れたことを指摘されても、「そんなはずない」とか、話がかみ合わなかったりする。忘れている自覚がないことが多いかも。 |
| 探し物 | 「鍵どこ置いたっけなー」って探して、いつもの場所じゃないけど「あ、コートのポッケだ」って見つかる。 |
冷蔵庫の中に財布が入ってたり…。「誰かに盗られた!」って言い出しちゃうことも。しまい忘れたこと自体を忘れてるから、見当違いの場所を探したり、人を疑ったりするんだよね。 |
| 日常生活 | 物忘れはするけど、普通に生活はできてる。 |
ゴミ出しの日を何度も間違えたり、約束をすっぽかしたり、日常生活に「あれ?」っていう支障が出始める。 |
こんなふうに比べてみると、単なる物忘れとは質が違うのかも…って思えてくる。MCI(軽度認知障害)っていう、認知症の一歩手前の段階だと、日常生活はなんとか送れてるけど、こういう「あれ?」が増えてくる状態みたい。
言葉より「行動パターン」の変化に気づく
物忘れって分かりやすいけど、それよりもっと前に出てくるサインがある気がする。それは「その人らしさ」の変化というか、行動のパターンが変わること。
例えば…
- 好きだったことをしなくなる:毎日庭いじりしてたのに、ぱったりやめちゃったり。趣味だった手芸や読書に、まったく興味を示さなくなったり。 「疲れたから」とか言うけど、前は疲れててもやってたのになぁ…みたいな。
- 会話が少しだけ噛み合わない:話が飛ぶとかじゃなくて、なんかこう…会話のテンポがズレる感じ。「うん」「そうだね」は言うんだけど、前みたいに話が弾まない。テレビドラマの内容も、前は感想言い合ってたのに、最近はついていけてないみたいだったり。
- 段取りが悪くなる:料理とか、買い物とか。昔は手際が良かったのに、最近はやたら時間がかかったり、同じものを何個も買ってきちゃったり。 新しい家電の使い方が全然覚えられないのも、サインの一つかもしれない。
- おしゃれや身だしなみに無頓着になる:いつも綺麗にしてた人が、身なりを構わなくなったり。お風呂に入るのを面倒くさがったり。
こういうのって、本人は無自覚なことが多いから、「なんでやらないの?」って聞いても、ちゃんとした答えは返ってこないかもしれない。でも、家族だからこそ気づける「いつものパターンとのズレ」なんだと思うんだ。🤔

海外だと、こういう見方もあるみたい
日本のサイトだと、どうしても「記憶障害」が中心に書かれてることが多いけど、ちょっと面白い視点を見つけたんだ。アメリカのアルツハイマー協会のサイトとかを見てみると、「自発性の喪失(Loss of spontaneity and sense of initiative)」っていうのを、すごく初期のサインとして強調してるの。
これって、さっき話した「好きだったことをしなくなる」とか「人付き合いを避けるようになる」 っていうのに、すごく近い感覚だよね。何かを計画したり、始めたりする意欲そのものが薄れていく感じ。
日本の「公益社団法人認知症の人と家族の会」も、「以前はあった関心や興味が失われた」というのをチェック項目に入れてるけど、海外ではこれが記憶障害と同じくらい重要な早期のサインとして扱われているみたい。文化的な違いなのか、それとも最近の研究でわかってきたことなのか…わからないけど、記憶力だけじゃなく「やる気」とか「関心」の方向が変わってきたら、それも大事な観察ポイントなんだなって思った。
家族として、どう観察すればいい?
じゃあ、もし「あれ?」って思ったら、どうすればいいんだろう。いきなり「病院行こうよ!」って言っても、本人は傷ついたり怒ったりするかもしれないしね…。
多分、大事なのは「問い詰める」んじゃなくて、「観察して記録する」ことなのかな。
- 簡単なメモでいい:「〇月〇日、リモコンの使い方がわからなくなっていた」「〇月〇日、同じことを3回聞いた」みたいに、具体的な出来事を手帳に書いておく。感情的にならずに、事実だけを。
- 本人がいないところで相談する:まずは家族だけで話すとか、地域包括支援センターみたいな場所に、匿名で相談してみるとか。 そういう場所なら、専門医につないでくれたりもするみたい。
- 健康の話から入る:「最近よく眠れてる?」とか「体の調子はどう?」みたいに、まずは体全体の心配から話を振ってみる。そこから自然に、「物忘れとか、気になることない?」って聞けるかもしれない。

決めつける前に考えたいこと
ただ、すごく大事な注意点があって。「あれ?」って思うことが全部、認知症のサインとは限らないってこと。
例えば、うつ状態になると、同じように意欲がなくなったり、頭が働かなくなったりすることがあるんだって。 あとは、耳が遠くなってると、会話についていけなくて、認知機能が落ちたように見えることもある。他にも、薬の副作用とか、他の病気が原因のこともあるみたい。
だから、「認知症だ!」って決めつけるんじゃなくて、「何か心か体のバランスが崩れてるサインかもしれない」って思うのが、一番優しい見方なのかもしれないな。
…と、なんだか色々考えちゃったけど、結局は日頃のコミュニケーションが一番なのかな。変化に気づけるのも、いざという時に話を聞けるのも、普段からの関係性があってこそだもんね。
皆さんは、家族とのコミュニケーションで、どんなことを大切にしていますか? もしよかったら、何かヒントを教えてほしいです。🙏